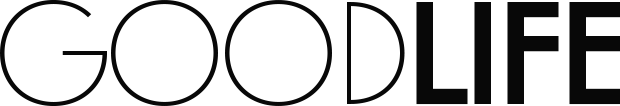乱入者はいないってだれが決めた?
- 問答無用、斬捨御免。
- 原則、冒頭から読めた部分までしか読みません、時間は有限なので。
- 読者の便宜をはかって☆〇△×の4段階評価をカンタンに付けています。
- ブンゲイファイトクラブってなんぞ?という方はご自分でお調べください。
- 以下の批評は、羊谷知嘉個人の責任でおこなうものです。
- 反論歓迎。
1回戦Aグループ
冒頭を読むかぎり、断トツで「巧い」のは金子玲介さん。タイトルで損してるけど。あとはまあ、五十歩百歩かなー。
ブンゲイファイトクラブ1回戦Aグループ|BFC ブンゲイファイトクラブ @ken_nishizaki|note(ノート) https://t.co/WRQZHiKT4O
— 凍結の批評者、羊谷知嘉 (@ChikaHitujiya) September 29, 2019
ここに厚さゼロの本があるといったとき、つまりそこに本はない。
叔父はそんなことを考えるのに人生の大半の時間を使ったのだが、わかったことといえば時間が足らなかったことぐらいだったらしい。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Aグループ
タイトル含め、この冒頭の意味段落を読んでおもしろさを感じたものが何人いただろう。
もちろん僕はそのひとりではないし、通常ならばここで読むをのをやめて出会わなかったものとして通り過ぎるのが僕の礼儀であり習わしだ――が、批評コンテンツを作る者としてはそうは問屋が卸してくれないらしい。
作者の大滝瓶太には日本語の基本的な文章能力があり、その点は評価できる。
作中後半部には大滝の独創性が垣間見える部分もなくはない。
しかし、引用した冒頭に続く比較的大きな段落全体が叔父とその部屋の「説明」にあてられており、端的にいえば読む気が失せる。
小説が好きで好きでしょうがない、質は問わないから空気のように吸っていたいという読者であればこの先も読め進められるだろうが、僕はそうではないし、今は娯楽コンテンツの量にも種類にも困ることは決してない時代だ。
大滝に文学的教養がないとはおもわないが、何を評価し、だれを尊敬するかが、控えめな言い方をすれば僕とは決定的に異なっているのだろう。
すくなくとも僕は、作品冒頭というすべての鑑賞者が観たり聴いたりする部分を「説明」というもっとも退屈なもので埋める作家を芸術的には評価しない。
おまえは立派な大人にはなれない、と言われながら男は育った。時間を守れないのは人として駄目だ、中身がどうでも一人前とはみなされない。たしかに何をするにも人より時間がかかり、集団行動には必ず遅刻した。準備が万全でもなぜか間に合わず、邪魔がひとつでも入ると三十分以上遅れる。それは実は、彼がタイムトラベラーで、体のまわりに重力のひずみが生まれ、他とは違う時間を生きていたからだった。(中略)
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Aグループ
作者の冬乃くじには基本的な文章能力があり、その点は評価できる。
しかし、タイムトラベラーという手垢が付きについたクリシェの唐突な挿入におもわず失笑してしまい読むのを止めた。
ある種の専門用語が日常語に遜色なく溶けこむほどそのコミュニティにどっぷりな読者は何も思わないだろうが、外にいる人間には何の文脈もなしに飛び交う専門用語は冗談としか映らない。
裏返せば、冬乃はタイムトラベラーという専門用語が唐突に出てきても問題ないようなコミカル調で展開するか、短い文章でもこの用語を違和感なく受け容れられるような説得力を冒頭数行に込めるべきだったということだ。
そもそも、タイムトラベラーという設定、あるいはSF的世界観が本当に必要だったのかというと答えはノーだろう。
それは冒頭だけに留まらず、彼がタイムトラベラーだからこそ起こりえた事態は何ひとつ惹起されることなく物語は集束する。
彼は実質的にはタイムトラベラーではなくたんなる文学好きの遅刻魔であり、作中中程で登場するもうひとりのタイムトラベラーの彼女も古典好きのせっかちさんに過ぎない。
こうした事態がなぜ起こるかというと、作者がタイムトラベラーという概念をあくまで言葉のイメージでだけとらえ、作中世界の現実として作品に組み込めていないからだ。
文学作品の素晴らしいところは言葉の上でならすべては自由なことだが、それを絵空事に終わらせないためには構造化の努力が作者に要求される。
蛇足になるが、タイムトラベラーの彼と彼女が対称的に描かれていることもそれが男性と女性なことも恋愛小説のアイデアとしてはいささか陳腐だろう。
「滑走路がない」パイロットが慌てた様子で叫んだのは、着陸予定時刻の十分前だった。
声を聞いた選手たちは下を見ようと窓に張り付くが、何も見えない。見えないものだから、張り付いたまま動こうとしない。順番を変われ、まだ見てない、の応酬が、機体を大きく揺らした。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Aグループ
作者の鵜川龍史には基本的な文章能力があり、書き込みが薄いながらもその要所を押さえた表現から相応の経験を積んだ書き手であることをうかがわせる。
しかし、面白いかというと、控えめにいえば、読者の好みにより分かれるといったところか。
冒頭を読んだだけではわからないが、奇想を筋道立てて重ねることによるナンセンスの面白みがこの作品の魅力であり、結末のひとことにそのエッセンスが凝縮されている。
エロもグロもないという意味ではナンセンスの勢いというか迫力にかける一方、純粋なユーモアに寄せたナンセンスはこの手の作風にしてはより多くの読者に訴求できる可能性はある。
しかし、物事の構造を無意味に変換させていく芸術的スタイルは少なくとも半世紀以上前からあり、今この時代にあえてそれを反復する意味はあるのだろうか、ナンセンスを越えることが時代的に重要だったのではと思わざるをえない。
作者の有する高い技術は感じられるだけに、この作品を構成する面白みの多様さがきわめて貧しいことが残念でならない。
……なに?「起きてる?」起きてるよ「この世で一番うまい食材、発表していい?」だめ「なんでよ」もう寝るから「なんでよ。遠征なんだから、夜更かししてなんぼでしょ」遠征なんだから疲れてるし、明日試合なんだからもう寝るだろ「アボガド」……なにが?「この世で一番うまい食材」……あれか、森のバターか。うまいけど、一番って言われるとちがくない?(中略)
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Aグループ
金子玲介のこの作品は面白いね、素晴らしい。
雑に読むと奇妙な言葉遊びに興じているだけにみえてしまうが、対話劇のような他愛ない掛けあいからふたりの男の子(多分)の心情が生きいきと伝わってくるという意味では文学的であり、その実、本質的にはこの掛け合いはコントの矢継ぎ早なそれであるためきわめて喜劇性が高かったりと、軽妙な雰囲気からは想像できない複雑な構成をしていることが非常にポイントが高い。
文学作品として観た場合、いわゆる地の文が存在せず、鍵括弧のない男の子と鍵括弧付きの男の子の発話が交互に繰り返されるというきわめて制約の厳しいスタイルをとっているので、敢えていえば実験小説の類にはいるだろうか。
しかしながら、会話中でもさりげなく「何かの大事な試合を控えた遠征中のふたり」という情報を「説明」せずに挿入しているため、実験小説にありがちな抽象度の高さ故のちんぷんかんさを巧み回避しており、作者の芸術的センスと会話文を書く演劇的教養をうかがわせる。
また、鍵括弧の無し有りという違いは、無い側がより発するニュアンスが強く、有る側がより聞こえるニュアンスを強くもたらすが、必然的に読者の目線と近くなる鍵括弧の無い側をお笑いでいう常識的なツッコミ役に配置しているのもさすがといったところか。
これほどの複雑でかつ笑える作品を書ける金子を僕なら迷わず優勝候補の一角に挙げるが、実験小説という制約の多さから普通には読みづらい形式をとっているため勝ち進めることはひょっとしたら難しいかもしれない。
なんにせよ、この才能ある書き手を正当に評価されることを審査員の批評眼に期待したい。
1回戦Bグループ
冒頭を読む限り、Bグループも雛蔵さりえさんが断トツで良い。言葉に対する意識のもちかたが芸術を成立させていることを示す好例。ただしこれも、タイトル損。
ブンゲイファイトクラブ1回戦Bグループ|BFC #ブンゲイファイトクラブ https://t.co/7bUZez92rd
— 凍結の批評者、羊谷知嘉 (@ChikaHitujiya) September 29, 2019
ぼちゃん、ぼちょん、と音がする。重たいものが水面にぶつかり、沈んでゆく音。とぎれることなく、一定の間隔を保って、音はたつ。ぼちょん。ぼしゃん。夫の細い背中が、カーテンを閉めた部屋で淡く燐光を放っている。奥に設置された巨大な水槽の中身は、暗くてよく見えない。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Bグループ
作者の雛倉さりえは本大会中最も言葉の美しさに意識を払った書き手であり、それゆえ多くの読者に支持されそうなことも加味したうえで優勝候補の大本命といえそうだ。
僕から観てもこの意識の払い方は正当なもので、世の少なくない書き手が文学作品があくまで言語表現であること、別の言い方をすれば言葉を媒体とすることを忘れがちだが、文学作品を芸術と考えるかぎりこの媒体への情熱と意識の透徹はただしく、雛倉のそれは耽美的傾向がときたま鼻につくものの高水準にあることは疑いえない。
また、雛倉のこの作品は全体としても非常にわかりやすく不明なことがない。
絵に描いたような気弱で裕福な夫とおなじく定型的な「悪い女」のわたしーーこの夫婦が怪奇風の「飼育」を通して奇妙な心の通わせ方をするところにこの物語の面白さがある、といえるかもしれないが、作品のわかりやすさは美点であると同時に短所でもありうることは以前書いた解説記事のとおり。
この作品の場合、主要登場人物の男女が紋切り型なのもそうだが、ふたりの「関係の正解」の原光景が新婚旅行で眺めたナイアガラの大瀑布(たぶん)というのがなんともわかりやすく、浅はかで、説得力に欠ける。
と、厳しいことを書いたが、雛倉の文体に比べれば内容面に難があるというだけで、優勝候補の強力なひとりに推すことに異存はない。
水天宮前駅に、タイから帰ってきた彼女を迎えに行った。改札前で、彼女を待っていると、知らない女の子に声をかけられた。
「まいこです」女の子はそう言った。古い黄色のスーツケースをガラガラと僕に近づきながら。僕は、そうですか、と答えて、彼女が現れるはずの改札を眺めた。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Bグループ
こ、この冒頭をどうおもしろがれと?
ひとの趣味にも多少はよるが、人類史上、いまほど多様でたくさんの娯楽コンテンツが遍く安価で溢れた時代は片時もなかったわけで。
実際、音楽業界ではアルバムが売れなくなっているだけでなく楽曲の長さもどんどん短くなっている現実があるわけで。
YouTube 然り、SNS 然り、Netflix 然り、Twitch 然り、旧来のジャンルを越えた無限にも思えるコンテンツの小宇宙が日夜僕らの有限の時間を奪いあっていることを思うと、タイトル含め冒頭におもしろさを感じさせない小説はきわめて致命的だと僕は考えます、ハイ。
作品自体の話をすると、主語と述語の関係とその対応が怪しかったり修飾と被修飾関係が混乱していたりと作者の文章能力に疑問を覚える箇所もまま散見される。
たとえば――
「どうしましたか?」女性の駅員は、口をあけたまま黙っている僕を無表情といえばこれだと、サンプルとして見本市に出せるような表情でこちらを見つめていた。
もちろん、通常の日本語文法や対応関係をあえて崩す文章表現もなくはないだろう。
しかし、文章を読みづらくしてまで何か得られるものが、たとえば音楽的な音韻の連なりであったり語り手の特殊な性質だったりがこの作中に僕が眼を通しえた範囲内であったとはおもえない。
また、こうしたあからさまに稚拙な作り手を稚拙であるがゆえに評価する価値観が世にあることも知っているが、僕個人の評価基準にそういったものは存在しない。
彼は卒業式の日に思いを寄せていた女の子に告白をしようと思い、校庭の木の下に彼女を呼ぶ手紙を出した。
時間になった。彼女は来なかった。三十分待っても、一時間待っても彼女は来なかった。彼の同級生たちはみんな打ち上げに行ってしまった。彼も形だけは呼ばれてはいたけれども、行くことはできなかった。(中略)
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Bグループ
タイトルの気持ち悪さから読む気が失せたのは僕だけだろうか。
最初の1行も言葉のリズムが詰まり気味で、文学作品があくまで言葉を媒体にした言語芸術であることを前提とすれば大きなマイナスだ。
だれかを待つ、とはどういうことだろう?
最終的に彼は文字通り宇宙の崩壊を超えてもなお彼女を待ち続けたらしいが、彼が人間であれ、超自然的な何かであれ、あるいは超自然的な何かに変化した元人間であれ、何かひとつのものを50億年以上待ち続けたことには変わりない。
この作品の問題は、何かを待ち続けるという行為がたとえ数時間程度であってもカンタンではないことで、心理的変化のみならず、摂食、飲水、排泄、睡眠、性欲処理といった生理的変化とも闘わなくてはならない――それも待ちながらである。
待ちながらどうやって食糧を調達する?
トイレに行っているあいだにもし彼女が来てしまい行き違いになったら?
告白するものが相手に寝顔を晒すリスクを負ってもいいのか?
そして、不審者を観るように通り過ぎるひとたちや実際に通報に出るひとといった外的環境からの干渉がある――戦争や宇宙崩壊まで起きているならなおさらだろう。
100歩譲って彼が生理的変化もなければ外的環境からの干渉も受け付けない超自然的存在だとしても、彼には彼なりの変化や影響があるはずだ。
ないとしたら、それはたんに待つという行為がディテールを欠いた絵空事としてしか書かれてないということだろう。
若い頃、僕自身もたった数時間だけだが「彼女」をひたすら待ち続けたことがあった。
50億年に比べれば塵芥にも劣る短い時間で、汚染物質のない晴れた夜空に流れ星を眺めることさえなかったが、僕の人生ではもっとも辛い出来事のひとつとして深い心の痛みとともに記憶されている。
女なら誰でも知っていることだが、生理は伝染る。旅行や合宿はもとより日帰り観光でも伝染る。三人いてその中の一人だけが生理中でも帰りになると全員が生理に伝染っている。未だ原因は解明されていない。現代であっても科学者は男が圧倒的に多い。男たちは女のからだに性的な興味があっても、女のからだの本質には興味がないのだ。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Bグループ
男ならほとんどは興味をもてないだろうが、生理は伝染らないらしい。
数年前に排卵期予測アプリの Clue が英国のオックスフォード大学とパートナーシップを結んで調査した最新の研究によると、女性の月経周期のシンクロ現象はたんなる偶然で、同居状態にある女性グループにおいても月経周期への影響は見られなかったそうだ。
語り手である「わたし」はこの現象の原因は未解明としているが、実際のところは一致した偶然の方が認識にのぼりやすく、そうではないハズレは意識すらされないという人間のパターン認識の性質に基づくものらしい。
興味がある方はこちらの Wired の記事を、カンタンな英語が読める方はこちらの Guardian の記事を読まれることをお勧めする。
たしかに科学者の男女比は世界的にみても大きな偏りがあり、深刻な問題であることに異論はないが、月経周期のシンクロ現象という都市伝説を否定するこの研究をおこなったグループのひとりは Marija Vlajic という名の女性データサイエンティストで、なによりこの小説を読む前から知っていた僕は生物学的にも性自認的にもまがうことなき男性だ。
男性の大多数が女性のからだに性的な興味はあってもその本質には興味がないという言は男性として否定できないが、人間には外れ値といえるひとも極少数ながらおり、そういうひとたちが自分の作品を読む可能性も書き手としてはあたまに入れておいた方が良いだろう――LGBTQの人物があたりまえのように映画やドラマに登場する現代ならなおさらだ。
もっとも、こうした貧しい男性観を語り手の「わたし」の性質として描くこと、あるいは読者にそう受け容れさせることは本質的にはできる。
だとしたら読者と「わたし」の緩衝材になり、語り手である「わたし」の視点を相対化する別の視点なりオブジェクトなりが必要なのだが、竹花のこの作品にはそれらがなかったため文学的意匠としては不出来といわざるをえない。
また、現実の科学的事実とは異なることがらを作品世界の基盤にすることももちろんできるが、それならその世界観設定を読者に無理やり納得させる文脈上の説得力が必要になる。
作者の竹花が生理周期のシンクロ現象がたんなる俗説に過ぎないことを知っていたかどうか確定的な判断は下せないが、知らなかったとしたら自分の考えや言葉を書くまえに軽くグーグル検索しておくべきだし、知っていたとしたら空想を作品の根幹にすえるための文学的技量をみせるべきだっただろう。
とはいえ、日本社会において女性と男性の公然と語ることが避けられている不都合なことがらを採りあげた社会性は高く評価したい。