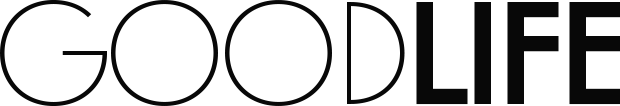真の闘いの勝利者はここにいる
- 問答無用、斬捨御免。
- 原則、冒頭から読めた部分までしか読みません、時間は有限なので。
- 読者の便宜をはかって☆〇△×の4段階評価をカンタンに付けています。
- ブンゲイファイトクラブってなんぞ?という方はご自分でお調べください。
- 以下の批評は、羊谷知嘉個人の責任でおこなうものです。
- 反論歓迎。
1回戦Dグループ
冒頭を読むかぎり、ここは良い意味でも悪い意味でも問答無用で矢部喬さん。メチャクチャな想像力(褒め言葉)だけど、音楽的センスのある文章でとてもテンポが良い。教養もある。逆ソローキン風の掌篇。
ブンゲイファイトクラブ1回戦Dグループ| #ブンゲイファイトクラブ https://t.co/4jIKVZJgQA
— 凍結の批評者、羊谷知嘉 (@ChikaHitujiya) September 30, 2019
たとえば、格好わるいと思っていたものがいくつかある。
ひとつにはやたらと怖がること。おばけとか、飛んでくる虫とか。叱られただけでも泣いてしまうのにも腹がたった。あとは大声を出されること。うるさいし、そもそもデリカシーに欠ける。それに手をつながれること。名前をちゃん付けで呼ばれることや、誰かれ構わず頼みごとをすること。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Dグループ
余計なことは書かずに淡々といこう。
斉藤優のこの作品の評価を率直にいうと冒頭引用部分だけで読むのをやめたーーとまあ、こんなことを書かなければプチ炎上もなかったわけだが、読み進めることができなかったことはどう控えめな言い方をしても初読時の立派な評価=批評ではないだろうか?
だいたい、ブンゲイファイトクラブの中心界隈では、批評はやれ新しい読み方を提示する、やれ新しい意味を見つけるものと思われているらしいが(あくまで、らしい)、僕自身はこの批評=解釈とする見方はかなり怪しいと思っている。
というのも、もし本当にそうなら作品の出来が良いものにも悪いものにも何にでも新しい意味は付け加えられるし、究極的にいえばサルに描かせた線の羅列にだって新しい読み方を自由にでっちあげることができる。
なにより、その批評の正当性を検証するものがない――だから、フリースタイルラップバトルのように格好良さげなことをそれっぽいカタカナ語で言ったもん勝ちになりやすい。
この批評観で置き去りにされているのは作品自体の価値だ。
だから僕は、作品が何なのかではなくどうなのかに注目する。
考えてみてほしい、ワインの批評家の仕事はその味覚や風味に新しい意味を見出すことだろうか、それがどうなのかという分析から価値を判断するのが仕事ではないだろうか。
斉藤優の作品に話をもどすと、まず、その文章技術はある意味で完成されている。
というのも、ディテールを書かない、あるいは書けないことが結果として語りの醸す愛らしいふんわり感を演出し、好き嫌いが分かれるもののたしかに作品の大きな魅力といえなくもないからだ。
たとえば、「格好わるい」ものとして挙げられた「大声を出されることだが」、続きのひと文を踏まえると、この部分の正確な表現は「他人が大声を出すこと」か「自分が大声を出させてしまうこと」かのどちらかで、控えめにいっても文の意味は結構違うが、なんとなーくのうちに次の文に流れてしまう。
同様に「誰かれかまわず頼みごとをすること」も、自分が思わずやってしまうその性格を指すのか、他者全般、あるいは具体的なだれかのことかがいっさい不明で、結局続く1行で「そんなことを思いながら……(中略)」とまとめられて現在時の語り手の状況に話が移ってしまう。
具体的なエピソードとしてではなく語り手による語り手の説明としては致命的に言葉足らずで、それが書き手の意図によるにせよそうでないにせよ、読み手を作品に入りこませるというよりはなんとなーくの甘い煙に巻いてしまう。
この文体の控えめにいえば書き手の癖というべきものはその後も、たとえば1人称にしてはやけに今いる建物の浸水状況に詳しい語り手の特に位置関係が曖昧で、廊下にある明かりのスイッチを探りあてたとおもったらいつのまにか女子トイレのなかで未知の生物に驚いていたりとやっぱりなんとなーくの雰囲気重視で物語は進んでいく。
だから、この文体のぼやけた感じが好きなひとはなんとなーく読んでなんとなーく読み終わればそれで良い思う、適当な解釈をヘタにはさまずに。
ただ、僕にはそれが作家の拙さであり致命的欠陥にしか映らなかったので芸術的には全く評価できないというだけの話――もちろん好意的に読み進めることも。
桜座でライブがある。
開始時間は午後七時半だった。午後五時半までに野暮用を済ませ、ざっとシャワーを浴びてから、家で飲みだした。
桜座に限るわけではないが、素面でライブに行くことはない。一杯やって、気持ちをリラックスさせてから出かける。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Dグループ
タイトルに「その一」とあるということは続きがあるのだろう、少なくとも作者の手許や脳内にはなかったとしても作品世界ではこの日記の続きを読者に予期させる。
おもえば、ブンゲイファイトクラブの参加作品にはやけにタイトルが残念なものが多かった――僕の価値判断を交えてほしくないなら「淡白」と言い換えても良い。
僕が高く評価したAグループの金子玲介(「アボカド」)や、Bグループの雛倉さりえ(「飼育」)もその例外ではない。
この単語縛りが創作クラスタの流行りなのか日本文学界のスタンダードなのか僕には判断できないが、どうせおなじやり方なら、フレンチやちょっと値の張るイタリアンのように「茄子・マグロ・カルダモン」のように複数単語を並べた方がまだ読者への訴求力は増していたはずだ――やりようによってはタイトルが詩にもなる。
また、僕自身も正直ここまで炎上して悪評を広めるぐらいなら、全作品タイトル批評・本文はいっさい読みません!ぐらい尖りがあってラクなことをすればよかった、本当にこれだけは後悔している、まあ、今からでも遅くはないのかもしれないけれど。
飯野文彦の「甲府日記 その一」は魅力的なタイトルだろうか。
もちろん僕はそうは思わないが、このタイトルの話をする前に基本的な評価をカンタンに書いておく。
この作品は率直にいうと最後までおもしろく読めた――ただし、作家の実際の言葉を無視し、手前勝手な映像監督として物語を脳内展開させていくならば。
初期コーエン兄弟の『ビッグ・リボウスキー』のような摩訶不思議系コメディ調なら相性も良さそうだ。
とはいえ、それが読み方のひとつであったとしても当該作品はあくまで文芸作品であり言語表現なので、自分が愉しむことではなく、作品の価値を判じること、すなわち、批評を考えるなら、映像作品の原作としてどんなポテンシャルをもっていようとも言語芸術として読んで評価すべきだろう。
言語表現として観た場合、この作品は冒頭からあまりにディテールが薄過ぎる――だから面白く読めるかどうかが読者の脳内補完いかんによってしまう。
たとえば、作品冒頭、大事なことだから繰り返すけどもだれもが読む作品冒頭、主人公の飲ん兵衛が午後5時半までに済ませた「野暮用」とはなんだったのだろう?
重箱の隅に難癖を付けているように思えるかもしれないがこう考えるとわかりやすい――ダメ人間繋がりでいうなら「愚図で無能な間抜け」の植川なら野暮用のひとことで済ませただろうか。
たぶん、違う。
植川ならもう少し具体的なディテールを描くことで読者にその人物の人柄を詳細に伝え、主人公の読者のなかで結ばれる人物像にもっと膨らみをもたせていたはずだ。
野暮用を済ますと言葉でいえばカンタンだが、実際には具体的な何かを具体的な行為を通して終わらせるのであって、その何をどうしたというたった1、2行の描き方の巧拙の差がいわゆる登場人物が「生きている」かどうかの明暗にあらわれる。
作者の飯野はこの点で劣るせいか、主要登場人物がたったひとりの割にそのひととなりがあまりよく掴めなかった読者は僕だけではないはずだ。
タイトルの話にもどろう。
結局、主人公が「蟻地獄」に呑まれたあとの世界はなんだったのか。
この読み方は千差万別だが、僕自身は脳卒中かなにかで危篤状態に陥ったのだろうと思った、正確にはそうあってほしい、僕だったらそれを匂わせる映像作品にしたいと強く思った。
最後の場面は、アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督の『Biutiful』のラストシーン、荒涼としていながらも美しく、どこか懐かしさを感じさせるイメージだ。
が、「甲府日記 その一」はその日記の続きを予期させるかぎり僕の解釈はおそらく作家の意図に沿わないものであり、僕個人の妄想に過ぎないのだろう。
タイトルは作品の顔だ。
潜在的読者が、あなたの社会的地位や本の装丁、サイトデザインを除けば最初に接する部分であり、鑑賞者のその後の読みを強く制限するためたしかに題付けはむずかしい。
が、だからこそ、檜舞台にあがる作品の顔にはそれが男であれ女であれ化粧ぐらいはさせてあげてほしいし、できることならほんの少しだけ微笑んでいてほしいと願わずにはいられない、ひとりでも多くの見知らぬ読者のために。
エリザベート、とこの学年では呼びならわしている。
その時折しも劇団四季の「エリザベート」が上演されるとかで、テレビで連日CMが流されていたのだった。この年は学校行事の芸術鑑賞が演劇に当たっており、まさかとは思うがエリザベートだったらやばー、見てえよなエリザベートー、と言い合っていたのだが当然のごとくというか、ごく普通の市民劇団の演劇を見ることになった。(中略)
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Dグループ
正井のこの作品も冒頭2段落目以降は読み進めることができなかった。
原因は明白で、書き出しからたった数行内に指示語のこそあど言葉があまりに多過ぎるため、参照先不明の指示語の意味をいちいち保留にしながら読み進めることがたったひと段落とはいえ大きな苦痛をともなったからだ。
この学年→どの学年だよ!
その時→いつだよ!
その年→だからいつだって!!
こんな調子だ。
何故こういう安易な書き方をしてしまうかというと、おそらく作者が自分の脳内にある作品世界を読者の視点や言葉そのものを無視して書き付けてしまうタイプだからだろう。
表現全般にいえることだが、鑑賞者の前には作品しかない。
正確にいうと、作品しかないという鑑賞上の理想状態を誠実な鑑賞者は心のうちで目指すべきで、なぜかというと作品の外部といえる前評判や作家の社会的地位、あるいは人間関係上の繋がりといった作品自体の価値とはなにも関係ない「臆見」が自分の鑑賞をゆがめるからだ。
また、表現者もこの鑑賞者の理想状態を想定すべきで、というのも、鑑賞者が表現者の頭のなかを覗きみながら鑑賞することができない以上、表現者がどんな壮大な作品世界を構築していようとも、どんな巧妙で奇抜な作品コンセプトを思い付いていたとしても、それがより良く表現できていない限り観賞者の観賞に、つまりは作品評価にはまったく関係ないからだ。
さらにいうと、僕の友だちの言葉を拝借するなら、作家が命を削っていようとも鼻クソをほじりながら書いていようとも眼の前のテキストには関係ないし、当然、身内の読者以外にはなにひとつ関係ないし興味も惹かない。
だいたい、提出期限に追われた学生ならカンタンに命を削って書いてくれるだろう。
自作を好意的に熟読してくれる条件がもし命を削ることなら、毎日毎晩いかに読者や視聴者が楽しんでくれるか試行錯誤を繰り返している人間にとってはひとことでいって甘過ぎるし、お花畑で、世に数多いる研鑽者を愚弄している。
現実無視もいいところの妄言だ。
正井の作品に話をもどすと、多分、僕の冒頭からの作家分析は間違っていない。
たとえば、作品中盤で舞台が女子校というわりと特殊な設定が出てくるが、作品中でこの設定が生かされることは勿体ないというべきかまったくないといって良い。
作家が作品をはさんだ読者とのあまりに遠すぎる距離感をキチンと踏まえていないと、鑑賞者視点では、言葉の使い方が粗雑になり、作品世界を読みながらうまく構築させられず、意識的な努力をはらわない限り読み進めることが困難になる。
一字一句をゆっくり読むタイプの読者が特にそうなってしまう傾向が強いだろう。
当然、僕がそうした作品を高く評価することはできない。
満願成就の夜が来てオールナイトハピネスは会社を飛び出した。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Dグループ
矢部喬のこの小説も冒頭一行以上を読み進めることはできなかった、というのは真っ赤な大ウソで、たったこの一行だけでも大会優勝最有力候補に躍りでるには十分なパワーと破壊力をもっているだろう。
まず、タイトルからして良い。
殺人野球小説は、最後まで読まれた方ならわかるように二重の意味で適切で、「殺人」と「野球」という語句の組みあわせは多くの潜在的読者をおっ?と思わせるほどキャッチーで奇抜といえる。
もちろん、このタイトルに惹かれて読みはじめた読者を本文が裏切ることも飽きさせることもないだろうし、反対に「殺人野球」に道徳的な違和感を覚えるタイプはそもそもこの作品を読むべきでない。
その意味で「殺人野球小説」はまさしく名は体を表すという慣用句を地でいく的確な題付けで、読者の事前選別としてよく機能しうるであろう名タイトルだ。
なにより、これだけのことをたった6字で、気取りも冗長さもなく端的に表現しえたのは天晴れというほかないだろう。
今大会1回戦中、矢部の「殺人野球小説」に比肩しうる名タイトルが他にあっただろうか――僕の意見ではCグループの蕪木Q平の「来たコダック!」がそれで、こちらもなかなかに愛らしさと文体上の特質がよく表現された短くも魅力的なタイトルだ。
また、冒頭1行目も紛うことなき脳殺モノだろう。
「満願成就の夜が来て」など通常の文としてはまったくもって意味不明だが、語感が恐ろしく良いため異常な説得力をもって喉から舌先へ滑りだす――そして続く「オールナイトハピネス」。
これまた常識的な語の組みあわせではないながら、語感が良く、言葉の意味するところはわかりやすいため「オールナイトハピネス」がこの作品の主人公というか主役級の登場人物だということは違和感なく受け容れられる。
これらの奇妙に俗っ気がありながら詩的ですらある語彙の奇抜な組みあわせを冒頭から確信的に砲じられる矢部のキャッチーな言語感覚、完全に「天才」のソレだろう。
作品全体にも少しだけふれておくと、ウラジミール・ソローキンの初期短篇を裏返したような構成はかならずしも矢部オリジナルの独創的なものではないが、元高校球児の意見として、この作品がきわめて完成度の高い高校野球のパスティーシュであり卓抜なブラックユーモアと奇想によるパロディであることに疑いの余地はない。
思い付きで書いてはあるが、思い付きだけでは出来ていないきわめて理知的で教養深い傑作だ。
1回戦Eグループ
冒頭を読むかぎり、ここのグループは本当に五十歩百歩なので大変悩んだが、技術的にマイナス要素の少ない大前粟生さんがいちばん良かった、かもしれない……。#ブンゲイファイトクラブ 1回戦Eグループ https://t.co/C2ld6yQYJe
— 凍結の批評者、羊谷知嘉 (@ChikaHitujiya) September 30, 2019
「早く大きくなりますように」ベビーベッドで寝ている弟にいった。私は早く遊び相手がほしかった。毎日リュウタの前でお祈りをした。リュウタはみるみる大きくなった。一年で私と同じ身体。私くらいかしこい。1歳7か月なのに大人と同じことをいう。いじめられるんじゃないかとお母さんは心配してノイローゼになるほどだったけど、リュウタが連日テレビで取り上げられて、天皇や国連のひとの訪問を受けると地区のひとたちも弟の保育園の友だちもその親もうれしそうだった。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Eグループ
Dグループの作品批評でタイトルについてわりと腰を入れて書いたので繰り返しはしないが、大前粟生の「私の弟」にもやはり否定的な意味でおなじ疑問を思う。
この淡白なタイトル付けでどういう層のどれくらいの潜在的読者への訴求を狙ったかだ。
しかし、ひょっとしたら大前の場合には作品全体に対しても同じことがいえるかもしれない――というのも、僕はこの作品を読んで面白さを感じられなかったし、また、作者がどういう面白さを狙ったかの意図すらも汲みとれなかったからだ。
他の参加作品と比較してみよう。
たとえば、この作品の語り手は11歳とあるので小学5年生前後と推測できるが、ここで思いだされるのはおなじ小学4年生の女の子を語り手としていた蕪木Q平の「来たコダック!」だ。
普通の意味では読みやすい大前の文体と、子どもの日記調の書き言葉を演技として模倣した蕪木の文体、読者の好き嫌いはわかれるにせよより難易度の高いユニークなことに挑戦しているのは蕪木の方だろう。
とはいえ、読みやすい文章を書くのはカンタンではない!不快だッ!という声もあるだろうが、文章のわかりやすさという問題については以前書いた記事を僕の見解として置いておく。
もちろん、大前の文章技術を拙いと批判しているわけではない。
正確にいうなら僕が相応に高く評価する参加作家に比べたら言語に対する意識が低い、といったところか。
実際、以下の引用のように読点の打ち方が文の意味としては適切ではあるものの、音の連なりという観点をおそらくは無視しているため、砕け口調の文体のわりにはテンポの悪い文章もそれなりに多く散見される。
お母さんが出かけてるあいだ、ねえちゃんねえちゃんと私を頼ってきて、最初の方はうれしくて卵を焼いたりしたけど、すぐに飽きた。
では、物語としてはどうかというと、鬼の遺伝子が発現したため成長が恐ろしく速い弟というワンアイデアを現代の日本社会に話を留めて展開したという意味では伊藤佐知子の「期待はやがて飲み込まれる草」と似ているが、社会騒動のユーモアに富んでいる分、伊藤作品の狙いは明確でありそこに面白さを見出すことはそう難しくはない。
また、大前作品はより当事者の方に視点を寄せてそこはかとなく人間の業と哀愁を匂わせているが、作品が描いているその深さという点においてはそこに全振りした植川の「愚図で無能な間抜け」とは比べるべくもない。
要するに、大前粟生の作品は良くなくもないし面白なくもない無難な作品としかいえず、そのそこはかとなさが好きな読者の気持ちはわからなくはないけども、僕の価値観としてはこの淡白な作品をこれ以上高く評価することはできなかった。
標準語話せぬ二人夕立へ
アイスコーヒー来ても黙ったままだった
終電を調べたくない夏に入る
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Eグループ
僕に誇れることが何かあるとしたら恋愛経験の深さだろうか。
それも、交際人数や経験人数ではなく交際期間の長さだ。
中学2年生から5年間、大学1年生から3年間、大学4年生から2年間、終わりの夏に3ヶ月間、大学院3年生から5年?6年目?と考えると、人生の半分近い時間を懸け、思春期の14歳以降はほとんど常にだれかしらと恋に落ち、パーマネントな関係に身も心も投じてきたことになる。
その経験から観て、原英の「抱けぬ身体」は実に甘酸っぱく、浅薄なものに映った。
この作品を高く評価するひとはより前者を重視し、そうではないひとは後者の方が眼に付いたのだろう――残念ながら僕は後者だ。
「抱けぬ身体」は、田舎から上京してきた者たちのひと夏の恋を描いた連作で、突然音信不通になった相手が実は何かしらの事情があり逝去していたことを知るというメロドラマ風の物語が背景にある――これらの句の主体にある程度の一貫性があるならばそれは女性、あるいは女性的な男性で、ひょっとしたら季節はもう1度めぐり心の傷もある程度は癒えている、かもしれない。
僕が特に気になったのは、恋の始まりと終わり、2人称の死という実に身も心も引き裂かれる感情的な経験を物語として追い掛けているにも関わらず、当の句はすべて定型のリズムを守って詠まれ、通常の文法や慣用、語句そのものがなんら壊れる気配もみせなかったことだ。
つまり、作品としての収まりの良さというか律儀さが、連作の背景にある物語をどこか白々しく感じさせている。
ジャンル不問の大会であれば、後半部に紙面1枚をまるまる用いた視覚詩を混ぜこんでも面白かったかもしれない。
もちろん、優れた句がないわけではなかった。
もう抱けぬ身体となって泳ぎけり
これなどは、表題にもなっている「もう抱けぬ身体」が主体の陰惨な過去を予感させると同時に「泳ぎけり」という比較的近い現在時の気楽な動きと組みあわせることで、消し去れない過去の重みを抱えながらも今は飄々と生きようとしている人間の姿を平易な言葉でよく描いている。
しかし、それだけでは物足りないのではないだろうか?
今は地球が壊れ、世界も国も権威もインターネットも割れている時代で、文芸もまたみずからその言葉を壊してきた歴史の上でなお創り続けられる言葉とはたぶん、ここまでなめらかな生肌はしていないはずだ。
たとえば、ホームに入ってくる電車の「つぎ」と「こんど」どちらが先か。
「先発」と「次発」は?
「急行」と「快速」と「特別快速」と「通勤快速」は、どれが早い?
あなたはこんなことでいつも悩む。ええいっ、と電車に飛び乗って、失敗したことは一度や二度ではない。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Eグループ
ググれよ……と思わず呟いた僕はこの作家の想定読者ではなかったのだろう。
出会うべきではなかったと思わせる作品は正直無数にある。
何年も前からVPNを噛ませて Pandra や Spotify でまだ見ぬ音楽を探し続けてきた身としては僕の耳に何の新鮮さも与えずに通り過ぎた楽曲がどれほどあったかとふと考えさせられる。
栗山心の「立ち止まってさよならを言う」も僕にはそういう作品のひとつだ。
飾り気も奇抜さもない素朴で丁寧なよくいえば素直な筆致の2人称体構成で、言葉の小さな矛盾の大きな躓きを掌編的に重ねていくこの作品はまさしく読み手が「あなた」に共感して近付けるかどうか、あるいはこのおっとりとした語り手の雰囲気に愛らしさを覚えられるかどうかで作品の評価というか好き嫌いがわかれそうだ。
もちろん僕はそうではなかったし、冒頭の語り手の主張も気持ちもわからなくはないがそこに作品鑑賞のコストをかけるほどの面白さは見出せなかったので、当然ながら読むのをやめた。
断っておくけども、だからといって技術的に下手だとかそういうことをいっているわけではない。
語り手におっとりとした印象を強く与える細かい読点の打ち方はたしかにひと文が長くなればなるほど読みやすさを損ね、氷菓のくだりなどほとんど一読しただけではその意味を掴めない深刻さだが、それでもこの遅滞した文体の雰囲気も栗山のすでに完成された魅力ととらえる向きもないわけではないだろう。
ただ、僕はそうではなかったし、多種多様なコンテンツがこれほど膨大に溢れかえっている時代にこの作家の悠長な文体に付き合い続けることも高く評価することもできなかった、それだけの話だ。
コンタクトを付けたまま寝ちゃって、今起きたら目がゴワゴワするし何か視界がぼやけて青っぽいのがものが見えるし、こりゃ早くコンタクトを外さないとダメだなと思って洗面所で鏡を見たら、居間からお母さんの叫び声が聞こえてきて、
「ちょっと、月が大変なことになってる、目玉になってる!」
そうは言っても大変なのはこっちもそうであって、自分の左目が、月に変わってしまっているのだ。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Eグループ
式さんの「月と眼球」を批評するのはそう簡単ではないと感じるが、思うにその原因はこの作品の完成度の低さにある。
たとえば文体を考えてみよう。
引用した冒頭部分はすべてひと続きの文章で、寝ているあいだに月と眼球がすり替わってしまった語り手がそれに気付く場面をわりあい砕けた文体で描いているが、この文章自体についてまずいうとあまり褒められたものではない。
というのも、文章の音としての連なりという音楽的側面にさほど気を配らずに読点を重ねて無理に伸ばしているせいか、テンポが悪く、冗長で、句点による切れ目もないためあまり意味があたまに入ってこないからだ。
が、僕が指摘したいのはそこではない。
作品の末尾を観てみよう。
かつて恐竜を滅ぼした隕石とは比較にならないほど巨大な眼球が地球に激突すれば、文明どころか惑星そのものが滅びることは明白であった。でもとっくの昔に文明は滅んじゃってて、生き延びた人々は迫りくる絶望にただ腰を抜かすことしかできなかったんだけど。
お気付きのとおり文体が変わっているのだ。
それも、Dグループの矢部喬の「殺人野球小説」のようにある種のショック効果であったり清々しさや爽やかさを狙ってすぱッと切断したというよりは、前半部のどこかでぐだぐだッと変わってしまった印象を受け、「明白であった」のような結構硬めの言葉と「滅んじゃってて」や「たんだけど」のような砕けた言葉が混在していることをふまえると、書き手の意図的な試みというよりは言葉のコントロールしきれなさを感じる。
要するに中途半端なのだ。
物語にもある程度は同じことがいえて、作風自体は非現実的なワンアイデアから話を拡げていく同グループの大前粟生「私の弟」やCグループの伊藤佐知子「期待はやがて飲み込まれる草」と同型なのだが、後半部ではその展開のさせ方も普通にいえばかなり雑なものに変わっている。
ひょっとしたら非論理的なナンセンスのおかしみを狙ったのかもしれないが、その変化のメリハリが明確に付けられていない分やはりこれも中途半端だといわざるをえない。
そして、僕自身は式さんという作家の他の作品を知らないため、この完成度の低さがこの方の技術や性格によるものなのか、あるいは制作期間に余裕がなかったりしたせいなのかは判別できない。
したがって、アイデア自体には面白みを感じなくはないのが残念ではあるが、好意的にいっても否定寄りの評価不能という批評をこの作品に付けざるをえない。