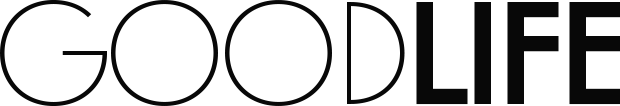書くヤツは書かれる勇気がある者だ
- 問答無用、斬捨御免。
- 原則、冒頭から読めた部分までしか読みません、時間は有限なので。
- 読者の便宜をはかって☆〇△×の4段階評価をカンタンに付けています。
- ブンゲイファイトクラブってなんぞ?という方はご自分でお調べください。
- 以下の批評は、羊谷知嘉個人の責任でおこなうものです。
- 反論歓迎。
1回戦Cグループ
冒頭を読むかぎり、このグループの作品は文章技術に難があったり説明的過ぎたりでレベルが低いけれども強いて推すなら蕪木Q平さんか。作者の力量は感じられ、唯一最後まで読まさせてくれた。
ブンゲイファイトクラブ1回戦Cグループ| #ブンゲイファイトクラブ https://t.co/srWaCmULpg
— 凍結の批評者、羊谷知嘉 (@ChikaHitujiya) September 30, 2019
蝶の道の下を歩いて、浜へ行く。
黒くて大きな翅から水滴のような形で後方へと伸びた部分だけが鮮やかに赤い彼らは、こんな曇り空にもよく映える。
茂みを抜けて浜に出ると、さほど遠くはないところに向こう岸が見える。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Cグループ
正直に打ち明けよう、書き手の北野勇作は文章が稚拙だなあという感想以外なにも出てこなかった――読み進めることさえできなかった、まったく。
たとえば冒頭2行目のクロアゲハ(たぶん)の描写を考えてみよう。
まず、大前提として極端に頭でっかちな主語述語関係はリズムが悪くなりがちなだけでなく、文章の意味としてもあたまに入ってきづらいという致命的な問題がある。
というのも、だいたいの文において主語の〇〇自体よりもそれが何なのか、どうするのか、どうなるのかといった述語部の方に全体的な意味の力点がおかれやすいため、そのバランスを予期している読者はその頭でっかちな主語部に躓かされてしまう。
また、具体的な描写が多い文芸作品では語の既にあるイメージを利用することで主語部を大幅に節約できるため、変に肩肘を張ったりして無駄な形容を重ねないかぎり頭でっかちな主語述語関係にはなりにくいという事情も関係している。
もちろん、抽象的な議論や概念の厳密さが要求される学術的な文章などではこの頭でっかちが大いに起こりうるが、その場合には、句読点の打ち方や語句の配列を工夫することでいくらかはその読みづらさも緩和できるはずだ。
ましてや、文法上の自由度が高い文芸作品ではそもそも主語を容易に省略することすらできるので、なかなかお眼にかかれるものではないだろう。
次に、北野が実際におこなった具体的な描写を観てみると、「黒くて大きな翅」「水滴のような形で後方へと伸びた部分だけが鮮やかに赤い」といったように、別段凝った表現や意表を突いた形容、あるいは語の日常的な使われ方やイメージを大きく裏切った詩的表現をしているわけでもない。
要するにもっと単純で短い表現に置き換えても差し支えないということだ。
この冗長でかつ凡庸な語の羅列にどんな意図を込めたかわからないが、少なくとも僕に読むのを止めさせるには十分過ぎるほどの威力だったと記しておこう。
【追記1 10/4】
冒頭から読めたところまでしか読まないという僕の批評スタイルがネット創作界隈の大きな反感を買い、どうも先日公開したABグループ編がプチ炎上しているようだ。
ようだ、というのは、僕の記事への流入はたしかに激増しているものの、実際に僕個人にたいして批判的なメンションを直接飛ばしてきたのは運営の1件、それから公認ジャッジの樋口恭介の引用1件、また、自身の note で僕への批判記事を書いたものの3件のみ(10月5日加筆)で、創作クラスタが騒然とし叩きに叩いている(らしい)割にはその実感が僕の方まで届いていないのが正直なところ。
陰キャか!というツッコミが舌先まででかかっているが、1日でも早く全批評を書きあげることに集中しているのでこの件には触れない。
何故冒頭から読めたところまでしか読まないかは該当記事でも何度か触れているが、人類史上今ほど多様でたくさんの娯楽コンテンツが遍く安価で溢れかえった時代は片時もなかったわけで、潜在的読者の限られた時間の奪いあいに「文芸」も等しく参加させられていることを踏まえると、冒頭からして面白くない(と、少なくとも僕にはそう感じられる)ことは作品として致命的だと考えている――当然、作者の社会的地位や実績がなんであれ、僕は自分の価値判断にしたがって根拠を示しながらハッキリ書くしかないので批判的なものにならざるをえない。
むしろ、どこまで読めたかを明記している分、反論の余地をわざと残しているため僕は良心的なのでは?とすら思っている――というのも、実際には読んでいないのに最後まで読んだかのような顔付きで批評なり感想なりを書くのはさほどむずかしくないし、作品自体にはあまり言及せず、作品のコンセプトから触発された反駁不可能な自分の解釈を「批評」と称して披歴することもまた、作品を精読せずともできるからだ。
また、直接寄せられた批判に自分の批評スタイルを見直すほどの論拠があったとは思えないので1回戦全32作品の全批評はやり通す予定。
まあ、最後まで読んでもらってあたりまえ、批判的なことは書かないのがあたりまえというひとたちは、あまいなー、今がどういう時代か見えてないなーという言葉しか出てこない。
僕は正直なところ今の日本の文学界に詳しくもないし興味もないが、もしそういうロマンチックなひとたちがいわゆる文学好きの中心勢力なら、出版業界最大手の新潮社が百田尚樹の『夏の騎士ヨイショ感想文キャンペーン』といういかにも大衆の俗っ気に訴えたプロモーションに打ってでるのも致しかたないのではないだろうか。
ちなみに僕はこのキャンペーンにわりと真剣に参加したかった。
独裁政府の言論統制下で、どうやって体制に媚を売りながら自分の本心を批評に潜ませるかの執筆チャレンジと見方を変えたら、書き手としてはなかなかにスリリングな表現の不自由イベントになっただろう。
1)回答します。中のひとへ。それはあなた個人の批評観か、帰属集団の常識です。僕には僕の批評観があり、その論拠は記事中に示しています。僕の論拠に対する反論のかたちをとらないなら、議論不成立で、自分の価値観を他人に押し付けているだけですね。到底容認できません。 #ファイトクラブ https://t.co/7ocKR9KL3C
— 凍結の批評者、羊谷知嘉 (@ChikaHitujiya) October 3, 2019
2)運営主体へ。自由に書かれた表現に激怒していますと運営アカで伝えるぐらいなら、はじめから「日本の文芸史上かつてなかったもの」と銘打たず、2回戦からは招待制のネットサロンなどでひっそりと作品掲載することを提案します。忌憚ない意見に晒される覚悟、あります? #ブンゲイクラブ https://t.co/7ocKR9KL3C
— 凍結の批評者、羊谷知嘉 (@ChikaHitujiya) October 3, 2019
1)どうも、#ブンゲイファイトクラブ を愉しまれている皆さん、全作品批評の羊谷です。お騒がせしてすみません。運営と公認ジャッジからお怒りを受けていますが、特に自分のブログで全作品批評を書くのを止める理由が見つからなかったので1回戦32全作品までは書きます。それ以降は遠慮します。
— 凍結の批評者、羊谷知嘉 (@ChikaHitujiya) October 3, 2019
麦畑の空中にぽっかりと、穴が空いているのを最初に見つけたのは、バスケットボール部の朝練で早朝に家を出た中学一年の女の子だった。
きらきらと万華鏡のように輝く穴だった。
よく見るとあたかも気をするように膨張と収縮を繰り返し、それが息であるならば、何か意思を持った生物の呼吸器ということになるが、息を吸ったり吐いたりする空気の流動は感じられなかった。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Cグループ
面白くはないけれど良く書けているし巧い、僕の率直な感想だ。
評価できるところから観ていこう。
まず、文章能力に関しては申し分ない――意味するところが無駄に曖昧だったり不明だったりする部分が見当たらず、華麗な形容や音楽的律動に導かれているわけではないが普通の意味で過不足ない良い文章だ。
内容に関していうと、麦畑の空中に突如「穴」が空くというワンアイデアを現代の日本社会に話を留めながらもよくユーモラスに構造化し作品世界を構築していると評価できる。
先日公開したABグループの全作品批評の際にアイデアの構造化が足りないという評言を何度か残したが、あのとき僕がいわんとしていたのはこういう意識の払い方だ。
文学は言葉の上でならなんだって実現できる――が、書かれゆく事柄が相互に緊密な関係を結んで作品世界を作っていかなければそれも一場の夢にすぎないだろう。
伊藤佐知子のこの作品はお手本のようなクオリティでこの努力に成功している、が、物足りない――多分、この言葉がいちばんしっくり来る。
たとえば、アメリカ合衆国はどういう反応をするだろう。
日本のマスメディアが騒ぐほどに話が広まれば当然海外マスメディアをはじめとしたネットユーザーも喰いつくはずで、奇妙キテレツな「穴」の発生に大国アメリカが黙しているはずはない。
また、お隣の韓国中国がどう騒ぎたてるかも気になるし、欧州の原子力研究機関やロシアも何らかの反応を示すだろう。
ひょっとしたら、軍事的緊張をはらんでいるアラブ諸国は何か軍事利用できないかと諜報機関のエージェントを送ってきやしないだろうか?
だとしたら、狙われるのはまず第1発見者のあの女の子だ!
とまあ、意識の持ちようで物語の小さな枝葉はいくらでも拡げられる。
お行儀良くまーるく綺麗にまとまったものとハチャメチャに拡げ散らかしたもののどちらが良いか、これは趣味の違いかもしれない。
が、僕が高く評価するのは創ることがより難しい後者の方で、作者の文章力があればもう少し枝葉のユーモアを拡げ増やしてもしっかりまとめあげられたのではと残念に思わずにはいられない。
1来たこと!弟が死んで私のへやにコダックがきたのは、じこがあった日が弟はコダックをおいかけて道ろに出てしまったのですぐあのコダックとわかったからです。コダックは2だんベッドの2のだんにきゅうにいて、そこは弟の使っていた。バイクがつっこんだとき弟はかならず色ろちがいかもと言ったが色はふつうでき色だったがわたしは大切にすると思った。(中略)
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Cグループ
コダックは希少性のある色違いよりもオリジナルの方が可愛いと思うのは僕だけだろうか。
ポケモンの色違いという出現率の低い希少種は独特なカラーバリエーションをしているが、メガゲンガーのように贔屓目にみても素直に格好良いと思えるものもある一方で、コダックのようにやっつけ感のあるあまり捕獲意欲を刺激しない色違いもけっして少なくない。
実際、僕の嫁ポケのナマコブシも希少種のカラーリングが下水道育ちを思わせるため僕はいまだに色違い厳選デビューをせずに済んでいる――この致命的な問題で開発のゲームフリークを批判すべきか感謝すべきかは実に難しいところだ。
価値判断が悩ましいといえば蕪木Q平の作品もそうだろう。
大前提として、創作上、登場人物の死を正面から扱うのはきわめて難しいという問題がある。
というのも、言葉の上でひとを殺すのはカンタンだがーーナンセンスな可笑しみを狙う場合はむしろカンタンに殺すべきだがーー登場人物、それも語り手の弟という親密な者が死ぬ場合にはその死による周囲の物事への強い影響を構造化できなければ、「書けていない」ことの不出来を鑑賞者から容易に見透かされてしまうからだ。
また、死ぬということが人間として直視しがたいことなため、作り手としても読み手としても書きづらい、書き難いというのもあるだろう。
この観点からいうと、蕪木のこの作品は語り手の弟の死による幻視とその周囲の健常者的反応というきわめてシリアスなテーマを、コダックという可愛らしい意匠で上手く緩和させながら真正面から取り組みーーおそらくは成功している。
タニシや生前の弟との会話、また、ここは解釈次第で意見がわかれるだろうが、語り手の少女に対する父親からの性的虐待を匂わせる不穏なディテールも、その書きかたから含めて素晴らしい。
蕪木Q平は掛け値なしに優れた作家だ。
問題は、我が嫁ポケのナマコブシをマスコット枠に採用しなかったこともそうだが(マイナーポケモンだからです、ハイ、知っています)、簡潔にいえば文体の読みづらさだ。
作者による偶然のミスはなくすべて意識的にコントロールされきっていることを前提とするが、作品世界の物語内容から逆算して考えれば、小学4年生(たぶん)で深刻なPTSDを背負った少女の脱字も含めた通常の日本語文法及び言語慣習を破った語りの演技は理屈のうえでは納得がいく。
しかしそれは、20世紀中頃くらいからの言語自体を裏切る実験的な文学作品に慣れており、かつ、この作品をある程度読んだうえで理性的に納得できることであって、たとえば小説をさほど好きでも読んでもいない読者がこの作品を数行内で脱落せずにどこまで読めるだろうか。
要するに僕のこの作品に対する批判は、コダックという意匠とは裏腹に蕪木の文体は高尚過ぎるのではないだろうか、だ。
もちろん、文学好きの読者含め、作者がそういう教養の低い読者をはじめから眼中に入れていないのであればそれで良いだろうが、より広い層に訴求できるものとそうでないものとでは、内容が同じならば前者の方が良いし時代的にも適っているのではというのが僕の価値観であり考えだ。
とはいえ、蕪木Q平が本大会で別の作品も読んでみたいと思わせられた数少ない作家のひとりだとも明記しておく。
あと、ナマコブシの方が断然可愛いことも。
ほらッ!!
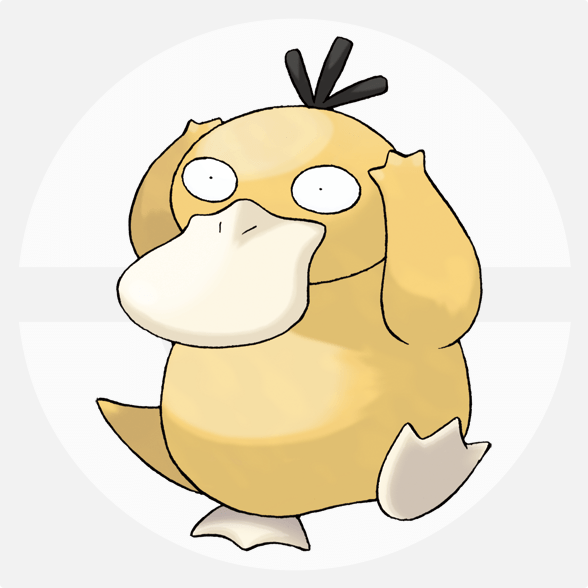
via. No.054 コダック

via. No.771 ナマコブシ
愚図で無能な間抜けがいた。容貌は醜悪で態度は横柄で可愛げがなかった。父親からも母親からも疎まれた。愚図で無能な間抜けだから愛されようともしなかった。長じて学校に通うようになったが成績はひどいものだった。集団行動もできず、友達もいなかった。たまに話しかけられても気の利いたことは何も言えず、相手はすぐに退屈した。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Cグループ
僕は何故批評を書き続けるのだろう。
いや、ブンゲイファイトクラブ全作品批評になぜここまで執着するのか。
批評を書くということは、笑い者にされて袋叩きにあうにせよ、聴く耳をもつ読者の参考になるにせよ、結局はこのコミュニティの「エサ」になることであって、僕に直接的な関わりのないこの”界隈”にそこまでする義理も意義も利点もとてもじゃないがあるとは思えない。
それでも愚直にしようとするのは、僕もたぶん、愚図で無能な間抜けのひとりだからなのだろう。
植川の小説「愚図で無能な間抜け」は、率直な感想をいうと、面白くはないけれども書き手の技量と使命感を高く感じる悪くはない出来の作品だ――ただし、おもしろいと感じるかどうかはこの愚図で無能な間抜けにどこまで共感できるかで話はまったく変わる――もちろん僕のことではない。
まず、社会の下層階級に位置する光のあたらざる者を描くことは、近代文学、というより近代芸術のひとつの大きな流れに属するもので、それを現代でベタに再演するという古さは気になるにせよ正当性のあるものだ。
淡々とした語りも、たんに話の筋を追いかけたり愚図で無能な間抜けの説明をしたりせず、物語のディテールを重ねることで彼の生き様を描いており高く評価できる。
文章技術も普通に読むかぎり申し分ない。
ネックとなるのはやはり想定読者の幅の狭さか。
書き手の技術を理性的に評価できる読み手を除けば、改行なしの1段落構成という意図的に可読性を押し下げた紙面構成もあいまり、この作品を最後までおもしろく読めるかはこの愚図で無能な間抜けに共感できるか否かにすべてが懸かっているはずだ。
現代的に再構成するとしたらこのクソ真面目なシリアスさを緩和するなにか、たとえばコダックのようなものを使ったり喜劇仕立てにしたりすることだろうが、はたしてそれが作者の趣味や価値観、あるいは作家としての矜持に適うかどうか。
結局大事なのは作者が自分の表現・創作行為に何をもとめるかなのだろう。
――自己の救済か、神への献上か、他人を面白がらせることか、新奇さへの渇望か、クローズドサークルの評判か。
僕自身はそれら全てという統合性を最上と考えるため、この点において自己の救済に寄っているこの作品をこれ以上高くは評価できない。
【追記2 10/6】
気付かれた方もいるだろうが、このCグループでは完全な初読時のツイートよりも、伊藤佐知子、蕪木Q平、植川の3氏の作品評価にそれぞれ若干の上方修正をくわえている。
現時点でわかったこととはいえ、ツイート時に今の僕としては誤った作品評価を載せてしまい大変申し訳ありませんでした。
だったらはじめから否定的な評価をだしてんじゃねーッ!黙ってろ!という批判の声が聞こえてきそうだから事前に書いておくが、その理屈でいえばこの世のすべての作品が半永久的にオールオーケーということになってしまう。
僕としてはその都度毎に作品に真摯に向かいあい、その都度毎にだせる評価をキチンとだし、その前後に変更があれば修正をくわえて謝罪する。
この批評態度ばかりは何をいわれても変えるつもりはない。