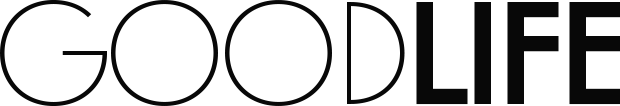妄言は甘く、良薬は苦い
- 問答無用、斬捨御免。
- 原則、冒頭から読めた部分までしか読みません、時間は有限なので。
- 読者の便宜をはかって☆〇△×の4段階評価をカンタンに付けています。
- ブンゲイファイトクラブってなんぞ?という方はご自分でお調べください。
- 以下の批評は、羊谷知嘉個人の責任でおこなうものです。
- 反論歓迎。
Contents
1回戦Fグループ
冒頭を読むかぎり、このグループでは蜂本みささんがいちばん良い。完成度が非常に高く、荒削りな傑出も野心的な試みもないがだれもケチをつけられない秀作。隙がないものを独りで作れるのはもはや才能だと思う。#ブンゲイファイトクラブ 1回戦Fグループ https://t.co/3LuPMi1DQZ
— 凍結の批評者、羊谷知嘉 (@ChikaHitujiya) September 30, 2019
まだ暑さの残る体育館の中はほの暗く、海の底のようだった。けして広くはない田舎の小学校の体育館は、全校生徒が集まってもまだ空白があった。いつもと違う気配を察して、皆がざわめいていた。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Fグループ
意外に思うかもしれないが、一見何の変哲もない珠緒の「手袋」はこれまで評してきた参加作品のいずれとも異なる奇妙な印象を受けた。
文章自体にはいかなるも試みも可笑しみもあるとはいえないが、テンポの悪いことを除けば批判されるべきもののそれとは決していえない技術と経験を感じはする。
冒頭を越えて読めたか読めなかったかでいえば読めていない――正確にいうなら読む気にはなれなかったが無理して読んだが正直なところで、僕がこの作品に迫るために問題にしたいのは読後感としてどこか肩透かしを食う印象を受けたことだ。
僕はこの作品に何を期待していたのだろう。
名前は敢えてださないが、作品に面白みをみいだせなかったりその試みが失敗していたりする作品はやはり文章からして良くなかった。
しかし、珠緒の場合にはそのそつなく良くなくはない文章力から予期されるほどには書き手がどう面白さを作ろうとしていたかまったく見出せなかった。
思うにそれは、本作品のクライマックスであり唯一の謎である手袋の「中身」を語り手みずからが解説してしまい、読者の想像を越えてこないため不気味さもなにも感じさせずに流れてしまっているからだろう。
そもそもをいえばこの作品にははじめから読者を惹き付ける謎がなく、タイトルも手袋の1語のみでどうやって読者の興味関心を惹こうとしているのか皆目見えてこなかった。
ひょっとしたらこの作家にはことさら衆目を集めたり読者を面白がらせようという気持ちがあまりないのかもしれない。
だとしたら、自分にしか書けない何かに特化して超個性派作家として突き抜けるしかないのだが、まあ、本人にとってはこういう評言も余計なお節介なのだろう。
「天空分離」という現象について管見の限りではあるが、初めて言及していると思われる文献は、アメジスト・ロータリーの「天空分離記」であろう。天空都市フラナリーが「空の牢獄」に突如として囚われた、旧フラナリ―歴一四九八年の三年後、分離暦四年八月二十七日の日付が奥付に記された、黒革の美麗なこの装丁本の著者は、その最初の部分で次の様に「天空分離」について記している。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Fグループ
文芸作品を冒頭から読めたところまでしか読まずに批評する、僕がこの全作品批評で採用している評価スタイルに創作界隈から厳しい批判の声が集まる気持ちもわからなくはない。
が、たとえそれで僕が「作品の本質」というべき何かを捉えられずに作品を不当に「貶め」ていたとしても、現実問題としてタイトルや最初の数行、数段落、数頁で読むかどうか買うかどうかを決める読者がいなくなってくれるわけではない。
YouTube 動画に否定的なコメントを付けたりグッドなりバッドなりの評価ボタンを押すのにわざわざ最後の1秒まで再生する必要があるだろうか?
同じ理屈でいうならアニメやドラマは控えめにいってもシーズン終了まで固唾を呑んで見守ることしか許されず、何か否定的なことを書こうものならただちに批評取締委員会から書き直しを迫られたり極度の不快感を表明されたりして磔刑に処された上に聴衆から石を投げつけられる。
素晴らしい文芸ディストピアではないか?
1万歩譲ってこのスタイルでは「作品の本質」はわからないとしても、残念ながら作家が読み手や自作にどういう態度で向き合っているかの違いはわかる――というのもそれらが潜在的読者に向ける作品の顔だからだ。
前置きが長くなってしまったが、伊予夏樹の「天空分離について」もやはりその点に深刻な問題がある。
分離暦3000年という架空の節目に架空の古典文献を引用しながら天空分離という架空の出来事の言説の歴史的変化をやや硬質な文体で論じた本作は、伊予により意図されたであろうそのアイデアや体裁というか演技の面白さもわからないことはない。
しかし、だとしたら何故「天空分離について」という味も素っ気もないタイトルにしてしまったのか。
書き手の世界観のなかでこの文章をどう位置付けるか次第だが、たとえば記念祝典のパンフレットに寄せた短文だとか学術論文だとかにもっと寄せた方がそのアイデアの面白みを際立たせられただろう。
だいたい、天空都市フラナリーに住まう者たちが彼らのルーツに関わる歴史的大事件について何も知らないはずがないので、彼ら彼女らに向けたであろう硬質な文章のタイトルが「天空分離について」なのはいささか世界観に反していないだろうか?
文体についても同様で、どうせならもっと極端に走った方が個性も際立ち冒頭からより魅力的になれたにちがいない。
いずれにせよ、アイデアの掘り下げにせよ、構造化のさせ方にせよ、シビアな読者との向き合い方にせよ、やはり甘いといわざるをえない。
遠吠えには自信がある。なにせ師匠に恵まれた。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Fグループ
素晴らしい書き出しだ。
有史以来、遠吠えに自信のある文明人が果たしてどれだけいただろう――サバンナや熱帯雨林での非定住型部族ならいざ知らず、都市生活に慣れたものには遠吠えをあげるインセンティブがないため技術を培うことはおろか自信などもちえようはずもない。
そして、優れた師匠までいるときた。
だれだろう……人間か?イヌか?狼か?と一瞬のうちに思考を巡らせたわけではないが、言葉にするならそう考えさせるだけの謎と魅力を秘めたテンポの良い名文である。
タイトルも良い。
Dグループの矢部喬「殺人野球小説」のような痛快な派手さも、Cグループの蕪木Q平「来たコダック!」のようなキャッチーな愛らしさもないが、蜂本みさの「遠吠え教室」は物語一般のもつ謎の魅力をうまく使いながら読者を誘っており高く評価できる。
今大会の参加作品のレベルを踏まえれば、蜂本はこの書き出しとタイトルだけでも十分シード権獲得もののはずだがこれで次点繰り上げ予選通過とはなんと贅沢な大会だろう。
冒頭の批評だけでも、いや、冒頭の批評だからこそ「作品の本質」というロマンチックなものにとらわれず、事実上の落選作の意外なレベルの高さを簡潔に示せるのだから僕の批評も捨てたものではないはずだ。
作品全体として観た場合、普通の意味でいえば非の打ちどころのない創作物のお手本のように優れた作品だが、僕が挙げたほかの優勝候補作品と比べれば、渋いといえば聞こえは良いがややおとなしくキレイに纏まり過ぎている印象も否めない。
たしかに、新しい作家の書く古典的な作品に一定度の需要も積極的な価値も認めるのはやぶさかではないが、日本の文芸シーンを押しあげる作品を想像した場合、矢部や蕪木はもちろん、ミクスチャー文学とでもいうべき面白さと実験精神を兼ねたAグループの金子玲介「アボカド」の方が価値は高いのではないだろうか。
もちろん、作家にとっていちばん大事なことは、自分がどういう作家を尊敬し、何を背負い、何と闘おうとしているかであって、だれが何といおうともそれはそれという話でしかないのだが。
いずれにせよ、僕の眼からすれば優勝候補の一角を担える実力者の蜂本が、予選繰り上げ通過者としてどこまで勝ち進めるかは本大会の大きな注目ポイントかもしれない。
「久保さん」がやばい。
「久保さん」というのは残穢にでてくる「ライター」で「物語の発端」となる人物だ。こいつがやばい。物語の始めに「久保さん」の家で「畳の上で何かこするような音」がすると「恐怖小説」を書いている「私」に「手紙」をだすのだ。そこはいい。(中略)
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Fグループ
文章中の約物が嫌いだ、特に鍵括弧、この世から消えてなくなれば良いとすら思っている。
一般の書き手や読み手のことは知らないが、僕自身が何かしらを書くときは通常の意味の通りだけでなく、文における音と画の通り方も意識し、また、他人の芸術性を求められるジャンルの文章を観るときはどうしてもこの両側面が気になってしまう――少なくとも僕にとっては言葉の美術的・音楽的側面は切り離せないからだ。
そして、鍵括弧が許せないのは、大抵の場合「あってもなくても良い程度」の分際で文の「美術的な通り」と「音楽的な通り」をこういうふうに「分断」し「阻害」してしまうから、たとえばこんなふうに。
もちろん、この鍵括弧への憎しみは僕個人の美意識の問題であってあまり強く他人に押し付けるべきでないことはわかっている。
それでも僕はひとりの人間である以上、ひょっとしたら一色胴元の「読書感想文『残穢』」の評価にも僕の美意識からくる感情的な判断が無自覚にはいってきているかもしれないので、なんというか、ある程度割り引いて受けとっていただけると有り難い、申し訳ないけれども。
また、一色のこの作品はおそらく小野不由美の『残穢』を下敷きにしていると思われるが、僕はこの作品の内容を知らないのであくまで実在の本を下敷きにした作品という以上は踏み込まないでおく。
さて、一色胴元のこの作品はひとことでいってとても巧い。
冒頭の書き出しも、その約物にはきわめて腹立たしい思いこそさせられるものの、たんに「久保さんがやばい」ではただの日常的な文と遜色なくなってしまうため、小説の、それも冒頭の書き出しとして久保さんを鍵括弧で括り間接化し、読者に異質な印象をあたえるのは正解というほかない。
一色胴元は間違いなくこの約物を戦略的に乱用している。
文章自体も、一見ラフなだけの文章に映るかもしれないが、文章中における短文と長文の組みあわせかたなどは音としてとても心地良く出来ている。
物語として観た場合も、久保さんがやばいという言葉にすればそれだけのことをテンポ良くそのディテールを解きほぐしながら読者に語るその語りの魅力は見事というほかなく、書き手の深い文学的経験と教養を伺わせる、オチの付け方も良い。
しかし、やはり僕にはダメだった。
この作品に良さや面白さを感じるというよりはあくまで理性的に巧いと判断しているに過ぎず、この作品を批評するという目的意識なしに見掛けて頁をひらいた場合、最後まで気持ちよく読み進められる自信があまりもてなかった。
もちろん原因は前半部の鍵括弧の多用だ。
それが視覚的効果を狙ったであろうことも含めてこの作品に必要だとは認めるが、鍵括弧による文章の寸断が一見さんお断り的な敷居の高さを醸してその文体とは裏腹に早々の離脱を読者に促してしまってはいないだろうか。
まあ、この点に関しては僕が神経質過ぎるところがあるので自分の見方にあまり自信がもてないところではあるのだが……。
以上の理由で一色胴元のこの作品を蜂本みさのそれとは1段劣る評価としてはいるが、事実上の一騎打ちであるEグループをどちらが勝ち抜けてもおかしくない白熱の闘いであることは明言しておく。
1回戦Gグループ
冒頭を読むかぎり、いちばん良いのは伊藤なむあひさん。死のような抽象概念や視覚的にイメージできないもの、ありえないものを言葉の上でだけ生き物のように表現することは実は難しい。コミカル調ならなおさら。力量ある書き手。#ブンゲイファイトクラブ 1回戦Gグループ| https://t.co/kf8NAVaFUi
— 凍結の批評者、羊谷知嘉 (@ChikaHitujiya) October 1, 2019
東京都江戸川区にある古い木造アパートの一室で、死は生まれました。産声なんていうものは特になく、死は、じっとそこに留まります。ややあって、ぽーん、ぽーん、とその場で二度跳ねると、三度目のジャンプでいつから開いていたのかもわからない窓から、軽やかに飛び出しました。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Gグループ
伊藤なむあひの「跳ぶ死」はこの作者が本大会の栄誉を争える書き手であることを証明する優れた作品だ。
たしかにその文体は描写の妙や物語の展開量と比べればやや冗長さを感じさせ、テンポの悪さを感じる部分もなくはないが、野生動物の生態に密着したネイチャー番組の語りをパロディした本作は実にコミカルでその試みは成功している。
タイトルや書き出しも悪くない。
1回戦の全参加作品中、僕が高く評価する作品のなかで死というテーマを正面から扱っていたのはCグループの蕪木Q平「来たコダック!」と植川「愚図で無能な間抜け」だろうか。
この両作品と比較した場合、伊藤は「死」を扱い描いていたとしても何かが死ぬということを明示的には描いてはいないことに気付かされる――明示的にという留保は、作品最終部の死の水垢を眺めながらの待機と着地を通して間接的には描いているからだ。
創作上、死を正面から描くことの難しさは蕪木作品の批評の際にカンタンながら触れてはいるのでここでは繰り返さない。
その観点からみると、まず、伊藤は何者かの死がもたらす周囲への意味や影響はよく構造化して書けている。
作品前半部の「車道の端に横たわるそれ」に対する周囲の描きかたは実に緻密で、伊藤なむあひが話の筋だけを追うことに終始したりコンセプトを説明するだけの語りで良しとしない優れた作家であることを明かしている。
しかし、伊藤は同時に「それ」がなぜ、どのようにして道端に横たわったのか、つまりは死ぬというただそのことを読者に想像させることも含めてかなり周到に隠している。
それは後半部の独居生活者の死に対しても同じだ。
たしかに水垢を模様をみながら暇潰しをする死はたいへん愛らしく、ディテールの良い書き込みだが、伊藤ほどの実力があればその着地先がどういう人物でどのような過程で死にいたったのかを読者に想像させる空間の描き方は十分にできたはずだ。
伊藤がなぜ何者かが死ぬということを意図的に隠して「死」を描いたのかはわからない。
ただ、批評であれ構成要素であれ、ないよりかはあった方が良く、足りないよりかは余るぐらいの方がちょうど良い。
もし、伊藤が死ぬことを隠さずに「死」を愛らしく描きえていたならこの作品の深みや見方も変わっただろうにと残念に思わずにはいられない。
最後に余談を。
何者かがいつ死んだとみなしえるかは科学的にはかなり難しい議論だ。
ある者の心臓が止まっても脳はまだしばらく活動を続けるし、体内のマイクロバイオームも宿主の死後48時間程度なら生前と変わらぬものを保ち続けるようだ。
「死」がいつ着地し、いつ跳びだすのか、その死生観には少々興味が湧く。
豚を使う理由がわかるか。
伯父がそう質問したのは少年が裏庭の小屋で、豚の目をクリーニングしているときだった。養豚場から買った目玉には脂肪や肉がついている。それらを取り除くのがクリーニングだ。(中略)
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Gグループ
「クリーニング」という言葉の使い方についてだけ書きたい。
逆算的な書き方になるが、吉見駿一郎の「夏の目」は、平安時代の終わり頃から代々継承されてきたという死んだ動物の角膜を使ってその最期の映像を観る技術を「少年」が変わり者の叔父のもとで学ぶ話だ。
作品最終部では少年がその修練の枠を越えてさまざまな動物の屍からやや執着的に眼球を採集するあたり、この作品に怪奇ものの雰囲気を漂わせているという見方もできなくはない――もちろんこれらのことはあらすじを知らない読者にとっては読みながら想像し構築することなのだが。
クリーニングというカタカナ語をグーグルの画像検索にかけてみよう。
当然、白洋舎やホワイト急便を筆頭とするあの「クリーニング」のイメージ画像が大量に出てくるはずだ。
もちろんこの「クリーニング」がクリーニングという語の唯一意味するものではありえないが、一般的にクリーニングといった場合、業種としての「クリーニング」のニュアンスがどうしてもクリーニングという語を使う際には付き纏って離れない。
これらを踏まえて吉見の作品冒頭にもどると、だれもが読むであろう冒頭3行目にクリーニングという語を使うのはきわめて軽率な語彙選択だ。
逆算的にみればこの作品の醸したい雰囲気を著しく損ない、普通の読み手の視点でいえば作品世界の構築を阻害する。
また、ここでクリーニングという語を使わざるをえない文章を書かなければ、つづくふた文でわざわざそのクリーニングを説明する必要もなく、もう少し有益な描写なり語りなりに文字数を費やせたはずだ。
わざわざそんなことで……とめくじらを立てる向きもわからなくはないが、それが言語感覚というもので、自分の評判やプロモーションという作品の外部にあるものを利用しない限り、作家は自分の言葉の使い方に徹底的にこだわることでしかより良い表現は達成されえない――プロットもコンセプトも結局言葉によってのみ具体化されるからだ。
当然、僕がそうした努力を怠る作家を芸術表現として高く評価することはできない、アイデアというか設定自体は面白くなくはないだけに残念だが。
堕落論とうふの入る貸金庫
ポロシャツの正義の味方とび降りて
しらたきがはるかに遠いテレビ局
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Gグループ
何も想起させられもしない作品は存在する。
詩でも、小説でも、哲学でも、評論でも、映画でも、美術でも、デジタルゲームでもなんでも、制作者の敢えていうなら世界観が作品という実際の表現に落とし込まれないまま作り手のなかで完結してしまい、広い意味での鑑賞者にひらかれていない作品がそうだ。
構造的にいって批評はその正当性を証すために検証可能な方法をとるべきだが、現実的にはあくまで批評者=鑑賞者の感覚を離れられないというジレンマがある。
このあたりのことは以前簡単に書いたことがあるのでふれないが、何も想起させられない作品はその意味で批評殺しだといえる。
川合大佑の「ニルヴァーナ 川柳一〇八句」も僕にとってはそういう作品だ。
Eグループの原英「抱けぬ身体」と比較して、紙面構成や語彙選択から川合により高い技術と経験の蓄積を認めることもやぶさかではないが、だからといってそれが面白かったり良いと評価できるかはまた別問題だ。
たとえば冒頭直後のこうした句はあなたにどういった感覚、感情を想起させるだろうか。
流体をどこまで甘酢あんと呼ぶ
雨の日のさばを食べても演劇部
制作者には何か確固とした世界観があるにも関わらず、作品として鑑賞者にひらかれていないものを面白がったり良く評価したりする唯一の方法はその制作者を信奉することだ。
このひとの作るものが面白くないわけがない、素晴らしくないわけがないという批評性を欠いた信仰心が解釈という名の神学的な註釈を無限に生みだしていく――見ようによってはその中身の薄さこそが好き勝手に解釈を付けたい読み手を呼び寄せているのだが。
当然、僕にはそうした作品を高く評価することができない。
もちろん反対に僕が「わからない」だけで、実際にはこの作品は素晴らしいということも可能性としてはありえるだろうが、それを正当に評価する人物が僕ではなかったということ、それだけの話にすぎない。
とはいえ、
カルピスのここより白く狂えるか
これなどは意識の冴えを感じる素晴らしいもので、すべての句をひとしく否定寄りで評価しているわけではないことは明記しておく。
「友だちにまた虫を見せてやりたいんだけど、だめかな」
菩提樹の木陰にあるベンチに寝転がって本を読んでいると、ナインがやってきて、申し訳なさそうな顔をして見せた。ここで会うのは二回目だ。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Gグループ
樹齢130年の菩提樹はどれほど特殊な樹だろうか。
最初に思ったのはそのことで、正確には書き手がどれほど特殊なものとしてこの樹を位置付けようとしているかだった。
逆算的にみればこの作品の面白さは語り手の手の甲に時折穴が空いて謎の羽虫が出入りするというアイデアにあるが、当然、書き出しから順当に読んでいく読者の視点ではそれはあくまで作品中頃になってはじめて明かされる構成要素に過ぎない。
つまり、文章の大改造を考えないなら、この書き手が冒頭から読者を魅せる唯一の方法はこの樹齢130年の菩提樹の描きかたで、おそらくはミャンマーかその近隣国と思われる東南アジアのエキゾチックな雰囲気を醸すことだけだったはずだ。
ちなみに京都の僕の自宅から徒歩数分圏内には樹齢伝承800年の大樟もスダジイもある――だからこの菩提樹はこの作品世界ではさほど特殊ではないだろうし、樹齢130年という1語で読者の興味を惹けるほどのパワーワードではありえない。
そもそもをいえばこの菩提樹は樹齢130年という情報以外にはとくに描写がない。
同様に、ナインという登場人物にも病気がちの母親に代わって妹や弟の食糧調達義務があるという情報以外は特に描写がない。
そして、語り手である「私」もまたそのディテールの一切が不明のままだ。
語り手は現地の人間なのかそうではないのか、外国人であれば「私」とナインは何語をどれほどの流暢さで用いて会話しているのか、現地の人間であれば「私」はどういった社会階層に位置する人間でなぜ菩提樹の木陰で悠然と本を読んでいるのか――。
ある種の実験的な作風であったりナンセンスを効果的に用いた作風ではないにも関わらず、作品世界のディテールがその語りに影響しない浅薄な作品を僕はとてもじゃないが評価することはできない。
1回戦Hグループ
冒頭を読むかぎり、このグループには悪い意味でかなり頭を悩ませた。あえてひとり推すなら、悪くはない文章技術をもてている磯崎草介さんだろうか。普通の意味できちんとした文章を書くことは本読みでもそうカンタンではない。#ブンゲイファイトクラブ 1回戦Hグループ https://t.co/HPggfsZuZt
— 凍結の批評者、羊谷知嘉 (@ChikaHitujiya) October 1, 2019
鳩が嫌いなひとはわりといる。同居人もそうで、彼は鳩がとくに怖いと言って、鳩の群れに出くわすと十分な距離をとって避けて歩いた。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Hグループ
そう、鳥が嫌いなひとは多く、嫌悪対象としてハトを挙げるのは結構メジャーな部類だろう。
僕がそうというわけではないが、「ハトフォビア」を告白する知人友人は過去に少なからずいたし、グーグル検索で念のため調べてみるとやはりハトに嫌悪感や恐怖感を覚えるひとは一定数いるようだ。
だとしたら、作者の斎藤友果はなぜ語り手の「同居人」が鳩を嫌っているかのたいして奇抜でも独創的でもない理由を書くのに紙面半枚以上も割いたのか。
普通に読めば、作品最終部までかならず熟読してくれる理想的な読者でもないかぎり、長々と続くなぜ「同居人」が鳩を嫌っているかという平凡な語りに読み手は早々と離脱してしまうのではないだろうか、この「同居人」と同様「ハトフォビア」を患っているひとでないかぎり。
とはいえ、作者の斎藤にある種のセンスがないとも思わない。
話の筋を追うだけに終始したり物事を説明することが良き語りではないことはわかっているようだし、部分的には普通にいっておもしろいディテールの重ね方や活かし方をしているところもある。
鳩の頸を切った痕から木の実やら何やらが溢れてくるといったところがそうだ――ただ、熱を入れて書くべきディテールとそうではないディテールがちぐはぐな印象を受けるだけで。
だから、斎藤に欠けているのはあくまで醒めた目線の仮想読者の内面化か、書き手に代わって読者をいかに面白がらせるかをアドバイスする同伴者か、あるいは読者ガン無視でもうひたすらに自分の世界を追求する潔さか。
いずれにせよ僕は斎藤のこうした作品を高くは評価できないが、その作家名は覚えておこうと思ったことは明記しておく。
斎藤友果、近い将来化ける下地はある。
皺だらけの祖母の手に、じっとりと汗が滲んでいる。つないだ手のひらは、梅雨時の風のように生ぬるい。ぼくは、この手が大好きだった。両親がいないことでいじめられ、泣きながら帰ったあの日、祖母は大きな手のひらでぼくの髪の毛をくしゃくしゃになるまで撫でてくれた。不思議とそれだけで、ぼくはひとりぼっちじゃないことを実感できた。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Hグループ
泣かされる良い話だ。
作品の好き嫌いや価値評価は分かれるにせよ、磯城草介の「ハハコモリ」がいわゆる「イイ話」なのは間違いない。
最近の僕の Twitter のタイムラインはもっぱらホアキン・フェニックス主演の『JOKER』の話題で埋まっている。
映像の美しさと演技の魅力にうち震える旦那のとなりで奥様は時計を見遣りながらずっと溜息をついていたという友人夫婦から、はやく羊谷さんにも劇場にいってほしい、映画好きの第3者の意見を聞きたいというお願いまでされている。
もちろん僕はこの全作品批評に手をとられているのでまだ未鑑賞なわけだが、おそらくは決して「イイ話」ではない『JOKER』が相応に共感をもって迎えられ、同時にその魅力故にアメリカの映画館では子どもには観せないよう警告をだしたり地元警察や米軍が警戒にあたっているのには興味を惹かれる。
「イイ話」も世にはあって良いし、あって然るべきだが、ひょっとしたら「イイ話」で終わる物語が支持される時代ではないのかもしれない。
そして、批評的にいえば現実の悲惨さや無惨さが何も描かれない「イイ話」で終わるものはさほど難易度が高いものではなく、その感動もどこか浅薄で白々しものに映るのもやむをえないだろう。
磯城の作品でいえば、語り手の「ぼく」と祖母がいかに強い関係にあったのかは描かれていても、何故そうならざるをえなかったかの背景が「両親がいないことでいじめられ」てのひとことで片付けられてしまっている。
どんなに「イイ話」であっても背景の書き込みが薄過ぎる作品を芸術表現として評価することはできない、少なくとも僕には絶対に。
低い食テーブルの上に入れ歯がぽつんと置かれていた。剥きだした歯の側面には年季の入った赤や黒のシミのようなものと、まだ新鮮な食べ物の滓が、ところどころ付着している。入れ歯をたたえるようにして、こぼれた米粒や鮭の滓が取り囲んでいる。(中略)
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Hグループ
林四斜の「くされえにし」は率直にいって評価が難しい作品だ。
冒頭から観てみると、紙面半枚ほど続く入れ歯の描写はコミカルな表現もなくはないものの普通にいえば気持ち悪いが、以降も続く祖父とその不衛生極まりない生活の描写を逆算的に思えばまだこの程度は序の口といった方が良いかもしれない。
もちろん、読者に気持ち悪い思いをさせられたということはこの書き手に相応の筆力があったということだ。
実際、初読時はその嫌悪感のせいで冒頭以降は読まずに済ませたが、今割り切ったうえで読むとなかなかに林が良い文章力をもっていることがわかる。
この嫌悪感の催しはどの程度書き手に意図されたものなのだろう?
もちろん読み手にはわかる由もないが、もし、この作品世界の出来事が作者の実体験に基づくことならこの嫌悪感の効果は作者の想定よりも大きくなっている可能性がある。
たとえば、世のなかの大半のひとは自分の吐瀉物を無理やり食べ直させられることは想像するのさえ気持ち悪いことだと感じるだろうが、僕はそう思わない。
なぜなら僕は幼少期に食卓の場で吐いたものはその場で食べて片付けるよう躾られたので、たぶん、僕のなかの何かしらの感覚が麻痺しているからだ。
まあ、極端な例ではあるが、同様の効果の誤認が林の筆致を不必要に気分の悪いものに変えさせている可能性はある。
だとしたら作者にはなんとも気の毒な話というほかない。
実際、作品最終部ではなにやら良い話風の流れで物語は終わるが、不衛生な生活感をここまで緻密に描いたものをどれほどの読者が読み進められただろうか、あるいは、作者の林はどういう読者像を想定して書き進めたのだろうか。
嫌悪感を催す描写がこの作品に欠かせないものであることは認めるが、だとしたらコミカルな調子にしたり、語り手がなぜ祖父の家に滞在するようになったのか、祖父はどういう経緯でこんな暮らしをしているかのエピソードをはさむことで緩急も付けられたはずだ。
当然、嫌悪感の問題を抜きにしても、ふたりの背景をもうすこし丁寧に描くことでこの物語自体も良くなったであろうことは想像に難くない。
少年は小さなウクレレを爪弾きながら家路をたどる。
とても気分がいいとかご機嫌というのではないけれど、なにひとつ悪いこともない。いつもの、ただの帰り道だった。
via. ブンゲイファイトクラブ1回戦Hグループ
「ハワイ」とだけ題されたこの掌編小説に、未知の読者を惹きつけよう、おもしろがらせてやろうという作家の意識がどれほど通っているかは不明だが、魅力的でない題の作品にどうして最後まで付き合った上での批評を強要されなければいけないかもやはり不明のままだ。
貝原の「ハワイ」で奇異に映るのは冒頭を読むかぎりタイトルだけではない。
とても気分がいいとかご機嫌というのではないけれど、なにひとつ悪いこともない。
これはいったいどういう表現なのだろう?
同型表現は次の段落でもあらわれる。
まだあまり上手く弾けないが下手でもない。それほどもう手元を見なくても弾けるようになっている。
〇〇ではないが××でもないという表現は、少なくとも貝原のこの作品では全くといって良いほど意味や価値をなしていない。
実際、前者の場合には続く「いつもの、ただの帰り道だった」というひと文で補足説明されているのでこの文章は削除しても問題なく、後者の場合にも続く引用のひと文と「辺りの空気を気持ちよく響かせる、一応ひとつの曲になっている」というひと文で補足説明されているのでこちらも削除して問題ないだろう。
では、これらはあってもなくても良い文章だったのか?
僕はそうは思わない――むしろ積極的に削り、何かもっとマシなことに文字数を費やすべきだったはずだ、字数制限が厳しいフォーマットならなおさら。
表現の無駄を省き、効果的なアイデアを盛り込んだり描写をふやしたり気の利いた会話を挿したりする、結局はこうしたことの積み重ねがいわゆるテンポの良い文章を生み、物語を展開させないまでも読者を飽きさせない魅力ある文章になる――そのお手本が本大会中でいえばDグループの矢部喬「殺人野球小説」だった。
本当に難しいのは何を無駄と判定するかは個人の感覚と知性に依存することだろう。
ゆるーい時間感覚とゆるーい鑑賞者との関係のなかでは多くの表現の無駄が許容されるだろうし、血走った時間感覚とシビアな関係のなかで作られれば表現の無駄はどんどん切り詰められていく。
もちろん僕が高く評価するのは後者で、前者のゆるさにあわせた鑑賞・批評行為は時間とエネルギーの無駄だとさえ考えている。
ひとの人生も時間もあまりに有限過ぎるほど有限だからだ。