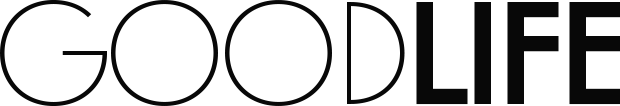受賞おめでとう、村上春樹さん
ノーベル文学賞、永年最有力候補の名誉日本人「村上春樹」。
氏が栄誉あるノーベル文学賞、すなわち大金と外国人(とくにヨーロッパ)からのお墨付きと Wikipedia に追記すべき一行を手に入れてしまう前に、私にはやらなくてはならないことがあります。それは、「あなたは(誤解されているけれど)とてもすごい」と前もって言っておくことです。「やっぱり受賞すると思ってました」と後から言うより、前もって「必ず受賞できますよ」と言って励ましておいたほうが、印象が良くなるに決まっています。
うまくいけば、おこぼれに預かれるかもしれません。「おそらくたぶん見込みのある作者の本」などと私の本の帯文でも書いてもらうことができればそれだけで、私の本はきっとよく売れることでしょう。じつは私は、作家を志す若者なのです。
さらに、文芸誌等の企画する「若手作家、村上春樹を語る」「ポスト村上春樹の時代」「私の村上春樹」「春樹とアメリカ文学」といった実に刺激的で、誰にも思いつかないような斬新な特集に参加して金銭を獲得することができれば、万歳三唱というものです。
寄稿依頼を想定して、先に少し書いておきました。一部を抜粋します。
題:村上春樹について語るとき僕の喉が枯れること
私は村上春樹が大好きです。核心に触れない回りくどく優しい書き方、なにかを言っているようでよく読んでみるとなにも言っていないあの奥ゆかしさが大好きです。そこはかとない悲しみが染みついていて、えも言われぬ喪失感が吹きこぼれていて、詳細な性描写に興奮できる(氏はペニスやヴァギナについてなかなか詳しいようです)、なんでも揃っている小説のホームセンター、大好きです。
私は HARUKISM に傾倒する、れっきとしたハルキストです。
ここでは「村上春樹」とは何者なのか? といった腰を据えた議論は遠慮させてください。私の目的は純粋に「村上春樹」を称揚することにあります。この文章は尻尾です。犬の尻尾のごとくぶんぶん振り回して、(私が)愛らしい存在であることを氏にアピールするための表現ですから、神話的構造、無意識、芝生の復讐、マラソン、脱構築、二重人格、猫のゆりかご、デタッチメントからコミットメント、オウム真理教、魔の山、一戸建てマイホーム構造、ゆで卵と法面、長距離走、学生闘争、ジャズセックススープ、猫、とは距離をとります。ご了承ください……。

金太郎飴が、どこを切り取っても同じくらい高いクオリティを示すのと同様に、氏の作品もまた、どれを選んでもすばらしいです。今回はそれら作品群から、私が個人的に感銘を受けたものを紹介します。この記事を読んだ皆さんは、ブックオフに行きたくて、いてもたってもいられなくなるでしょう。
およそ20年前、新世紀に入ってすぐに発表された作品に「海辺のカフカ」という長編小説があります。タイトルが難解ですが、このカフカとは過負荷という意味です。海辺における過負荷、すなわち海の家の経営難のことを意味しています。信じがたいことですが、およそ20年前の小説ですでに、コロナウイルスの流行にともなう海の家の経営難を予言しているのです。
タイトルからして先見性のある驚異の小説に、罵り合い専門家(すっかり紹介が遅れましたが、私は作家である以前に、罵り合いについて研究している学者でもあります)として強い衝撃を受けた場面があるので、紹介させてください。
……
主人公は筋トレ大好き中学三年生。なんとなく嫌気がさして(思春期なのです)家出し、四国の図書館に入り浸ります。理由は明瞭で「行く先は四国ときめている。四国でなくてはならないという理由はない。でも地図帳を眺めていると、四国はなぜかぼくが向かうべき土地であるように思える」からです。
主人公は図書館で司書の青年「ハンサムというよりは、むしろ美しいと言ったほうが近い」大島さんと仲良くなります。そんなある日、図書館に謎の二人組の女性が現れます。
二人は「女性としての立場から、日本全国の文化公共施設の設備、使いやすさ、アクセスの公平性などを実地調査して」いるらしく「この図書館にはいくつかの問題点が見受けられます」と言います。つまり、まさにこれから、女性の立場改善を目指す女性2名と、司書の大島さんとの口論が始まろうとしているのです。以下は台詞部分だけの不正確な引用になります。近年ではツイッターでも見かけるようになった、華麗なるおとぼけオウム返しをお楽しみください。
女性「まずここには女性専用の洗面所がありません」
大島「そのとおりです。この図書館には女性専用の洗面室はありません。男女兼用になっています」
女性「男女兼用の洗面所はさまざまな種類のハラスメントにつながります。調査によりますと、女性の大半は男女兼用の洗面所に対して使いづらさを切実に感じています。これは明らかに女性利用者に対するニグレクトです」
大島「ニグレクト」
女性「意識的看過です」
大島「意識的看過」
女性「どうお考えになりますか」
大島「もしあなたがたが男女別の洗面所の問題を追及なさりたければ、シアトルのボーイング社に行かれて、ジャンボ・ジェットの洗面所について言及なさったらいかがでしょう。私どもの図書館よりはジャンボ・ジェットのほうが遙かに大きいし、遙かに混雑もしていますし、私の知るところでは機内の洗面所はすべて男女兼用です」
女性「もうひとつおうかがいしたいのですが、著者の分類が男女別になっています」
大島「そのとおりです」
女性「この図書館では、すべての分類において、男性の著者が女性の著者より先に来ています。これは男女平等という原則に反し、公平性を欠いた処置です」
大島「学校で出欠をとられるときには、蘇我さんは田中さんの前だし、関根さんのあとだったはずです。アルファベットのGは自分がFのあとになっているからといって腹を立てますか? 本の68ページは自分が67ページのあとになっているからといって革命を起こしますか?」
もう一人の女性「あなたの主張していることは結局のところ内容空疎な責任回避、言い逃れに過ぎません。言わせていただければ、あなたはまさに男性性のパセティックな歴史的例です」
大島「パセティックな歴史的例」
女性「あなたは典型的な差別主体としての男性的男性だということです」
via. 海辺のカフカ(上下)合本版
もしかすると、この罵り合いの先で、フェミニズムという思想が陥っているアポリアに隙間風が吹くかもしれない、と期待するべきではありません。罵り合いに、建設的な議論から得られるような良識的解決策は、用意されていないのです。
この罵り合いの解決は大島さんの特殊性に委ねられます。大島さんは「私は性的マイノリティです」とカミングアウトすることで女性たちを退けるのですが、この小説ではその部分に重点は置かれていません。なぜなら後の展開で、大島さんに与えられたこのようなキャラクターの属性が深められることがほとんど無いからです。また、私の知る限り、別の作品で同じテーマが深められたということもないように思います。
それぞれ異なる主張を持つものを同じ土俵に立たせ徹底的に罵り合わせるのではなく、別の土俵に移動させて素早く罵り合いを畳んでしまった春樹氏ですが、どうしてわざわざ彼らを罵り合わせたのでしょうか?
実はこの罵り合いの重心は、氏が、大島さんの口を通じて語らせた言葉から読み取ることができます。大島さんは二人の女性たちを撃退すると、主人公とスピナッチ・ラップを食べながら、
「差別されるのがどういうことなのか、それがどれくらい深く人を傷つけるのか、それは差別された人間にしかわからない。痛みというのは個別的なもので、そのあとには個別的な傷口が残る。(中略)ただね、僕がそれよりもさらにうんざりさせられるのは、想像力を欠いた人々だ。」
と愚痴りつつ
「ゲイだろうが、レズビアンだろうが、ストレートだろうが、フェミニストだろうが、ファシストの豚だろうが、コミュニストだろうが、ハレ・クリシュナだろうが、そんなことはべつにどうだっていい。」
と言います。
すなわち、個別的なものの見方をしているふりをしながら、実際には個別的な物を抑圧する結果になっていることに気づけない、身勝手な振る舞いをする人々を大島さんは批判しているのです。そして、そのような人々への対抗策は、基本的には「無視」であるようです。ただ、今回のように大島さんが適当にあしらわず、「自分が抑えきれ」ずについ余計なことを言ってくれたおかげで、我々罵り合い観測所は興味深い罵り合いに出会うことができました。
とはいえ、私の見解では、人類のほとんどは想像力の欠如した、自身の不安と欲望に脳みそを食いつぶされた唯我論者の群れ、自分を哀れむのに精一杯で不意の目隠しにも数日間は気づかず普段通りの往復的生活するであろう常識人たちです。そのような大衆を無視し、適当にあしらい続けることは本当に可能でしょうか? 実際、大島さんはたやすく失敗しているというのに?
多勢に無勢、いかに不利な戦いだとしてもしかし、氏に追従する有望にして愛嬌のある若手作家「私」は、想像力欠如人との戦いに加勢して恩を売りたいと思っています。氏の戦略は、無限に湧き続ける、身勝手な人々をすべて無視することです。私も氏に倣い、静かに目を閉じ、耳に水を詰め、砂漠の砂にかぶりついて、自分の世界に没入することにします……。

……、我ら健やかなる罵り合い青年隊は、いかにしてより多くの罵り合いに出会えるか真面目に考えます。学者として、これは遊びではありませんから、氏の作品も贔屓なしに冷静に評価しなければなりません。
先程述べたように、今回の罵り合いが生じたのはひとえに、大島さんが我慢しきれなかったからです。仮に大島さんが大人の対応をしていれば、我ら青年隊は砂漠に似た日常を前に途方に暮れるほかなかったでしょう。
つまり「どうして大島さんは二人の女性を前にして我慢しきれなくなってしまったのか?」その謎を明らかにすれば、罵り合い生成のメカニズムを明らかにできるかもしれません。
大島さんの戦略は「無視」です。鬱陶しい相手は無視するに限ります。しかし、無視というのは単純なようでいて、意外と難しい態度表明です。
そもそも無視とは、「見たくない」なのか、それとも「見えてない」なのか、どちらを意味するのでしょう?
「見たくない」の場合、
話しかけられても応答しない、これが最もわかりやすい無視だと思います。
次に、話しかけられてないが、自分からも話しかけない。これは、単に明らかになっていないというだけで、一度会話が始まれば、無視されていることに気づきます。会話を始めようとしても一向に会話が始まりません。
たとえば、多くのSNSでも、ブロックやミュート機能があります。ブロックは前者のあからさまな無視、ミュートは後者の明らかになっていない無視、に近いと思います。SNSとは、いかにして見たくないものを見えていない状態にして快適な世界を構築するか、そのプロセスを楽しむ娯楽事業なのです。
次に「見えてない」の場合、
人間に比べて猫は錐状体と呼ばれる視細胞が少ないため、人間よりも区別できる色が少ないと言われています。おそらく、人間と猫では、見ている世界が違うでしょう。同様に、相対性理論を知っている人と知らない人の見ている世界は違うはずです。また、都市で生活を送ってきた人間と、漁村で生活を営んできた人間では、見えている世界が違うと思います。
つまり、すべての人間には、それぞれに盲点があります。社会的条件と生物学的条件が、人間の部分的な盲目状態を設定します。しかし、どこに盲点があるのか知らない他人からすれば、まるで無視されている気分になるはずです。相手が眠っていることを知らずに話しかけて、返事がないことに憤るような状況といえばいいでしょうか。
大島さんに関して言えば完全に「見たくない」の方の無視です。すでに見えていて、けれども見たくないからこそ、わざわざ主人公に自分の心の内を話すのです。
「僕はそういうものを適当に笑い飛ばしてやりすごしてしまうことができない」
もし何も見えていないのなら、そんな事を言う必要はないのですから。
すると、氏の作品に頻出の、無関心を装う「やれやれ」という言葉は、罵り合いに発展しようとする苛立ちや憎しみを浄化するためのおまじないだったのかもしれません。見えているから、気づいているからこそ、あえて見えてないふりをする、気づいていないふりをする、その象徴が「やれやれ」であり、大島さんが言うところの方法としての「無視」です。
つまりここ、日本唯一の罵り合い観測所が注意すべき観点として公にしたいのは、表面上の罵詈雑言でも、台詞回しの洒脱さでも、取り上げられている題材のキャッチーさや意識の高さでもありません。残酷で皮肉な事実を目の当たりにし、そしてそれを凝視し続けたためにきりぎりまで張り詰め、今にもちぎれてしまいそうになっている世界に対する期待を、寸前で弛緩させる言葉としての「やれやれ」です。それは罵り合いという、得難いコミュニケーションの前触れなのです。

罵り合い愛好家として残念でならないことが、ひとつあります。それは、近作ではそんな寸止め呪文「やれやれ」が、すっかり影を潜めてしまったことです。洗練された氏の作風から、罵り合いが退けられるのは仕方のないことかもしれません。
ですが、罵り合いの気配すらないとなると、そこにあるのはただの現実逃避、もしくは自分で自分の目をえぐり取ることで心の平安を保とうとするようないじらしさです。
厳しい言い方をすれば「見たくない」から「見えてない」への移行は、単なる責任放棄に他なりません。徹底した知らんぷりは、割と邪悪です。何も知らない人々が、なんとなくスパゲッティを食べたり、猫をなでたり、恋人を探して異世界に行ったりして、たまに「やれやれ」と言ってみるだけの小説では、大人は満足できません。「見えてない」を貫くというのは、そういうことです。自分の見たいものしか見れないので、思考力も低下し何も分からなくなってしまいます。分からないというのは、分かるための試行錯誤があって初めて意味を持つのであり、ただただ首をひねってうーむ分からん、と言うのは表現でもなんでもなく、単に馬鹿です。
それだったら、我慢し続けずに、たまには無視するのをやめて、気が済むまで罵り合いに興じてみたらどうでしょうか。そのほうがストレスも解消されて、おそらく健康にも良いと思います。もちろん、氏が歴史に残る上品な文豪になることを目指しているのなら、私の提案は全く見当違いということになりますが。
いつか、罵り合いという野蛮な小競り合いへのぎりぎりの抵抗としての「やれやれ」がもう一度聞こえてくる頃、重なり合うようにして、ストックホルムからの惜しみない万雷の拍手が聞こえてくると私は信じています。そのとき私は、既存の有能な太鼓持ち作家連や書評家連より頭一つ抜けて目立ち、「なるほど、この者信頼に足る」というわけで氏からのお墨付きと推薦とお歳暮を得、(私の)順風満帆な作家生活が始まるというわけなのです。