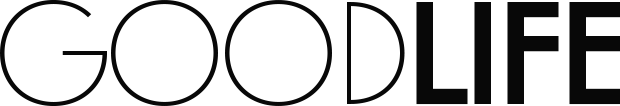制作者は名誉だけで活きるのか?
このインタビュー記事は、長年の友人であり、本ブログにも琉球文学やオタク論などを寄稿され、文芸同人「抒情歌」の『GLATIA vol.6』にて評論「中国現代文化のエコシステムとブンゲイファイトクラブ批判」を執筆された秋津燈太郎さんにお話を聞いたものです。
ブンゲイファイトクラブとは、昨年末、西崎憲の一人出版社・惑星と口笛ブックスと大手出版社に勤務する匿名の編集者3人が「全員無償」で企画した、トーナメント方式で「すべての文芸の書き手たちが作品で闘うという前代未聞」のネットイベント。
本記事では秋津さんに、現代中国のコンテンツ文化の盛りあがりやテンセントがそのエコシステムをどう築いてきたかの事業戦略、そして、日本の文芸コミュニティの問題についてお聞きしました。
ちなみにテンセントは、1998年に深圳で創業されたアジアで最も時価の高いIT系企業で、Eコマースを中心とするB2B事業から出発したアリババとは対照的に、インスタント・メッセージ・サーヴィスに原点をもち、月間アクティブユーザー数が11億人を越えるチャットアプリ「微信」を起点とした「人と人をつなぐ」エコシステム型のプラットフォーム事業とコンテンツ事業を多角的に展開しています。
創業者の馬化騰(ポニー・マー)はアリババのジャック・マーと並ぶ中国随一の資産家であり、中国の全人民代表大会の代表を務めるほどの大出世を果たした人物。
それでは、日本のコンテンツ産業を活性化するために何が必要なのでしょうか?

羊谷:『GLATIA vol.6』掲載の評論、拝読しました。面白かったです、昨年末に僕が炎上したブンゲイファイトクラブのことは抜きにしても。着眼点が鋭いよね。秋津さんがテンセントに興味をもち執筆された背景を聞かせてもらってもいいですか?
秋津:執筆経緯はですね、一番最初にあったのがまず、現代の中国文化がコンテンツ産業としても色々と発展していて、今の日本文化にも影響を与えはじめているのでそろそろ世に紹介された方がいいんじゃないかと考えたのがひとつ。ふたつめがそれにくわえて、じゃあ、中国文化がどういうふうに成長してきたかを語ることで日本のコンテンツ産業の現状とその仕組みを書きたかったこと。
そして、今回文芸同人誌に掲載した評論では「ブンゲイファイトクラブ批判」と銘打ったとおり、日本の文芸界隈の仕組みというのが今現状どうなっていてどういう試みがあり、それはテンセントも小説コンテンツを扱う事業もやっているからなんですが、中国企業でなされている施策との違いを浮き彫りにする比較文化論をやりたかったというのもありました。
羊谷:僕もそうなんですが、今の中国文化の盛り上がりを知らないひとには10年程前に頻りに報道されたコンテンツの剽窃問題のイメージが強く残っています。最近ではもうオリジナリティの面で日本産のコンテンツを超えはじめたのでしょうか? たとえば、以前とは逆に日本が中国産のコンテンツをお手本にしはじめたりとか……。
秋津:作品レベルで中国のこのアニメが日本の新しく制作された作品の参照先になったという話はまだ聞かないですね、おそらく。ただ、ビリビリ動画やウェイボーとか、ああいうソーシャルメディアや動画共有サーヴィスは中国発祥ではないんですけど、日本の声優さんやアーティストなども中国のソーシャルメディアを活用していて、最近ではお客さんの強さというか中国市場の大きさを無視できなくなってきているのはあります。
また、批評的に観た場合、たとえば、新海誠作品に強く影響を受けた中国の李豪凌(リ・ハオヤン)監督が新海監督の所属するアニメ制作会社と共同で『詩季織々』というビジュアル面に凄いこだわりのあるアニメ映画を作っていたり、中国産ゲームでいうとやっぱり『アズールレーン』ですよね。艦隊を擬人化するというコンセプトにおいては日本の『艦隊これくしょん』によく似ている作品ですけど、幅広い国の艦隊を擬人化させ、ゲーム性においても戦闘にアクション要素の強いSTGを採用していたりガチャのレア排出率が比較的高かったりとユーザーライクですので、たとえ作品の元ネタが外国産コンテンツであったとしてもそれを世界レベルで戦えるようにアップデートしてより凄いものを作ろうという気概が感じられます。
なので、技術力はすでに日本と比べても遜色のないものですし 、日本以上のクオリティのコンテンツをあと2、3年以内に産みだす可能性はじゅうぶんにありえますね。
羊谷:なるほど。その文化的隆盛には今の中国を代表する巨大企業テンセントのエコシステム構築の努力が欠かせなかったというのが秋津さんの論ですが、テンセントが何を具体的にしてきたかあらためて教えてもらって良いですか?
秋津:テンセントはエンターテイメント産業の幅広いジャンルでより良いものを産みだすエコシステム形成の試みをしてきたのですが、具体的にはまず知的財産(IP)を大事にする意識付けからはじめました。というのも、テンセントで制作したオリジナルコンテンツをアニメやドラマや映画などにメディアミックスとして展開させることでより多くのお金を稼げるからです。
そのためにはまず、何を作るにしても良い作品を知らないと作れませんよねということで、漫画やアニメだったらやはり日本が強いので日本の作品をキチンと輸入することをテンセントは始めました。ご存知の通り、『ナルト』や『ワンピース』などはすでに有名だったのですが、正式に輸入したものではなく、海賊版が横行し、何でも無料で見放題だったのでテンセントはその状況を変えようとしたわけです。要するに、外国産の作品を正規輸入することで、創作物というものがキチンと対価を伴うものであることを意識付けるとともに、クオリティの高い作品に触れる機会を作ることで作家の創作の糧にしてもらうことがテンセントの狙いだったのではと私は考えています。
そして、テンセントは資本力の強い企業なのでいわゆる作品制作プラットフォームを作りました、日本でいうと「小説家になろう」みたいなのがちょっと近いですね。たとえば、「騰訊動漫」です。そこに、色々なユーザーに作品を発表してもらい、人気のある作品をもてるようになった作家には編集者が付いて技術的な指導をくわえていくことで作家も育てていきました。当然、成長した作家はより良いものを作れるようになるので、多くの読者の眼にふれられ、メディアミックス展開を企画していくなかでさらに収益を増やし、作家にお金を還元することで次の作品に取り掛かってもらうというエコシステムを構築しました。
要するに、テンセントは良い作品という基準の選定から育成、展開までを全部やってしまったわけです。これがだいたい、4、5年前の話ですね。そのあたりの事情は『テンセント 知られざる中国デジタル革命トップランナーの全貌』という本にかなり詳しくまとめられているので、テンセントの事業に興味のある方はぜひ読んでいただきたいです。
羊谷:ゲーマーとして無視できない話題なので述べますが、グローバルなゲーム業界で近年最も存在感を放っているテンセントはそれと同じ試みをこの領域でもやろうとしているように見受けられます。
たとえば、テンセント傘下の Epic Games は世間的には『フォートナイト』の開発で知られ、業界的には Unreal Engine という最も成功したゲームエンジン、プレイヤーとしてはゲームストアが最も馴染み深いのですが、実質的に Steam の1強状態だった配信ストア市場に時限独占販売や週替りの無料配布といった物議を醸す戦術を武器に今殴りこみをかけています。エピックが特にこのストアの「ウリ」にしているのが開発者へのロイヤリティの高さで、従来では7対3と慣例的に決まっていた収益配分からストアの取り分を12パーセントにまで引き下げるなど、開発者に優しいストア運営を続けることが長期的にユーザー全体の利益に繋がると明言しています。
また、月額制だった Unreal Engine 4 の全機能を無料化し、一定の売上額をあげた制作物のみ5パーセントの使用料を支払うようにしてゲーム開発や3DCG作品制作の敷居を下げました。いずれも、クリエイター中心のエコシステムの構築とお金の流れの整備というテンセントの発想を知らないと理解できない動きでしょうね。

via. 『詩季織々』公式サイト
羊谷:秋津さんの評論文ではこのテンセントの試みとブンゲイファイトクラブ批判、特に優勝賞品を名誉のみとしたことが交差するスリリングな展開がありました。少なくとも作品批評に終始していた当時の僕にはその論点は思いつきもしませんでした。テンセントと日本の文芸シーンは秋津さんのなかでどのように結び付いたのでしょう。
秋津:端的にいうと、コンテンツはエコシステムのなかで成長するというテンセントの事業戦略上の目算があって、その仕組みが機能するのに必要なのはどう考えてもエコシステムの血液にあたるお金なんですね。テンセントの場合、お金の良い循環のしかたがよく考えられていることが注目に値します、エコシステムなだけに。
では、日本の文芸界隈にもそういう血液のまわり方を意識されたエコシステムが形成されているかどうか、もしくは文学とお金の関係性についてテンセントほど考え抜いてきたひとが歴史的にいたかどうかを振り返ると、おそらくは少なかったはず。ですから、今回の評論文でテンセントの施策を観ることで、日本のエンターテイメント業界の限られた狭い領域ですけど、文学という場所のエコシステムを照らすことが裏テーマとしてありました。
羊谷:なるほど。では、テンセントの施策を通すことで秋津さんの眼には日本の文芸界隈はどのように映りましたか?
秋津:まあ、日本の文芸の現状をいうと凄くケチですよね。それと、自分たちの置かれている環境への意識がやはり低いなと強く感じます。先程はテンセントを例に挙げましたが、アリババも主には事業者向けの分野でインフラの構築と整備をめちゃくちゃ意識しています。
たとえば、アント・フィナンシャルという農村や零細企業、一般消費者に焦点をあてて様々な金融サーヴィスを提供する企業グループを経営していたり、そこで「芝麻信用」という独自の与信システムを導入していたりと、アリババはもともとECサイトで名を挙げた企業ですけど、事業者のお金の巡りを整備することで自分たちのビジネスをより有利に進めてきた経緯があります。だから、現代の中国企業は環境構築に意識がよくまわるんですね。
一方、日本はというと、企業レベルではある程度意識はされているのですが、文学とかアート界隈でそれがどれくらいできているかというと多分今の中国ほどにはできていないように見受けられます。要はお金が回りさえすれば生活ができ、生活ができれば余裕ができ、余裕ができれば作品制作もできるというのが自然な流れで、テンセントはそれを意識してやっているのですが、先程も少し話にでたブンゲイファイトクラブの「名誉」の話、結局「名誉」は次の仕事に繋がるから意味があるのであって、名誉自体は食えるわけではないですからね。そのあたりが環境構築・整備への意識の違いとして強くでているなと思いました。
羊谷:秋津さんの評論文でのブンゲイファイトクラブへの批判は主に2点、オールジャンルの文芸作品を受け付けるとぶちあげながらも実質的には掌編小説ばかりの「ショウセツファイトクラブ」になっていたこと、そして、優勝者への賞金はおろか何の特権も用意されていないことでした。後者の論点についてもう少し詳しく説明をお願いできますか?
秋津:ブンゲイファイトクラブはデヴィッド・フィンチャー監督作の『ファイトクラブ』を元ネタにしていると推測されますが、あの映画は要するに資本主義的な価値観へのカウンター思想をもった映画ですよね。大事なのはお金ではなくオスとしての名誉をめぐる闘いであり、そのメタファーとしてファイトクラブというストリートでの喧嘩イベントがあると。おそらくそれをある程度下敷きにしてあのイベントが出来ているので、勝者が得られるのは名誉だけというのはそういう意味では的外れではないと思います。しかも、システムにもちゃんと透明性があり、だれがどの作品にどういう審査をして、だれがだれに勝ったかがわかるのは今までの文芸新人賞とは違い、公正で、エンターテイメント性もあり、仕組み自体は凄くしっかり考えられています。
問題は、文芸シーンを変えるというキャッチフレーズにこの企画を全部瓦解させてしまう危うさが潜んでいること。というのも、先程述べたとおり文芸のシーンを変えることを文芸を取り巻く環境を変えるという意味でとらえると、やはり経済というかお金の流れの問題が大事になるからです。文芸の仕組み自体を変えるということはその領域の色々なひとを動かすことが必要で、結局お金がいちばんひとを動きやすくさせるのは事実なので。そして、ブンゲイファイトクラブというイベントも今回が初企画の新しいものである以上は名誉も歴史も実績もまだないわけですから、もし、文芸シーンを本気で変えようとしていたのであれば、名誉以外の報酬を用意した方がより大きなインパクトがあったのではないかと。
もちろん、大学生企画のノリでやっているのであれば全然良いですけど、大のオトナが何人も運営やら何やらに関わっている以上はお金の問題は避けられないじゃないですか。みんな暇なわけじゃなくて、限られた時間を使って審査なり執筆なりをしているわけですから。だから、傍から観ていてこのイベントは趣味人が余暇としてやっているんだなと映りました。つまり、名誉だ尊厳だと謳いつつも結局生活に余裕のあるひとたちが文芸界隈でお祭りをやっているんだな、と。だから、文芸畑の外のひとがあのイベントを観て何かしらのインパクトをもらうかも不明という……。
羊谷:職業的に文章を書いている招待枠の選手や審査員に金銭の支払いがあったかどうかは知りませんが、トーナメント方式という大人数の参加に依拠したイベントでありながら副賞に値するものが何も用意されていないこと、また、それにも関わらずとても多くのひとが参加を希望したという事実にはなにか違和感を覚えますね。それは、文芸創作コミュニティが成熟し、熱気があることの証左なのか、あるいは名誉のために書くという無報酬の創作が意識レベルではあたりまえになっているのか。

羊谷:では、ブンゲイファイトクラブから離れて、日本の出版社中心の文芸シーンをエコシステムの観点からみると秋津さんにはどのように映りますか?
秋津:今回僕の評論文ではブンゲイファイトクラブを例にしましたが、エコシステムという観点では日本の出版社もできているようでできていないと感じます。つまり、新人賞で100万円貰えます、芥川賞で数100万円貰えますという賞金制度はたしかに作家へお金を還元しているようですけども、大人ひとりが1ヶ月に使う金額は30万円とか、安く抑えても20万円とかなので、2、3ヶ月程度はその賞金だけで暮らせてもすぐに次のヒット作品をがんばって書かないと生活者としてはあまり意味がなく、作家を救うことにはならないですよね。もちろん、〇〇新人賞受賞と経歴には書けますが。
それであれば、1回10万円とか、25万円ぐらいで何かしらの仕事を継続的に発注していく方がおそらく作家としては先が見えるぶん、生活者として精神的に安定できるだろうし、クレジット付きの仕事であれば作家としてのキャリアを少しずつ積み重ねていけますから私としてはそちらの方が良いと思います。
もちろん、新書やライトノベルというジャンルであれば印税で食えている作家もいるでしょうが、純文学の世界でじゅうぶんな印税をもらっている作家は少ないと推測されます。たとえば、直近の芥川賞を受賞した古川真人の『背高泡立草』は現在5万4千部程刷られているそうですが、初版は4千部。単価は1500円で、印税が10パーセント超と仮定すると、初版の段階で作家に入ってくるのはおそらく60万円〜120万円くらいでしょう。しかも、古川さんは比較的成功している部類の作家ですが、ほかの新人賞を受賞してからも継続的に作品を発表できている作家の数はというと、残念ながらひじょうに少ないのが現実です。
羊谷:えーと、絶賛ワーキングプア中で1ヶ月の支出をなんとか10万円以下に抑えようとしているコンビニ店員の僕としては聞き捨てならない台詞がいまあったのですが……。
秋津:それは羊谷さん個人の問題ですから今は横に置くとして(笑)、「名誉」の問題に関連してもうひとつ気掛かりなことがあります。つまり、作家の名誉をもちだしてお金の問題に蓋をすることは単純に文芸史の先人たちの試みとその努力を無駄にしているということです。
つまり、文学でどうやって食べていくのかは少なくとも明治時代ぐらいから議論されてきたわけで、この問題に対し、本の宣伝に精をだしたり賞を設立したりして結構色々な作家がとり組んできた経緯があります。だから、文学がいま食えない食えないといわれていますが、別にその悩みは今にはじまったことではなく、現代よりも娯楽コンテンツの量も種類も限られていた昔ですら文学で食えていた時期はとても少なかった。よしんば文学で食えていた作家がいたとしても、ほとんどはちゃんと本業で稼ぎながら小説を書いていたひとたちです。
たとえば、文学賞の社会的地位の向上に寄与した作家のひとりが菊池寛でしょう。彼が創設した芥川賞ももともとは世間的にさほどの注目を集めていた賞ではなく、今でこそニュース番組で報道されたり新聞の紙面に大きく掲載されたりして文芸関係の賞ではいちばん有名ですが、当時は本当にもう本当にちっちゃなところで芥川賞だれだれ受賞みたいな扱いに過ぎませんでした。それに対して菊池寛が抗議したり、ほかの作家が地位向上のために奔走したりという頑張りがあってようやく芥川賞があそこまで権威のあるものとして成長できたんです。こういった文学とお金の関係は『カネと文学 日本近代文学の経済史』という本が詳しいです。まあ、実はこの書籍は羊谷さんに「もしかしたら面白いかも」と8年くらい前に紹介されたものなんですが(笑)
つまり、日本の文壇の黎明期においては文学で食えるようにするエコシステムの構築と整備をしようという気合の入った先人がいたわけですが、それに比べて今の作家はどうかというと、まあ、お世辞にも多いとはいえません。要するに、既存のシステムに作家もそのまま乗っかって出版社がなんとか頑張っている今の現状で、ブンゲイファイトクラブ自体は面白い試みだとしても、その運営者が真剣にエコシステムの問題を、具体的にはお金をどうやってうまく配分するかなどを考えないことには文芸シーンは変わらないでしょうね。
羊谷:なるほど、貴重なお話をありがとうございました。
今回お話を聞いた秋津燈太郎さんの評論「中国現代文化のエコシステムとブンゲイファイトクラブ批判」が掲載されている『GLATIA vol.6』は送料別500円で販売しています。興味をもたれた方はぜひこちらの文芸同人「抒情歌」さんに購入希望の連絡をしてみてくださいね。