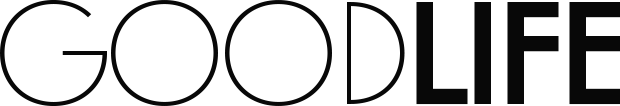ゲームの面白さとは何か?
霊視能力を「呪い」のように背負ってきた主人公が突然掛かってきた謎の電話の求める助けに応じ、ソ連の衛星国時代に「大虐殺」があったという都市伝説の残る朽ちた保養園を探索する――。
昨年最も話題を呼び、毀誉褒貶に晒されながらも重要な金字塔をうち建てた CD Projekt を筆頭に、近年東欧のポーランドがゲーム開発大国として注目を集め続けてきたのは情報感度の高いあなたならご存知だろう。
本作『The Medium』を制作した Bloober Team もまたクラクフに拠点を置き、『Layers of Fear』シリーズなどのサイコホラー系ADVで高い評価を獲得した気鋭のゲーム開発企業だ――個人的にもまだデジタルゲームを漁りはじめて間もない頃に体験した、押井守の実写映画『アヴァロン』を彷彿とさせる『Observer』の陰鬱な世界観と独特なヴィジュアル表現はよく印象に残っている。
本作は、マイクロソフトの専売タイトルながらいくつかの独創的な特徴でリリース前から高い前評判を得ていた。
日本でもサブカル界隈で人気のズジスワフ・ベクシンスキーを思わせる世界観や、分割画面による現実と霊界のパラレルな探索行動、オールドスクールな定点カメラの採用などだ。
結論からいうと、ゲーマー目線では買い切りの6千円強は高過ぎるが、月額制のゲームパスなら一見の価値はアリ、批評家目線ではけっして面白くはないが、優れた部分も少なくなく、感銘を受ける場面もあり、デジタルゲームの良さを問うには意味のある作品だった。
その内容の薄さから世に流通しやすい「推し」や「解釈」とは一線を引き、原理的な洞察も踏まえた忌憚なき分析と評価を書いていこう。

『The Medium』は面白いのか?
この端的な問いにはまずデジタルゲームへの原理的な洞察からはじめたい、というのも、本作は面白くはないが高く評価すべき部分もある厄介な作品だからだ。
ゲームの面白さにはシステムによる課題設定とプレイヤーの試行錯誤が前提にある――ただし、ソリッドな課題とリキッドな課題という違いには注意が必要だ。
たとえば、敵対的NPCやプレイヤーを倒したり、パズルを解いたり、何らかの方法で一定時間生き延びたりすることはゲームシステムから用意された課題であり、特殊な例、たとえば強力な装備やアイテムを手に入れる寄り道などを除けばこの課題解決は避けられず、対人戦では勝利としてプレイの目的そのものになる。
そのため、ソリッドな課題では常に難易度設定やバランス調整が問題だ――だれだって、あまりに理不尽過ぎたりイージー過ぎたりする課題に愉しさは覚えられず、プレイヤー間の公平性がない課題をマジメに取り組もうとも思えないからだ。
それに対し、リキッドな課題とは、タイムアタックやロールプレイ、プレイヤーが欲するままの自由な建築、特定の武器や防具のみに使用を限定したある種の縛りプレイなど、ゲームデザインが用意したものを時に意図されざる形で利用するも課題自体はプレイヤーが自発的に考えたものだ。
そのため、リキッドな課題では常にプレイヤーの自由度が問題になる――『Apex Legends』でウイングマンやモザンビークなどの武器縛りができるのはそれだけ多様な選択肢が用意されているからで、『Minecraft』が高い人気を誇り続けているのもそれだけ自由な課題設定を促すからだろう。
もちろん両者の関係は複雑で、二元論に割り切れるほど単純ではない。
一見するとリキッドな課題の試行錯誤は時にシステムやルールを「ハック」する創造力が必要なことからより耳目を集めやすく、高級に見られがちだが、ソリッドな課題を最終的に解決できなければどのように面白いやり方でも有効とはみなされない――今や数多くの作品に導入されている建築要素も大抵はプレイヤーキャラクターの安全を守る目的があり、武器の縛りやロールプレイ、カードゲームにおける奇を衒ったコンボもゲームクリアや対人戦に全く勝てなければリキッドな課題解決を達成したとは言い難いはずだ。
結局のところ、ソリッドな課題は常にゲームデザインが要所要所で規定の結果を求めるのに対し、リキッドな課題はその結果(ソリッドな課題達成)に至るまでの過程におけるプレイヤーの自発的な課題設定と試行錯誤であり、前者の達成がある種の前提条件として後者の成否をチェックする関係にあると整理できる。
ここで、ソリッド/リキッドな課題という分析上の概念を導入したことでゲーム作品がプレイヤーにどのような試行錯誤を強要/許容しているか観えてくる。
その意味でいうと『The Medium』は実のところ簡単なパズルを解くゲームでしかない。
つまり、課題設定とその解決というより抽象的な視点でみれば本作は要所要所のパズル(ソリッドな課題)を解いて物語を進めるだけで、その過程におけるプレイングの自由度(リキッドな課題設定)はほとんど許されないデザインだ――ちなみに道中には主人公を捕食する異形の敵が登場するが、プレイヤーのハンドスキルを要求する場面は僕の感覚ではなかったのでアクション要素は認めていない。
また、当のパズル自体も基本的には一本道で、さまざまな仕方で課題解決がガイドされているのでやり甲斐が感じられず、解決時に喜びを覚えるものでもなかった。
ちなみに、昨年のゲーム業界で最も高く評価された『Outer Wilds』も同様に、抽象的に観れば、デザインされたパズル課題を解くことで物語を復元し、その過程におけるプレイングの創造的な自由度がほとんど許されない線の細い作品だったが、ソリッドな課題解決に焦点を絞ればパズル課題を解く順序はプレイヤーに委ねられているので自由な印象を与えるデザインだろう。
その比較からもやはり本作『The Medium』はソリッドとリキッドの両方の課題で自由度がなく、その印象も与えない、単純明快でやり甲斐のない作品だと批判せざるをえない。
特に、本作の特徴でもある現実と霊界を股にかけた分割画面での探索は蓋を開けるとどこかでやったことのある仕組みばかりで大きく失望したのが正直なところだ。

思うに、本作を開発した Bloober Team がここまで単純なゲームプレイをデザインしたのはひとえに没入感のためだろう。
実際、雰囲気重視のダークな世界観でちょっとしたパズルやステルスを中心にデザインされたものは多く、たとえば Playdead による『Inside』や『Limbo』など世間的に高く評価されたカルト的作品もある――「だったらドラマや映画でいいじゃん……」と思う向きも個人的にはあるが。
また、先程述べたように本作は要所要所のパズル課題をかならず解いて進むだけの作品だが、パズルを解くという課題の報酬が必然的に物語を先に進めるだけになり、本作の魅力は他の作品にも増してドラマ的側面(物語や音楽、映像、人物造形など)に大きく依存する。
その意味で、本作のヴィジュアル表現を考えるうえで Bloober Team が採用したオールドスクールな定点カメラ、というより、3人称視点ながら肩越しの画一的な動きから解放された開発主体のカメラワークは重要だ。
実際、本作の普通の意味で美麗なグラフィックとは相性が良く、僕が以前から主張しているデジタルゲームとアートの融合という観点でいえば、昨年の『Cyberpunk 2077』や『The Last of Us Part 2』とはまた違った端緒を切り拓いたといっても過言ではない。
もっとも、純粋な映像表現として考えると、本作のカメラワークはプレイングの利便性を考慮してかフィールドをより広く捉えられるようにやや引き気味のものが少なくなく、カットの独創性や臨場感という観点では物足りなさも強く感じた。
パズルにしてもステルスにしてもかなり簡単でかつ親切なデザインなので、多少のプレイアビリティを犠牲にしてでもその表現の可能性を追求してほしかったところだ。
グラフィック自体に眼を向けると、レイトレーシングとHDRを有効にした最高の画質設定ではさすがに出色といわざるをえず、夜明けとともに湖畔で迎えるクライマックスは近年のゲーム作品でも屈指の美しさだと称賛できる。
が、前半部の廃墟探索は本作のシグネイチャーといえるグロテスクな霊界が分割画面上で最もよく交錯するパートだが、低俗な表現に耐性のある僕でもややうんざりする息苦しさと不快感が続き、後述する物語の停滞感もあいまり結構辛い体験だった。
10時間の忍耐の末に得られる結末はたしかに優れた出来映えだが、その過程はなかなか苦行に近く、「ドラマで良くない?」という想いが何度も頭をよぎったことを告白したい。

さて、本作の物語への僕の評価もまた複雑なものだ。
主人公マリアンの霊能力を知る謎の男の助けを求める電話が養父の死とともに掛かってきたことで物語は幕をあけるが、保養園の廃墟で「サッドネス」と称する少女の亡霊と出会うことで他人の謎から自分自身の封じられた記憶の探索行へと物語が変貌する。
そのため、冥府下りという古典的な構造をおさえながらもその果てに見出すのは人間の心の闇であり、失われた記憶であり、悲劇的な事件であり、今もなお尾を引く自身の出自の秘密という仕掛けになっており、最終局面ではそれらとの対峙を迫られるという比較的良く出来たシリアスな物語となっている。
また、小児性愛者による児童虐待や、社会主義体制下における秘密警察など、アートフォーマットとして娯楽的側面の強いデジタルゲームではあまりふれにくい社会的意義のあるテーマを盛り込んだのも高く評価できる。
ただ、プロットとして、つまり、俯瞰的に何が起こっていたかではなくプレイヤーと主人公が直接経験する物語として考えた場合、前半部の廃墟探索はほとんど意味もわからず「サッドネス」に振り回されるだけなので正直物語に魅了されてプレイする感覚はもてなかった。
冒頭から一貫して主人公が語っているその話相手はだれなのか、保養園の廃墟になぜ何者かが主人公を監視していた形跡があるのか、大虐殺は何故起きたのか、そして、少女の亡霊「サッドネス」とは何者なのかなど、序盤から複数の伏線が仕掛けられているにも関わらず、物語の謎が加速し、収束するのは結末間近のほんの1時間足らず。
クライマックス直前、主人公がある人物と邂逅し、この陰惨な物語をいちから物語りはじめてからの場面はカメラワークも含めて実に感動的な美しさがあるが、前述の通り、デジタルゲームとして操作感や試行錯誤が愉しめる作品ではないからこそ、物語前半のフックの弱さは致命的な短所といわざるをえない。
くわえて、心的外傷をストーリーの中心軸に据えたせいで近年の物語としては空間的な拡がりを欠く息苦しいものになった印象も拭えない。
総じて、大筋としては高く評価しつつもゲーム性の弱さを補って余りある物語の出来かというと僕はそうではないと判断した。
その意味でもやはり「ドラマで良くない?」という疑問が何度も首をもたげるのだった――というのも、アートフォーマットとして明確な話の区切りがある以上、物語のフックと次回への引きをその都度作る必要に迫られるからだ。

デジタルゲームへの愛着が強いひとには他のアートフォーマットと並べて問うことが愚問に思えるかもしれない。
しかし、プレイヤーの可処分時間は現実問題として限られており、有償無償を問わず多種多様なコンテンツが今の世に溢れかえっている以上、デジタルゲームのゲーム性が貧弱なことは僕には大きなマイナス要素にしか思えない――ただでさえゲームは鑑賞者に課すエネルギーが高く、相応に楽しむには結構な時間を費やさなくてはならないのだから。
とはいえ、繰り返しになるが本作のドラマ的側面はけっして悪いものではなく、特にその映像表現の可能性は Bloober Team 自身の手でなくとも今後追求され、ヴィジュアルアートとの融合として深化すべきもののように僕の眼には映る。
物語自体も、賞賛はできないまでもシリアスな深みのある優れたものだ。
僕がなぜゲーム批評を書くか、それもSNSで人気を得やすい「推し」ではなく耳障りな分析と批評に全振りするかには色々な理由があるが、そのひとつは作品分析で構造をひらき、批評の価値付けでその中身を検証可能なカタチで腑分けし、耐久年数の高い言葉/文字として社会に残すことで何らかの可能性を他人とその未来に繋ぐことだ。
もちろん、それ自体に何の意味があるかは僕の預かり知るところではない。
ただ、ゲーム作品が発表され、メディアによるアナウンスと当たり障りのないレビューや攻略系まとめサイト、素朴な実況系感想、バズ狙いの「推し」記事の流砂に覆われて忘れられるよりはひとつでも率直でかつ分析的な文章が増えたら良いと思う。
「サッドネス」のように時が凍り付き、廃墟にひとり遺されるよりは。