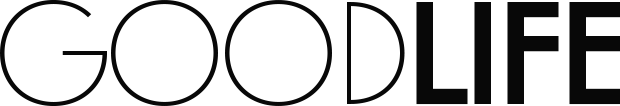ソーシャルメディアの罵詈雑言の暴力
せっかく気になっている相手と一緒に遊びに来たというのに、相手は隙を見つけてはスマホを取り出し、指紋の凹凸の具合が心配になるほど熱心に画面をこすっているのでモヤモヤした、という経験をお持ちの方はいますか。しかも、それとなく画面を覗いてみると(最も推奨されざる行為)、ツイッターのアプリが開かれていて、今まさに「沈黙が長すぎて息苦しい、なんか喋れよ。はやく帰りたい」という心の叫びが、裏アカウントから投稿されようとしている……。
SNSとは人間の隠された心理を可視化する、暗視ゴーグル並みの画期的な発明です。秘密があるから疑いが生じるのだ、すべてさらけ出せば疑いは消え、そこから生じる人間の浅ましさもきれいに洗浄される、という屈託のない自由な思想こそが重要なのでしょう。
私は前回の記事で、罵り合いの二つの大きな要素、当事者と野次馬について検証しました。ただ、主に当事者を検証するばかりで野次馬についてあまり言及できなかったので、今回、結果として野次馬について検証する内容となったのは、第二回として自然な成り行きだったのだと思います。当事者についての「じつに啓発的で分かりやすく猿にも読めて誰もが人生の指針にしたいと切望するような、有益な情報」に興味のある方は是非、第一回をお読みになってください。
罵り合いの構造、R-指定と呂布カルマの名勝負を文学的に読み解く
誰かが猛烈に怒鳴られていたり、しょうもない言い合いをしている様子というのは、じつに面白い見世物です。ただ、自分が怒鳴られたり、言い争いに巻き込まれるとなると、事態は一転、憂鬱で腹立たしいものに変わってしまうのではないでしょうか。
さっそく、前回の予告通り「ドン・キホーテ」における罵り合いを詳らかにし、理解をさらに深めていきましょう。と、言いたいのですが、遠くで小銭が地面をはねる音すら決して聞き逃さない、繊細で貪欲な人間よろしく、私はふいの罵り合いの気配を感じ取りました。まずは、青い鳥のさえずり、トラツグミのような不吉な響きを含ませるその鳴き声を頼りに、罵り合いの気配の充満するネット世界を訪ねてみることにします。寄り道とはいえ、新鮮な罵り合いに出会えれば儲けものです。
皆さん、「種子法」「種苗法」をご存知ですか?
— Ko Shibasaki 柴咲コウ (@ko_shibasaki) April 30, 2020
これは、有名タレントの柴咲コウ氏が、4/30に自身のTwitterアカウントで投稿したツイートです。存じ上げなかった私はネットで調べてみることにしました。というのも、どうやらこの教育的効果抜群のツイートをめぐってまさに罵り合いが、もとい、議論が紛糾しているようなのです。すでに群がり始めていた野次馬に交じってことの次第を鑑賞するために、前情報を集めましょう。以下は私がネットを平泳ぎしながら、手あたり次第に拾ってきた情報のまとめですから、当然信憑性に欠きます。
まず、種子法と種苗法は全く別の法律です。ただ、なぜか種子法はそれほど話題になっていないので、今回は種苗法を中心に見ていきます。
今年の通常国会に「種苗法改正案」という法案が提出されました。その法案をめぐり、今年の5月から6月にかけて、ネットを中心に反対運動が起こったのですが(反対運動とは、基本的には、自分のツイートにおそろいのハッシュタグをつけることを意味します)発端となったのが、上記のコウ氏の「ご存知ですか?」のツイートです。種苗法は、一般に、種の開発者の権利を守るものであると認識されています。知的財産の保護、と言い換えてもいいでしょう。今回の改正案では、新種の海外流出などの事態を受けて、その保護がより強力になるといわれています。一方、反対派は、保護とは同時に規制であり、新種の開発者の権利を強めることで、農家経営者への風当たりが強くなると意見します。
ただ、種の開発者と農家経営者は、対立しているわけではないのです。農家経営者がいなければ、どんなに優れた種があっても、効率的に作物を育て、収穫することはできません。また、病気に強く味の良い作物をローコストで生産するためには、優れた種の開発が必要です。論点は、新種の違法な海外流出を防ぐために、どこまで権利を保護するのか、という点に絞られるでしょう。
すると、種苗法改正案の反対派の意図は二つに分けることができるようです。一つは法案の国会への提出が拙速であったことに対する「一旦持ち帰らせてください」であり、いわば穏健な、内容の再検討の申し立てです。もう一つは、農林水産省すなわち国家と、なにやら裏であやしい法案が通ろうとしていると不安がるTwitter人民とのあいだで生じる、法案の内容とはさほど関係ない運動です。
現在(7/18)、通常国会の会期は終了し、種苗法改正案は見送りとなりました。大手柄の火付け役、コウ氏は次のようなツイートをしています。
今回のことに限らず、例えば学校や会社などで何かを決めるときに、誰か一部の人の意見で物事が決まっていってしまうと、残された人の懸念や不安が置いてきぼりになってしまいます。意見を言うことは、誰にも平等に与えられた権利です。
じつに常識的で率直な言葉で、人々の心理を的確に描きつつ、権利を主張してます。
しかし事実とは異なる投稿、捏造、誹謗中傷、脅迫行為、ミスリードしさらなる事実誤認した記事の作成元に関しては法的措置も検討しています。
— Ko Shibasaki 柴咲コウ (@ko_shibasaki) May 27, 2020
コウ氏は、意見をすることは大切だが、根も葉もない、人を傷つけるようなことは言ってはならない、と伝えようとしているのでしょう。建設的なことなら言ってもいいが、罵り合ってはいけない、と。実に優秀な見解です、が――。
前回の記事で私は、法的措置、すなわちルールの適用は、スポーツを成立させることはできても、罵り合いを成立させることはできない、と書いたつもりです(もしかするコウ氏は、前回の私の記事を読んでいないのかもしれません)。感情的な低次の意見は法的措置をとることで処理し、理性的な高次の意見、たとえば種苗法については自由に発言するべきである、というコウ氏の判断に、罵り合いを期待する私は、冗談ではなく、全く賛同できません。
たしかに、すべての感情的な意見にいちいちつき合っていたら、いくら時間があっても足りず、堂々めぐりを繰り返すだけです。それに、法的措置、という言葉は、誰かからの罵りに耐え切れなくなったとき、付き合いきれなくなったときに適用できる、一種のセーフティでもありました。しかし、はじめに人々、あるいは30万人を超える自身のフォロワーに感情的な働きかけをしたのは誰でしょう。たとえ意図がなかったとしても、コウ氏のツイートは「国家が悪巧みをしているかもしれない」という、危機意識への呼びかけと捉えられる種類のものだったのではないしょうか。もちろん、「たしかに悪巧みをしてそうだな」と思われる国家に問題があることは自明ですが。
じっさい、はじめからルールに則った、理性的な言葉で種苗法についての議論を起こすつもりであれば、今回のような認知の広がりは見せなかったでしょう。まず感情的に議論を起こし、最後は理性的に、感情のさまざまな副生成物を排除していくというやり方は、炎上商法そのものです。結果として、国会で見送りになった種苗法改正案について、それがよいことだったのか悪いことだったのか、素人の私には判断できません。ただ、罵り合い専門家としては、罵り合いの雰囲気だけを利用しながら、法をちらつかせて実際に罵り合わずに終わらせようとする上品な対応は、全き欺瞞であると考えます。罵り合いがなければ、罵り合いは鑑賞できず、世界は闇に閉ざされます。
コウ氏を批判するつもりはありません。しかし、そこにどんな大義があったとしても、おこなわれていることはマッチポンプ(自作自演)であり、罵り合いの上澄みを掬う行為であり、長期的にみれば消耗でしかないと思います。法的措置という言葉はトラブルを事前に回避するための抑止力としても機能するようですが、同時に、罵り合いの生成を阻害する有毒ガスとしての役割も果たすのです。また「抑止力」は、あえて換言するなら「脅し」でもあります。
このあたりで、罵り合いという野蛮な行為を奨励する私に対して「貴様は罵られたことがないから、自分を特権的な立場において無責任なことを言っているだけだ。世間知らずのおめでたい野郎め。人の気持ちを考えろ。感情のない人間のくず、差別主義者」といった意見もありえるでしょう。こんなことを言う野郎こそが「おめでたい人間」なのであって、耳を貸すだけ無駄ですし、たしかに、ささっと法的措置という言葉でまとめて処理したくもなります。
ところで、ここで唐突に現れて厚顔にも罵りをおこなう「おめでたい人間」とは、いったい誰なのでしょうか?
ここで種苗法の話題を一段落させ、ドン・キホーテの文学世界に入っていきたいと思います。ここがちょうど3分の1の地点で、もうすぐ折り返しですから、おたがい頑張りましょう。

思い直してみると、後編のドン・キホーテは、いわゆるおめでたい人間に翻弄され続ける人物であり、前編よりもさらに悲しみに満ちた物語が展開されていました。もしかすると、ここに手がかりが見つかるかもしれません。おめでたい人間の正体さえ分かれば、法的措置以外の手段の講じようがあるというものです。そうなれば、抑圧されていた罵り合いが表面化するはずですから、みんなで鑑賞して、みんな幸せになれます。世界に光が差します。
ドン・キホーテとは50歳になろうとしている一人の男性の名前です。当時(17世紀スペイン)流行していた騎士道小説を読みふけるうちに、「睡眠不足と読書三昧がたたって脳味噌がからからに干からび、ついには正気を失ってしまった」彼は、自身を騎士と見なし、鎧を身に纏い、従士サンチョ・パンサとともに世の中の不正をただすための冒険に出ます。彼と出会う人々はみな、彼の狂気に触れ、新鮮な驚きを覚えます。紆余曲折を経て、最後に彼は故郷に帰ることになるのですが、ここまでが前編です。今回は前編にはとくに言及しません。
後編では、前編の冒険から約一ヶ月後、やはり狂気から回復していないドン・キホーテが、従士サンチョ・パンサとともに新たな冒険出ようとするところから、物語は始まります。前編との大きな差は、作中の約一ヶ月の期間に、ドン・キホーテの前編の冒険が本として出版されていて、彼は有名な狂人として世間に知られているということです。作中で「も」、出版されているというのがポイントです。もはや人々はドン・キホーテに新鮮な驚きを感じません。自身を騎士とみなし、魔法や巨人の存在を信じているその愚かしさは、本の出版によって周知のこととなっているので、人々はドン・キホーテの狂態を鑑賞するために、ドン・キホーテに偽りの冒険を提供するようになります。
では、提供された冒険のうち、第三十六章に始まる<苦悩の老女>にまつわる代表的な冒険を、みていくことにしましょう。ここでのドン・キホーテの目的は人助けですが、私たちの目的はおめでたい人間の正体を探ることにあります。
第三十六章において、ドン・キホーテ主従はとある公爵夫妻に騎士とその従士として、歓待を受けていました。しかし、出版されている前編を読み、すでに彼らのことを知っていた夫妻は、当然、ドン・キホーテが騎士ではなく、ただの狂気にとらわれた人間であることに気付いています。つまり、あえて騎士としてもてなしたのです。夫妻は大勢の召使いにも、主従を丁重に扱うようにと裏で指示しています。主従は、夫妻にとっては、愉快な見世物に過ぎません。そこへ、<苦悩の老女>が現れました。
<苦悩の老女>は、いろいろあって、巨人の魔法によって、女性なのにひげ面にされてしまったから助けてほしい、とドン・キホーテにすがりつき、それをドン・キホーテは騎士なので二つ返事で引き受けます。で、なにをすればいい、と訊ねるドン・キホーテに、<苦悩の老女>は、憎き巨人を倒してくれ、巨人のいるところまでは特別性の木馬で行ける、その木馬はじきに現れるはずだ、と言います。
夜になり、緑色の蔦をまとった男が四人がかりで大きな魔法の木馬を運んできました。ドン・キホーテ主従は、木馬にまたがる前に目隠しをつけるよう言われます。木馬が空を疾駆するので、めまいを起こさないようにするためです。いよいよまたがると、木馬は飛び上がり、主従は速度を感じさせる強風や、太陽に近づいた証としての熱と皮膚のほてりを感じました。しかし、唐突に爆発があったかと思うと、主従は「ほとんど焦げたような状態になって地面に叩きつけられてしま」います。いったいなにが起こったのでしょうか?
じつは、<苦悩の老女>は公爵夫妻が用意した役者でした。もちろん、木馬はなんの変哲もない、ただの木馬です。主従が目隠しをしているのをいいことに、風は、召使いたちがふいご(送風装置)を吹き、熱は、燃えている麻くずを吊した長い竿をゆっくり近づけていただけでした。そして、最後の爆発は、木馬の空洞の腹の中にオデュッセウスの代わりに詰め込まれていた爆竹に火をつけたことで起こったのです。すべて、公爵夫妻によって仕組まれた愉快な見世物でした。
注目すべきなのは、ドン・キホーテ主従が、木馬にまたがって空を飛んでいると思い込み、風や熱について驚きと感嘆のコメントを長々と差し挟んでいるあいだ、周りでは、公爵夫妻のみならず、大勢の召使いたちも、必死で笑いをこらえているということです。現代風に言えば「ドッキリ」なのですが、ネタばらしはありません。仕掛け人は、公爵夫妻ということになりますが、彼らは同時に鑑賞者でもあります。もしくは、召使いたちを含めた鑑賞者たち全員が仕掛け人とも言えます。
この状況は、いったいなんなのでしょうか? こう考えることもできます。ネタばらしのないドッキリは、なんのためにおこなわれるのか。じつは、ドン・キホーテの作者セルバンテスは続く冒険において、ある明瞭な解説を加えています。

<苦悩の老女>をめぐる冒険が終わると、ドン・キホーテは、別の老女に泣き付かれます。なんでも、自分の娘が、ある男と結婚する約束をしたにもかかわらず裏切られた、しかし相手は大金持ちの百姓で復讐することもままならず、ドン・キホーテ以外に頼れる人がいない、と。じつは老女の主人である公爵は、娘を裏切った金持ちの男の父親に、頻繁に借金の保証人になってもらっているため、まるで力を貸してくれないのです。
ドン・キホーテは騎士ですから、困っている人を放っておきません。そのやりとりを耳にした公爵は先回りして、娘を裏切った男の代役を自分の召使いに務めさせることにします。兜の目庇を深くおろせば、決闘のさなかに偽物だと気づかれる心配はありません。さらに、召使いにはドン・キホーテを殺さないように指示し、ドン・キホーテには、あなたの宗教(キリスト教)は生命を危険にさらすことを認めない、と説得し、槍の穂先を外させます。こうして公爵は、老女とその娘の名誉のかかった決闘を、自然発生しかけていた本物の冒険を、自分たちの楽しみのために、命の危険のないおふざけにつくり変えてしまったのです。
しかし、実際には公爵の考えていたほど、ことは上手く運びませんでした。召使いは、老女の娘を一目見るなり、恋に落ちてしまったのです。この決闘は自分の負けでよい、だから、当初の約束通り結婚することにする、と兜を外して棄権してしまいます。そのときの状況について、セルバンテスは、次のような解説を加えました。
広場の観衆は、ドン・キホーテの勝利を称えて、拍手喝采した。とはいえその大半は、彼らが期待していたようには決闘が展開されず、二人の闘士がずたずたに切り裂かれる様を見られなかったがゆえに、落胆し、不満そうであった。それはちょうど、絞首刑になるものと思われていた罪人を、訴人が、あるいは法廷が赦免したために首吊りが執行されなくなり、期待していた見物の子供たちが、ひどくがっかりするのに似ていた。
その後、老女とその娘は、兜を外した代役の男の顔を確認して、公爵に抗議の声を上げます。
いんちきよ、これは! 御主人の公爵様の従僕を、あたしの本来の夫の替え玉にしてるんですもの! 卑劣なぺてんとは言わないまでも、こんな悪ふざけをするなんて、どうか神様と国王陛下のお裁きを!
via. セルバンテス『ドン・キホーテ〈後篇3〉』
この罵りには、社会階級の異なる人間、とくに自分より目上の人間に対する、悲痛な響きがあります。そして、ここに罵り合いは成立しません。なぜ成立しないのか、それは、本来なら中立的な立場を保っているべき野次馬たちが、この「悪ふざけ」を主催する公爵に全面的に味方をしているからです。ここでは、ドン・キホーテが信じているものはすべて笑いによって相対化され、見物人たちによって囲い込まれてしまっています。
ドン・キホーテにおける罵り合いは、ここまで、幾度となくずらされてきました。前編では、ドン・キホーテ主従による罵り合いでした(私はもともと、この部分を紹介するつもりだったのです)。それが、わけを知っている人々、おもに公爵夫妻の登場によって仕組まれた冒険に変貌しました。加えて、自然な冒険がうまれる機会までもが、わけを知っている人々の「いんちき」によって奪われ、見世物として消費されていきます。前編においては、登場すらせず、本によってその内容を知っただけの野次馬であった人々が、ようやく物言うための口を得たかのように、後編では積極的に関わってくるのです。
彼ら彼女らは部外者であるにもかかわらず、身の程知らずにも、あるいは、自分たちが野次馬に過ぎないということを自覚していないために、他人の営みに口を突っ込み、お節介をしてくるのでしょう。それでいて、野次馬としての性質である、匿名性、社会的な地位や階級への意識、部外者面をしっかり保持する彼ら彼女らは、私が知っている野次馬とは別の存在です。暗闇に紛れて石を投げつけ、それが肉にぶつかることで喜悦する卑劣さは、たかだが400年くらいなら、平気で人間の魂に保存され継承されるのだということがはっきりしました。
さらに想像力の翼を広げるなら、もしくは、無責任な思い込みを書き連ねるなら、最後に引用した老女の「どうか、神様と国王陛下のお裁きを!」というのは、公爵よりも身分の高い存在に助けを求めている、という意味ですが、神様はおいておくとして、君主制では最高の権力は国王にあります。立憲君主制ではどうでしょうか。おそらく、「(憲)法の裁きを!」となるのではないでしょうか。しかし、ほのめかすように「法的措置をとります」と言う場合、悲痛さよりは卑しさが目立つように感じるのは、しかし、私の思い込みでしょう。
ようやくここで、2/3の地点に到着しました。ドン・キホーテという文学の沃野を、最短距離で通り抜けたところです。これ以上ドン・キホーテについて書くことは、せっかくの一人旅で無理矢理ガイドをつけられるような鬱陶しさを、読者の皆様に感じさせることになってしまいますので控えます。

最後はもう一度、現代における罵り合いを調査してみましょう。どうせ、現実は明日もいつも通り続いていくのですから、最後にはちゃんと400年分時間を進めて、現代に戻ってこなければならなりません。まずは、あるおめでたい人間の率直なコメントを紹介します。
リアリティー番組というフィクションの、登場人物への批判という意識でした。発言が非常に不快だったので、それに反応しただけです。ほかのテレビ番組でも出演者のアカウントに意見を書き込むことがあります。タレントとして活動する人の個人アカウントへ意見を発信することに問題があるとは考えなかったです。
via. 木村花さんの死が問いかけるもの
リアリティー番組とは、世間的に無名かそれに近い出演者と同じ名前を持った男女の登場人物たちが生活する様子を撮影し、編集したものを放送するテレビ番組のことです。もし登場人物のパーソナリティに、現実と番組のあいだで乖離があるとすれば、そこには演技があるということになり、演技は虚構ですからリアリティー番組ではないということになります。名前の統一は、そのような乖離が生じていない場合には効果的かもしれませんが、ほんとうに現実と番組の人格はぴったり一致していたのでしょうか。もし、現実と番組の人格の同一性が、強制されたものだったとしたら?
リアリティー番組に脚本がないと主張することは、映像に納められているのはすべて自然発生したものだ、と言うのと同じことです。そこでどんなことがおこなわれようと、制作者にはなんの責任もない、と言外にメッセージを発しているのです。これによって、視聴者、もしくは野次馬たちは、テレビドラマにおける虚構の障壁をらくらく乗り越えて、(というより、制作者がこの壁を取り壊したのですが)真っ先に出演者へと、奔馬のように突っ込んでいきます。結果、おめでたい人間たちが蚊柱のように大集合します。
はたしてそのとき、出演者は何を感じたのでしょうか。このことを考えるのは、私の手に余ることであり、傲慢なことでもあるでしょう。そのことを踏まえた上で、可能な限り接近してみることにします。
彼女の不安は想像を絶するものだったはずです。同じ名前と身体によって関係づけられ役者が役を終える、という瞬間が片時も訪れない。一瞬も安心できない。SNSでは、毎日のように番組の自分を非難する言葉が並ぶ。それはほんとうの自分ではないと反論すれば、リアリティー番組自体が虚構なのだと告発することになってしまう。虚構の自分に対する他者からの人格否定は、現実の自分への人格否定として流れ込んでくる。出演者と登場人物としての自分は別人なのだと分かっていても、もしかすると共通点があるのではないか、全く同じ体で、全く同じ名前なのだから、似ているところがあるのではないか。そのような疑いが生まれる。あるいは、むしろ違いなどなく、現実と虚構は一致しているのではないか。もはや、自分自身のことが分からない。どこまでが自分で、どこまでが自分でないのか。誹謗中傷は、真実の自分を知らない。本当に? もしかしたら、自分はみんなが言うような人間なのかもしれない。なぜなら、みんながそう言っているから。
たった一人、誰からも理解されず、憎まれ恨まれ嫌われているのだという状況で、どのような生活が可能だろう。そして、自分自身を誤解しなければならないような状況、最も理解しているはずの自分自身を否定しなければならないような状況で、どうして明日も生きようという気持ちが生まれるだろう……。
ここに至って、おめでたい人間は殺人を犯した、ということなのでしょう。しかし、彼らは口をそろえて、そんなつもりはなかった、と言います。もちろん彼らを法的措置という網にかけて処理するのもいいでしょう。ただ、彼らの幼い感情をくすぐり、たきつけたのは誰なのかについて、考える必要もあります。それに、リアリティー番組そのものへの人々の欲望は、法的措置によって解消できるでしょうか。現に、リアリティー番組自体は世界で30名以上の方が亡くなっているにもかかわらず、存続しているという事実があります。
(これは蛇に腕をつけるような行為ですが、リアリティー番組では視聴者を巻き込むために、(気にくわない)出演者を投票で排除する制度がある場合があります。『ビッグ・ブラザー』シリーズや、日本では『オオカミくんには騙されない』シリーズなどに存在しているようですが、この視聴者の介入のさせ方には気がかりなものがあります。個人がまるで為政者、もしくは支配者のように、誰を残し誰を排除するかを決定することの違和感について検討した小説に、安部公房の「箱舟さくら丸」というものがあるので、興味のある方は読んでみるといいかもしれません。ただ、これ以上続けると、蛇の体にムカデのような大量の脚を接続することになって不気味なので話を戻します。)
おめでたい人間は、自身の暴走した野次馬精神と、腐った感受性だけを頼りに、攻撃できそうな人間を狙って攻撃し続け、都合が悪くなれば自分はあくまでも傍観者なのだ、という態度を取って責任や反省からの幼児的な逃走を続けるでしょう。また、社会的地位の高い人間や著名人、もしくは学歴のある人間たちは、一流の詐術で自身を弱者と偽り正当性を誇示しながらむやみに「法的措置」を持ち出します。弱者のものであるべき法は、感情的な人々を機械的に弾圧するための脅し、もしくは実行力となるでしょう。
そこでは、人間と人間が醜くも勇壮にわたりあう、コミュニケーションとしての罵り合いは決して成立しないのです。
今回は柴崎コウ氏の種苗法改正法案をめぐる動き、ドン・キホーテにおける野次馬の変貌、そしてテラスハウスというリアリティー番組がひき起こした痛ましい事件を扱いました。暴走してしまった野次馬としてのおめでたい人間は、決していびつな人間ではなく、どこにでもいる、コミュニケーション不全を起こしただけの人間なのです。しかし、このコミュニケーション不全は、個人の心の性質のためではなく、コミュニケーションを成立させる場としての社会が不全であるために生じています。
これこそ、新しい、SNS時代のコミュニケーションなのだから仕方ない、としても、まるで運命のように素直に受け入れるべきではないでしょう。私は、罵り合い研究家、もしくは文学者を自認する以上、この立場から動くつもりはありません。無知と頑迷さの霧の中で、悲痛さだけを頼りに物事の妥当性を検討するのが、古い文学者の定義であり、仕事だと私は思います。
「それで、文学云々はいいから、結局どうすればいいんだ!?」という追及の声が聞こえてきそうですが、今回はこのあたりでそそくさと撤収し、すべての課題は次回にゆだねたいと思います。読者の皆さんの、すべての山積する不満は、おそらく、次回の私がきっとなんとかしてくれるはずです。