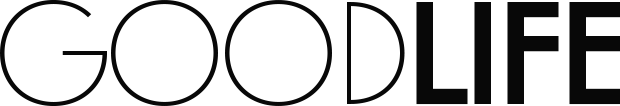グラフィックの華美な装飾の先へ
最近、日本の国産デジタルゲームの世界的躍進が目覚ましい。
昨年最も評価された作品『Sekiro: Shadow Dies Twice』や『デス・ストランディング』にはじまり、今の新型コロナ禍による外出禁止もあってか『あつまれ どうぶつの森』や『バイオハザード RE3』、そして『ファイナルファンタジー7 リメイク』(以下、『FF7R』と略記)の情報を海外のゲームメディアが日夜熱心に発信している印象を受ける。
特に『FF7R』はメディアからもユーザーからも大絶賛の嵐で、1997年発売のオリジナル作品を最高とみなす無印原理主義者を除けば否定的な声を探すことすら難しく、今年のGOTY最有力候補であることは間違いないだろう。
とはいえ、日本文壇の芥川賞やアメリカ映画界のアカデミー賞などと同じように、権威ある賞や多数のユーザーからの支持がその作品の傑出を保証してくれるわけではない――その権威を信じ、コミュニティの雰囲気に同調するなら別だけども。
『FF7R』はたしかに素晴らしさを感じさせる非常に説得力の高い作品だ。
しかし、その説得力の仕掛けにほだされずに解体してみると、当然ながら本作にもきちんと分析的に腑分けすべき良し悪しがハッキリと観えてくる。
ドレスアップした覚醒エアリスにガチ恋してしまう気持ちは嫌というほどわかるが、デジタルゲー厶を評価しようという気運が世界的に高まっているからといって本作を手放しに絶賛してしまうのは批評家の恥だろう。

『FF7R』は “RPG” なのだろうか?
ジャンルという概念上のもので実際の作品を裁断することはその本当の良さをとかく見失わせがちだが、批評の補助線としてはまずこの素朴な疑問からはじめるのが適当なように思う。
というのも、過剰評価とはその作品や人物しか観えていないから維持されるのであって、評価の見直しにはより大きな文脈に置き直し、ほかの作品なり人物なりと比較する作業が必要だからだ。
さて、RPGを問うにはまずテーブルトップのRPGと欧米圏のCRPG文化を歴史的に考えないといけないが、記事の紙幅からも僕の教養からもそれが今できるとは思えないので、さしあたり、RPGの原則は “選択と結果” だと指摘するに留めたい。
つまり、何者かを創り、演じ、興じることは、見方を変えれば別様にありえた無数の何者か=キャラクター像を捨てることであり、さまざまな会話の応答、人間関係の移り変わり、彼ら彼女らが辿る物語の結末を責任とともに引き受けるということだ。
換言すれば、主人公らが自由に何でもこなせることはありえず、自分が選ばなかった会話選択のやりとりも行動の結果もストーリーの結末も、同じ物語のうえではただひとつしか経験できない。
たとえば、昨年彗星の如くあらわれたエストニアの ZA/UM が開発した『ディスコ・エリジウム』は、いわゆる取り返しのつかない要素として、初期ステータス値や成長ポイントの割り振りはもちろん、独自システムの思想キャビネットに探索中で得た多種多様な「思い付き」を定着させることで、一定時間後に初めてわかるバフ・デバフ効果を半永続的に付けられる仕組みだ。
当然、割り振り可能なポイントもキャビネットの数も厳しく制限されているので前述のように「何でもこなせる主人公」は作れず、苦手なタイプのスキルチェックには成功率僅か数パーセントという絶望的な挑戦をしないといけない。
また、ストーリーとしては共産主義革命の成功と敗退を経験した Ravacol という歴史的に複雑な街で、主人公がどういう政治思想の持ち主として振舞うかはプレイヤーの選択に委ねられている。
『FF7R』のようなメインストリーム向けの超大作とニッチな需要を満たすインディー作品との比較がフェアでないとしたら、一昨年の最高傑作『レッド・デッド・リデンプション2』(以下、『RDR2』と略記)はどうだろう?
たしかに『RDR2』もまた、『FF7R』と同様にステータス値の割り振りや成長要素、会話選択、シナリオの分岐などの選択の自由度に乏しく、RPGというよりは西部劇シミュレーターで、実際にある有名な業界人からゲームの特質でもあるメディアの双方向性に劣ると批判を受けたりもした。
しかし、本作には名誉レベルというシステムがあり、特定のクエスト中の行動や街なかでの立ち振る舞いに応じてお店での待遇などが変わるだけでなく、エンディングの分岐にも関わるとされている。
名誉レベルをあえて極端に下げる悪人プレイのメリットがあまりに薄過ぎ、インセンティブのバランスの悪さからロールプレイの自由度はないにひとしいが、それでも『FF7R』とは違い、プレイヤーの選択的行動にはかならず然るべき結果が憑きまとうゲームデザインだといえそうだ。

via. FF7リメイクのジェシーかわいいンゴねぇ
RPGの選択と結果の原則から『FF7R』を振り返ると、今の時代の技術で制作されたものとしては物語上の選択の自由度があきらかに少なく、会話の選択肢もオリジナルの無印作品から増えるどころか減らされていることに気付く。
本作のシナリオの分岐は僕が知る限り、ウォールマーケットにおけるティファ、エアリス、クラウドのドレスアップと、ティファとエアリスの好感度の違いによる3種類の印象的なカットシーンの2つだけ。
それも、コンパニオンからの好感度といってもゲームシステムと呼べるほどのものではなく、何でも屋としてのサブクエストをちゃんとこなしたかとか、2、3箇所の会話と行動選択でより相手に好ましいものを選んだかとかその程度に過ぎない。
興味深いのは、本作の分岐が概ねヒロインに関わっていることだろう。
発売当初からネットで “ギャルゲー” と親しまれて(?)きたように、たしかに本作のヒロインたち、対人関係スキルをメキメキと高めていくクラウドも含めるが、男性なら瞬殺もののルックスでありながら健気なティファも、愛嬌のある振舞いでドレス次第では覚醒するエアリスも、思わせぶりな素振りで気丈にお姐さん風を吹かせるジェシーもたしかに可愛い。
すごく可愛い。
なにより、POV視点でティファと部屋で「休憩」したりドレスアップしたエアリスが打ち上げ花火とともに主人公=プレイヤーの前に現れたりと、ヒロインの可愛さをあからさまに強調する演出が随所に盛り込まれているのが本作の特徴だ。
しかし、彼女たちの過剰な可愛さをいったん括弧に入れることで観えてくるのは、物語としては実に単線的で起伏のないメインストーリーと申し訳程度に追加された冴えないサイドクエストではないだろうか。
実際、クラウドをめぐる頼みの正妻争奪戦も彼女たちの可愛さを無視すれば、自称ソルジャー1stの強さと美少年的ルックスだけで無愛想ながらも出会ったばかりの美女たちがいともたやすく堕ちる小中学生的恋愛観を見せ付けられて正直辛いというか、いい歳した大人の恋愛模様としてはディテール=説得力に欠ける。
また、オリジナルの無印作品との大きな違いとしてはフィーラーと呼ばれる運命の番人の登場が挙げられるが、彼らの存在により『FF7R』が既存の作品で描かれたストーリーライン=運命に打ち克っていく話だと明示的に語られるのはあくまで本篇最終部。
プレイヤーの多くが物語の大筋を知っているからこそいかにそこから面白く逸脱し、超克するかが主眼となるはずなのに、リメイク版の物語上のオリジナリティが40時間前後のプレイの末に垣間見で終わるのは何をどう足掻いてもやはり発売前から懸念されていたプロローグ感が否めない。
要するに、フルプライス作品の物語とゲームシステムとしてはあまりにヒロインたちの可愛さに依存し、甘え過ぎた出来になっているのだ。
『FF7R』への称賛の言葉として頻りに挙げられるのはその映像美だ。
残念ながら僕はここにも疑問を覚える。
たとえば、多くのひとが眼にしたであろう本作のオープニングシーンは高精細な美麗グラフィックでエアリスの美しさやミッドガルの街並みを緻密に描いてはいるが、その後のアバランチの潜入場面を観ると、ジェシーが警備兵に飛び蹴りを喰らわせ、ウェッジが機関車から飛び降り、クラウドが高らかに飛び込んでくるなど動きのあるシーンでは人物の重さとそのエネルギーが軽視されていることが眼に付いてしまう。
高精細な映像で緻密に描くことは技術や物量の問題だが、アクションシーンなどで人や物に然るべき重さがあることを前提に描くことは芸術表現の問題だ。
23年前の無印作品の3Dポリゴンと比べればたしかに驚くべき進化であり、と同時に、今のAAA級作品を知っている人間からすると当然の進化といえるけども、映像表現の観点からみると正直子ども騙しの印象が拭えない。
また、カットシーンに留まらず、本編のプレイ画面でも実に高精細なグラフィックで街や道を緻密に描いているが、おそらくはその犠牲になったのがレベルデザインだ。
ウォールマーケットといくつかのダンジョンを除けばスラム街も含めてほとんどのマップが単調な1本道の組み合わせとして設計され、目的地に向かって走っているだけでも気が滅入り、前述の『RDR2』はもちろんのこと、『ホライゾン・ゼロ・ドーン』や『デス・ストランディング』、『龍が如く7』のような美麗グラフィックと細部にこだわった設計だからこそ得られるマップ探索の悦びは無いに等しい。
本作と同じように、グラフィックの美しさとヒロインの可愛さに重きをおいた(?)ストーリードリブンのAAA級作品で思い浮かぶのは2019年の秀作『メトロ・エクソダス』だ。
かならずしも正当な評価を得ているとは言い難いが、物語重視のシンプルな1本道シューターというメトロシリーズの旧来の作風からセミオープンワールドに舵を切り、ロケーションの少なさが気に懸かるものの、前述の『RDR2』とはまた違った意味でデジタルゲームにおける今日の映像表現の到達点を示した出来だった。
それは、以下に挙げるオープニングムービーからシームレスに繋がるプレイシーンを観ればわかるひとにはわかるだろう、『FF7R』のような派手さと華美な緻密さはないが、この作品の映像表現には物質の重さと現実の悲惨さが反映されていることを。
とはいえ、本作品に誉めるべきものが全くないかというとそれも違う。
『FF7R』のコンバットは、ガードの入力反応が悪いせいでパリィが発動させにくいという致命的な問題があるものの、アクション要素の爽快感とコマンドバトルの戦術性をうまく組みあわせたRTwP(ポーズ機能を備えたリアルタイム戦闘)的楽しさがあり評価できる。
ちなみに、僕の好みは物理攻撃に極振りしたティファを軸にATBをガンガン貯めて消費していくスタイルだ。
ボス敵も相応の強さをもちながらも弱点が明確で、カジュアルゲームを前提にすればきちんと考えて立ち回ると無理なく倒せる相手ばかりなので良い調整具合といえる。
また、本作の成長要素はキャラクター単位ではなく、武器とマテリアル単位でおこなわれるのも特徴だろう。
つまり、各キャラクター毎に魔法特化に育てやすい武器やクリティカル特化に育てやすい武器などがあり、その強化ポイントはレベルアップに応じて全武器に貰えるため武器の着脱だけでキャラクタービルドをいつでも気軽に切り替えられる。
また、本作ではRPG特有のパーティー編成がなく、クラウド、エアリス、ティファ、バレットのうち少なくとも1人は何らかの事情でパーティーにいない態勢が続くため、いかに有能なマテリアルを継続的に育てあげ、プレイアブルキャラクターの交代時に適宜マテリアルを組み直してその都度パーティーの役割を決め直すかが大事になる。
たとえば、僕の場合はティファを物理攻撃とアイテム支援に、エアリスはアビリティの魔法陣が強いため魔法攻撃に極振りさせるのを固定としたため、クラウドとバレットはその都度の組みあわせに応じてサポート的な役割を担わせた。
まあ、戦闘メンバーが指定されているコロシアムなど、キャラクター変更が頻繁に起こるコンバットの連続ではこのマテリアルの付け替えが煩わしく感じられるものの、先述のRPGの原則である “選択と結果” を鑑みれば、1度に限られた数のマテリアルしか育てられないという厳しい制約を課しながらも、キャラクター毎のビルドとパーティー内の役割はいつでも自由に組み替え可能というカジュアルさをとりいれており高く評価できる。
そのため、メインストリームのセールスを狙った大作ゲームに必須なバランスの良さを、本作のコンバット周りではきちんと備えているといえるはずだ。

ゲーム批評を僕が書くときは日本語と英語でほかの感想やレビューを多少とも読んで下調べをするのだが、なんというか、今回は奇妙なまでに役に立たないものがほとんどだった。
冒頭で述べたように大規模な蟄居生活が世界的に続いているのもあるだろうが、過剰演出ともいえるヒロインの可愛さによるくすぐりと、ビジュアルの表面的な作り込みの緻密さが醸す装飾的な完成度に多くのプレイヤーが見惚れてしまい、客観的な比較を通した批評なりレビューなりができなくなっていたのだろう。
もっとも以前書いたように日本のゲーム批評にどこまで中身があるかは疑問にせよ、英語圏の批評も大概なことは残念でならない。
ちなみに『FF7R』の続編制作はすでに着手されているらしい。
新作発売ははやくても2、3年後と考えると、シリーズ完結は10年先というのもなかなか笑えない冗談に聞こえてくる――どの程度のプレイヤーがそこまで残っているかはやや見物ではあるけども。
2016年の『ファイナルファンタジー XV』が主に物語の面で批判が集中し、おそらくはその反省を活かした本作が商業的に大成功したことを踏まえると、ヒロインの可愛さに依存した美麗グラフィックという本作のテイストは今後も引き継がれるだろう。
僕が願うのはせめて、今回の第1作のデータを引き継ぎ可能にし、プレイヤーのさまざまな選択を反映したマルチストーリーを導入することだけだ。
運命の束縛に打ち克つことを物語の根幹に据えた本シリーズでもまた覚醒エアリスがあっけなく殺されるとなると、正直僕は今度のエアリス・ロスに耐えられそうにない。
逆にいえば、ヒロイン依存のこんな作品を作っておいて彼女を無惨に葬るのであれば、スクエニもたいしたものだと感心するけども。