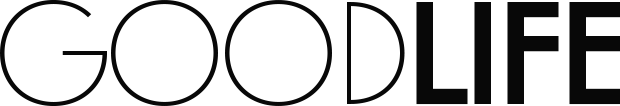グーグルに買収された注目企業の実力は?
デジタルゲームの世界を追い続けるのはなかなか骨が折れる。
毎月毎週のように新作タイトルがリリースされるなかで様々なジャンルの壁に敬意を払いつつも乗り越えていかなくてはならず、クラシックと呼ばれる金字塔的作品を勉強するのはもちろんのこと、一般的には陽の眼があたっているとは言い難い優れた過去作を掘り返すのも批評家としては必要な作業だろう。
『Cyberpunk 2077』を筆頭に今年も期待の新作ゲームが目白押しだが、日本ではすでに『龍が如く7』という僕的には複雑な評価の優れた大作が1月半ばにリリースされ、欧米圏ではこれとはまた違った意味で評価の難しい良作が先月リリースされた。
Typhoon Studios のSFアクションアドベンチャー『Journey To The Savage Planet』だ。
PS4版の国内販売が5月28日とまだだいぶ先なこともあり日本ではさほど話題になっていないが、欧米圏ではそのクオリティもさることながらこの開発の特殊さからリリース当初からそこそこの注目を浴びていた。
というのも、2017年創業でかつ従業員数30人前後のカナダの新興企業でありながら翌年のゲームアワードで本作の開発を発表し、先月末に公式リリース、つまり、会社を少人数で起こしてから実質3年弱のスマートな開発期間でデビュー作を世に送りだしからだ。
また、2019年には Google が買収し、彼らが今力を入れているクラウドコンピューティングを応用したゲームストリーミングサーヴィス Stadia 傘下に入ることが発表された。
まあ、それもこれも共同創業者のひとり Alex Hutchinson が大手開発の Ubisoft で『Asasin Creed 3』や『Far Cry 4』といった人気シリーズ作品を監督してきたゲーム産業のベテランなのが大きいだろうが、なんにせよ『Journey To The Savage Planet』はたんに実力ある開発が出てきただけでなく、新技術を用いた未来のプラットフォームでどれだけの実力とクリエイティビティのある開発元が画期的な作品を最初に世に問うていくかの試金石でもあるわけだ。

本作は、地球第4位の惑星探査企業キンドレッド・エアロスペース社の新入社員として不時着した未開拓の惑星 “ARーY26” の居住可能性を調べていくというもので、手許のスキャナーで現地の動植物の生態を記録しながらときに利用して道なき道を切り拓き、資源を採集し、3Dプリンターでジェットパックなどの装備をアップデートしながら道中で発見した知的生命体による巨大建造物の謎に迫っていく。
作品の世界観は『The Outer Worlds』や『Boderlands』シリーズに似た洒脱なブラックユーモアやコミカルな暴力表現が指摘されているが、美術家のシンディ・シャーマンやジェフ・クーンズが当時から表現していた1980年代アメリカのバカ陽気な大衆文化のグロテスクなパロディとした方がより正確だろう――最近の高く評価できる類似表現としては The Lonely Islands の “ヴィジュアル・ポエム” が思い浮かぶ。
特に、ゲーム進行上のマイルストーンを踏むたびに会社のCEOマチーン・ツイードから送られてくるうさん臭いビデオレターは映像表現としてもなかなか凝っていて見応えがある。
とはいえ、世界観や物語に深入りするのは批評的には避けた方が良いはずだ。
というのも、本作の物語は惑星探査に目的を与える最低限の役割を果たしてはいるものの、プレイヤーをプロットの妙で惹きつけたり大団円でカタルシスを感じさせたり、あるいは以前批評を書いた『ディスコ・エリジウム』のように明敏な哲学的洞察に裏打ちされたものではなく、あくまでゲームプレイに目的と方向性を与える以上の何かではないからだ。
また、デザインワークも、特に惑星のポップでキャッチーな動植物のクリーチャーデザインは本作をオリジナルのものにしている優れたものだが、それでもやはりプレイングのフレーバーを越えるものではないだろう。
意図的ではない物語を不必要に読み込むことは自分勝手な解釈で過剰評価を招きうるし、開発がさほど力を入れていないポイントに過度な期待を持ちこんで酷評するのはフェアな態度とは言い難い――デジタルゲームのような総合性の高い作品ジャンルではこうしたポイントの見極めが必要だ。
では、本作はどういった観点から批評していくと良いだろうか?

去年の海外メディアからのインタビューで、先述の Hutchinson は本作を「メトロイドヴァニアが『Sabnautica』と出逢い、『Far Cry』と恋に落ちたもの」とクリエイティブディレクターとして比喩的に表現している。
今年の2月20日に国内PS4版の発売を控えた『Sanbautica』は未知の惑星での海洋探査ゲームだが、『Journey To The Savage World』でも未知の動植物相のスキャンという意味ではフレーバーとして継承してはいるものの、飢えや渇き、酸素ボンベといったサバイバル要素のパラメータが存在せず(あれば絶対面白いので追加要素として期待してはいるが)、クラフト要素においても設計図という概念がなかったり素材の種類が少なかったりとあまり面白みがあるものではない。
また、『Far Cry』はジャングルや森林地帯といった野性味のある自然環境を駆けまわるゲリラ系ガンシューティングだが、本作の武器はピストル1丁のみで、ショットガンやアサルトライフルはもちろん、ライトマシンガンなどは見る影もない。
シューターアクションとしては残念ながら多少慣れていれば歯応えを感じるまでもなくクリアできてしまえるはずだ。
要するに、本作では物語もサバイバルもガンシューティングも開発的には無理しない範囲の作り込みに落としこまれており、完成度は高いが革新性はなく、面白味はないが要素としてはストレスなくプレイでるようにデザインされている――スリムな開発期間と体制で作られえたのはそういった削ぎ落としが奏功したのだろう。
したがって、真に注目すべきはメトロイドヴァニアとしての面であり、それぞれの要素にどういった価値の軽重の差を付けるにせよこのジャンルの真骨頂であるレベル=マップデザインは無視できない。

メトロイドヴァニアは、1980、90年代の『メトロイド』シリーズと『悪魔城ドラキュラ』シリーズに特徴付けられるノンリニアなマップ探索をベースとした古典的なゲームジャンルだ。
詳細は1年以上前に制作した『ホロウナイト』の批評動画を観てもらうとして、本作の場合は原生植物を利用してのジャンプ台の設置や壊れやすい壁の爆破、ジェットパックの改良などで4つのバイオームの道を切り拓いていくことにある。
特に、中盤以降は知的生命体が建造した謎のタワーをその外縁に繁茂する植物相を飛び歩いて登攀することが目的なため、ジェットパックとグラップルが大活躍なのだがこれがなかなかありそうでなかった。
目的地に到達するためにはどこにグラップルの掴みを作れば良いのかというパズル要素と、1人称視点での多段ジェットブースター付きジャンプアクションがうまく絡みあっており、難易度がけっして高いものではないが絶妙な爽快感を演出している。
接地直前にブーストすることで落下ダメージを無効化できるため、高いところから見下ろして未探索のレアアイテムがありそうな場所に飛び降りる荒業もできる――それもこれもあらゆる立体的な動線を想定した無駄のないレベルデザインの成果だ。
昨年末に話題を呼んだ小島秀夫監督の『DEATH STRANDING』は、地形の微妙なテクスチャーの差がプレイヤーの歩行バランスに細かな影響を与えるという意味では画期的なレベルデザインだったが、マップ探索という点では何らかの意味での移動に価値付与した作品にも関わらず、すみずみまで歩く執着的な探索プレイヤーにとってはそのロケーションと報酬の少なさから物足りなさが残るものだった。
もちろん『Journey To The Savage World』は革新的な何かを成したわけではない。
しかし、メトロイドヴァニアの核にあるノンリニアで自由と制限がうまく配合された伝統的なレベルデザインを見事に作りあげ、その立体構造を巧く活かしたジャンプアクションとストリーラインによる無理のない動機付けは “シブい” といわざるをえない優れた出来栄えだ。
正直にいって、マップにスポーンしたらまず背後に隠されたルートやアイテムが落ちてないかかならず調べる探索厨的プレイヤーにしかわからないだろうが、上下左右を常に見渡して “無理をすれば行けそうな場所” を探す必要のある本作は想像以上に良い意味で神経を使わされた。

したがって、本作はそのキュートでキャッチーな極彩色のクリーチャーデザインとは裏腹にけっして万人向けではないが、マップの隅々までほっつき歩いてインタラクションできそうな場所や希少アイテムを執着的に探しながらでないと前に進めないタイプのプレイヤーにとってはひじょうに面白く愉しめる。
もちろん、サバイバル要素を盛り込んだり、クラフトシステムの複雑化やコンバットの調整、ピストルのカスタマイズやアップデートをよりコミカルでユニークなものにすることなど、この開発なら出来たはずだが削ぎ落した要素はあまりに多く、野心的な作品とはお世辞にもいえないが、そのぶん完成度も高く、注力先の取捨選択が正確だったためこぶりながらもうまく纏まった佳作であることは疑いえない。
Typhoon Studios がグーグルのバックアップを受けることで今度はより挑戦的で革新的な作品を世に送りだせるだろうか?
それはまだわからないが、今後も注目する価値のある実力派のディベロッパーであり、本作がその力量の高さを証するに足る優れた作品であることは間違いない。