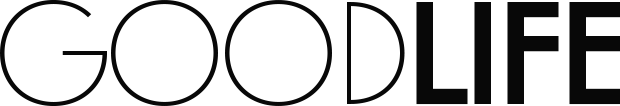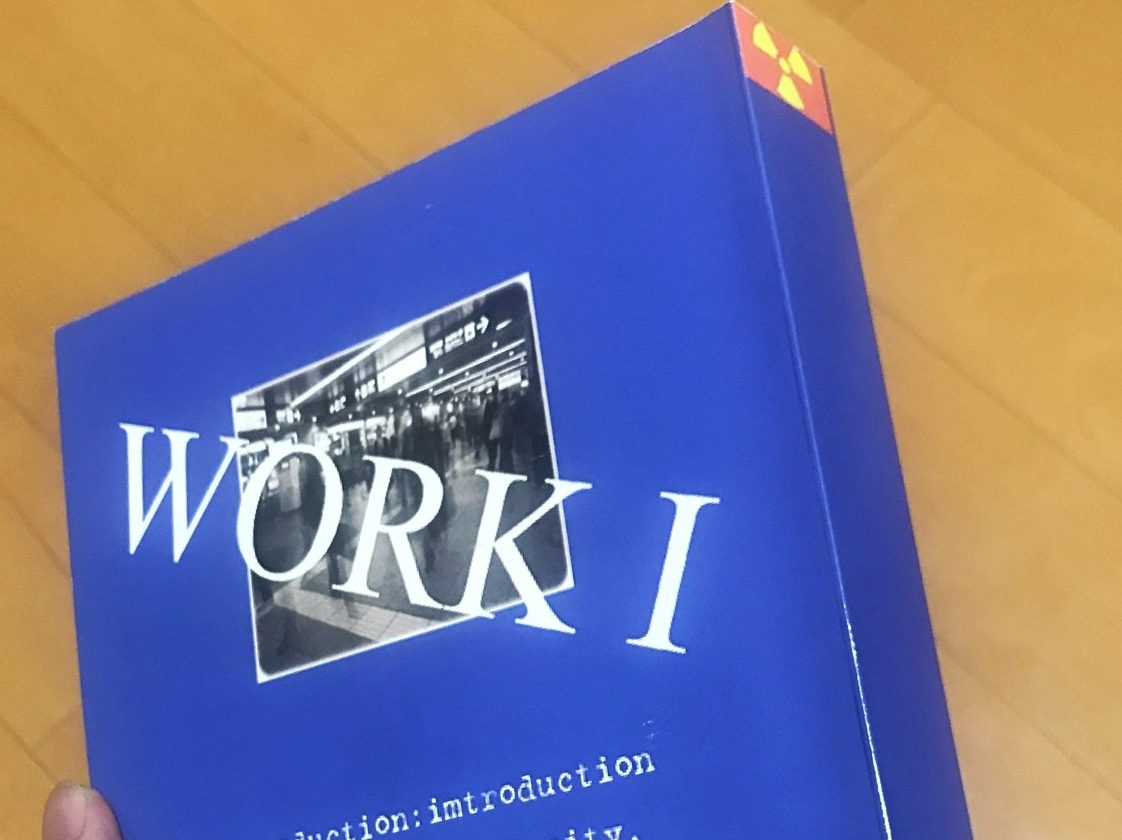ピルストさんが昨年の文学フリマ東京で制作・販売した文芸雑誌『WORK1』の批評を書きます。
定価0円の着払いで通販されているので気になった方は Twitter アカウントにコンタクトをとってみてはいかがでしょうか?
- 問答無用、斬捨御免。
- 原則、冒頭から読めた部分までしか読みません、時間は有限なので。
- 以下の批評は、羊谷知嘉個人の責任でおこなうものです。
- 反論歓迎。
- 批評をご希望の方はご依頼ください、批評記事のRTと引き換えに承ります。
- ジャンル不問。
ついに、文芸雑誌「WORK」が創刊されました。それはひとえに、私の声かけに応じて集まってくれた専業ではない、いわば「働く」小説家たちによる、激甚なる努力のたまものです。毎日の仕事に追われながら、やっとの思いで捻出した、大切なプライベートの時間を、しりとりゲームに次いで不毛な執筆という行為にあててくれたおかげで、今こうして文芸雑誌「WORK」は、世に問うことが出来ているのです。
via. ピルスト「巻頭(虚)言」
文学への屈折に満ち満ちた巻頭(虚)言からはじまるピルストの個人誌『WORK 1』は、出版社中心の日本の文学界への批判意識に支えられたパロディ文芸誌の体裁をとる創作同人誌だ。
ピルストの「文学」をおちょくるユーモアの姿勢は、僕の記憶にある限りではたとえば中原昌也のナンセンスに帰そうとする態度よりも愛と造詣を感じさせ、下半身ネタやグロテスクな表象の挿入で「文学」を悪趣味に貶めるというよりはカフカのような不条理文学への愛着が基底にあるのがわかるので好感がもてる。
クスリと笑える箇所も少なくなく、その主張には同意できるところが多い。
たとえば、「文学の未来」と題されたミュータント味なしと剣剣波による対談は方法的には対話劇として読むべきで、作者のピルストの思想と同一視すべきではないけども、プロアマ問わず(架空ながらも)作家の対談としてはとても鋭い知見に富んでおり、啓発的で、短いながらもなかなかに読み応えがあり面白い。
「巻頭(虚)言」とあわせてこの2篇だけでも十分にお金を払って読む価値がある。
「評価できるものは存在し、評価できないものは存在しない。もっと言うと、評価可能な内容はどんどん洗練され、『優れた』ものになる一方、評価不可能な、例えば形式に関する方法、これも広い意味での内容ですが、このようなものは『優れていない』ものとして、誰も書こうとしないわけです」
— 凍結の批評者、羊谷知嘉 (@ChikaHitujiya) January 10, 2020
「評価不可能な理由は、それがメタ的だからというのではなく、単に新人賞という方法にそぐわない、または既存の出版方式に対立する場合が多い、という理由によるのです」
— 凍結の批評者、羊谷知嘉 (@ChikaHitujiya) January 10, 2020
「評価不可能な小説は、すでに存在しているんです。ただ、評価方法がないという理由で、存在していないものとして扱われてしまっている。そのような状況が現在、もしかしたら僕たちを取り巻いているのかもしれません」
— 凍結の批評者、羊谷知嘉 (@ChikaHitujiya) January 10, 2020
とはいえ、コンセプトの徹底に詰めの甘さがあるのは否めず、本作が文芸誌パロディの独演とわかるのはあくまで冒頭の「巻頭(虚)言」を最後まで読んだうえでの話で、紙本としてのデザインのレベルから文芸誌を模していることが示唆されていないのは作品としても商品としてももったいないといわざるをえない。
たとえば、講談社の「群像」や新潮社の「新潮」を模した表紙デザインであれば少なくとも商品としてはもっとキャッチーだったはずで、既存のものに素材を採りつつもその参照関係を示唆しながらいわゆるパクリに堕しない表紙をどう作るかはデザインワークとしてはるかに挑戦的な課題になったはずだ。
また、綿山りさとか、島田雅太郎とか、堀田敏幸などのように人気作家のゲスト寄稿という体で作品単位でのパスティーシュがあればより笑えただろう。
ひとりの人間が創作、対談、評論、ブックデザインまでこなして400頁超の文芸雑誌をものす熱量の高さを褒め称えるのはやぶさかではないが、ピルストの「巻頭(嘘)言」からうかがえる強い批判意識と作品コンセプトを考たらひょっとすると志を同じくする面々を集めてより深く掘りさげかつ多様なアイデアを盛り込んで次作に挑んだ方がより面白くなって良いかもしれない。
もちろんそれは、大手出版社による文芸誌カルチャーに正面から対峙するだけの知性と教養と問題意識が制作者のピルスト自身にあることを伺わせるからにほかならない。
書くことだけはゆずれない。これでお金をもらっているのだから、半端なことは書きたくない。半端な仕事はしたくない。矜持というには大げさかもしれないが、自分の仕事に対するプライドは持っていたい。
via. ピルスト「WORKⅠ」 「どけ、おどけ」
『WORKⅠ』は、すでに採りあげた「巻頭(虚)言」と「文学の未来」と題した架空対談を除けば6篇の創作と3篇の書評、そして2篇のエッセイから構成されている。
小説家としてのピルストを批評するために全篇を冒頭読みしてサンプルとして採りあげるのにふさわしいと判断したのが引用の産毛坊主名義の短篇「どけ、おどけ」だ――余談だけどもサンプルの選定は批評的にはむずかしい問題をはらんでいて、何事でもいちばん良く出来ているものを選ぶようにしていることは以前パン屋批評を例にして書いている。
まず、この書き手の言葉の使い方からしてピルストが哲学思想系のバックグラウンドを備えた作家であることは疑いえない。
たとえば、
記者という仕事を続ける上で大事なのは、日々生じる不毛な事件や事故に、感情移入しすぎないことだ。……この仕事は、自分自身を一旦、括弧に入れて物事に接するという技術が必要なのだ。
via. ピルスト「WORKⅠ」 「どけ、おどけ」
とあるが、「括弧に入れて」という言い回しは通常の慣用表現ではなく現象学的還元という20世紀哲学の基本概念でのみ使われるものだ。
そのせいかはわからないが、作家としてのピルストはプロットや世界観、魅力的なキャラクター造形よりも、地の文の箴言的な煌めきと現実世界へのアイロニカルな参照が持ち味という内省的傾向が強い書き手で、そこに、ピルストの解像度の高い認識力からくるグロテスクに誇張された言語表現のおかしさがフレーバー的に加えられている。
注目すべきはそのグロテスク表現だ。
通常、この手の表現は作り手の低俗趣味による場合が多いのだが、ピルストの場合はたんに世のなかの無視できない悲惨ないし無残な現実を深く細かく言葉にしているだけなので作品の品格を不用意に貶めることがない。
当然、世間と社会は世の現実の悲惨と無残に無視を決めこむことで成立し、大多数のひとは物事の表面をさするようなイメージの薄さのなかで生きているのでピルストの認識の深さは文字通りの意味で才能の塊といっていいだろう――情報量の多い文章がなぜ良いといえるかは以前触れたとおり。
「(中略)どうやって、顔を潰しますか、地面に寝かせて、みんなで顔を踏みますか。うん、うつ伏せにさせて、みんなで順番に頭を踏んでいくんです。そうすればアスファルトが顔面をぺちゃんこにしてくれるはずです。鼻の骨が折れて皮膚を突き破ってくるくらいまでやらないと、この女には分からないでしょうね。何回も何回も、アスファルトにキスをするんです。唇もぐちゃぐちゃで、肉がむき出しになると思います。最高だな、この変態女の汚い唇に誘惑されたかわいそうな男たちのために、そう、私たちは期待されていますね?」
via. ピルスト「WORKⅠ」 「どけ、おどけ」
ちなみに、作家の特質という意味では袴輔介名義の短篇「猟的死数」にこそ顕著にあらわれているが、僕はこの作品を高く評価するものの良い意味でも悪い意味でも玄人好みというか物語としてのおもしろみが薄いため今日の作品としてはバランス面に弱さがある。
その点、女性の新米記者を語り手にした「どけ、おどけ」はピルストの持ち味がやや薄くはなるものの物語の骨が一応はあるので一般ウケもある程度は狙いやすいかもしれない。
僕の眼からすると、クリエイターとしてのピルストは大きな才能の原石に映る。
そのマイナスを挙げるならやはり小説としての完成度がやや劣るのと、「巻頭(虚)言」で語られたほどには、また、「巻頭(虚)言」を書きえたものとしては小説自体がまだ前世紀的な意味でシリアス過ぎるため未だ旧来の枠組みに囚われており、おそらくは既存の文学の外にいる潜在的読者までには訴求してゆかないことだろう。
ブンゲイファイトクラブの炎上の渦中で繰り返し主張したことだが、実質無料に限りなく近いコストの娯楽コンテンツがいたるところに溢れかえった今日では文学も例外なくSNSや YouTube 動画、ゲーム実況配信などとの時間の奪いあいを強いられているわけで、質的にいえばあれらのごった煮感やカットアップ同然の性急なスピード感がなければまともに立ち向かうことなどできないだはずだ。
もちろん、世の現実を拒否し、文学の枠内に留まって固定客のみを相手にしつづけることもまたひとつの選択ではあるが、ジャンルが骨董化していくなかで創造的なものが生まれえるはずもなく、そもそも「文学的」という表現を「湿りきってとうとう腐り、異臭すら放ち始めている」と形容するピルストがその壁のなかの安寧に留まることはもとめているとは僕には到底思えない。
とはいえ、究極的にはピルスト自身がだれの何の作品を尊敬し、どんな歴史を超克したいと欲望するかがすべてだ。
この書き手であれば20世紀的生真面目さから脱し、もっと笑えるものを、もっと楽しいものを、世間に無視されている現実の悲惨と無残を今日の明るさのなかで書いて創作の最前線にたつことを期待せずにはいられない。
たとえまだ磨かれざる原石だとしてもピルストにはそれだけの強大な才能をもっていることは疑いえない――『WORKⅠ』がたんにこの作家の才能を示すだけでなく、あらたな創作の課題と人脈の礎として次のサイクルに導くことを心から願う。