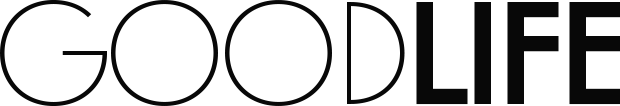男性の弱さに訴求する反ポリコレ映画
トッド・フィリップス監督の驚異の話題作『JOKER』は実に奇妙な作品だ。
カンヌでは最高賞の金獅子賞、トロントでは主演のホアキン・フェニックスが新設の功労賞TIFFを受賞という華々しいスタートを切りながら、アメリカ本国では数多くの厳しい批判にも晒されている賛否両論の本作は、2019年内では今のところ7番目に興行収入が高いヒット作で、R指定作品としては史上最も成功しているが、その内容は普通のいい方をすれば大人向けの社会派映画だ。
2度の鑑賞で僕が見掛けた下校途中の高校生グループや大学生カップルが気持ち良く帰れる作品ではないにも関わらず――この話題性は何だろう?
そしてなにより、直接的でない対象の撮りかたや構図、光の使い方、ポストプロダクションの色調補正などからこの映像作りはあきらかに「アート」をわかっている優れた者の手によるが、プリプロダクションに問題があるであろう映像のテンポの悪さやご都合主義ともいえる脚本の杜撰さはとてもじゃないが褒められたものではない。
あらかじめいうと、トッド・フィリップス監督作としての『JOKER』には僕はかなり否定的で、物語として観た場合には出来が悪く底が浅い上に卑怯だとすら思っている。
なので、ご自身の感想や感動、作品観を大事にしたい方は遠慮なくブラウザバックしてほしい――ひととひとの間に適切な「壁」が求められる時代に自分が嫌いな意見にも無理に眼を通すのはいささかナンセンスだ。
この批評記事は、自分の好き嫌いを超えて作品をより良く理解したり異なる価値観にも公平に耳を傾けたいと思う知的にタフな大人の読者のために書かれている。
主人公ジョーカーへの共感やそれによるカタストロフィックな感動でもってこの作品を称賛する通俗的な価値観はひとまずわきに置いて読み進めてほしい。
準備は良いだろうか?

まず、大前提として『JOKER』は物語として現実をよく描けていない。
フィリップス監督が映画公開前に、アメコミ映画の装いのもとにスタジオ制作の本物の映画を忍び込ませるのが自分らのやり方だと、現実的な予算で本物の映画を作り「fucking Joker」と名付けてやろう、それで出来上がったのがこれさと、実社会への悪影響に懸念を示したインタビュアーに応じたのは有名だが、彼のいう「本物の映画」がこの程度を指すならなんとも情けない話だ。
たとえば、ホアキン・フェニックス扮するジョーカーの心理描写にはこだわっていても彼の置かれている社会のあり様は制作者のご都合主義に大きく簡略化されている。
多少とも眼のあるひとなら、民衆暴動の火が拡がりつつあるゴッサムで政治的に最も重要な新市長候補トーマス・ウェイン出席のイベント警備があまりに雑というか緩過ぎるのにはおもわず吹きだしただろう。
当然、危機管理能力ゼロのウェイン邸には正門付近にさえ守衛のひとりもいないため、ジョーカー覚醒前の怪しい中年男性がのちのバットマンとなる幼いブルースに接触するのは何の造作もないことだった。
本格化する暴動からウェイン夫妻が護衛も付けずに劇場から逃げ出し射殺されるのはもはや当然の報いというべきか。
そもそもをいえば、この作品ではゴッサム・シティの富を独占する富裕層への怒りや暴動の拡がりはすべて新聞やテレビを通して説明され、登場人物らが実際に生きる社会空間として外部的に描かれることはほとんどなく、緊密に結び付いているはずのジョーカーへの覚醒と暴動の拡大もまた制作者の恣意性を匂わせる。
重要なネタバレになるが、本作ではジョーカーへの覚醒を、緊張すると笑いを抑えられなくなる脳障害を抱えた雇われピエロのアーサー・フレックが、世間に虐げられ、同僚の裏切りで馘首され、お気に入りのトーク番組のホストからも笑い者にされ、実の父親からも拒絶され(たと思い)、義理の両親から幼少期に虐待を受けていたことを知る(と思う)なかで、世のなかの嫌な奴を殺すことが自分の求めるもの、すなわち、世間の注目を浴びて暖かく迎えられることを擬似的に得る方法だと気付く過程にあてられている。
だからこそ、アーサーの最初の衝動的な殺人を世間がどう受け容れて彼ら彼女らの潜在的な怒りに火を付けたのかは、それがどのようなかたちであれきわめて重要なのだが、フィリップス監督はこの作品テーマの根幹に尺を割くことはおろか映像の外の出来事としてすら描くことはなかった。
これでは到底「傑作」とは呼べない。

もちろん、ジョーカーに共感してこの作品を賞賛してやまないひとが僕の文章にこう思うことはわかっている――それの何が問題なんだ?すべてはジョーカーの妄想であり作り話なんだから辻褄があわないのは当然じゃないか!
そう、正解だ、きみは正しい。
だからこそ『JOKER』は卑怯といえる、あらかじめ不出来な言い訳を用意しているのだから。
フィリップス監督やフェニックスが映画のプロモーションやインタビューなどで周到にこの作品を定義したり解釈に答えを与えるのを拒んでいることは周知のとおりだが、それは作中でジョーカーの語る倫理観、つまり、コメディとは主観で、何が笑えて何が笑えないかはひとそれぞれが勝手に決めることというニヒルな相対主義に従ったものだ、少なくとも建前としては。
しかし、実際の機能として観た場合、彼らの態度は作中の物語がほぼすべてジョーカーの信頼できない語りであり、究極的にはすべて語り手の妄想に過ぎなかったという単純な解釈をも許容する――というのも、本作最後のシークエンスはアサイラムでジョーカーが看護者の質問に答える場面だからだ。
結果、何がどこまで現実で空想でないか、あるいは恣意的な妄想の語りでないかの線引きを曖昧にし、鑑賞者に多くの謎を残してSNSで語らせるとともに妄想の名のもとで他人からの批判を拒絶する。
『JOKER』の場合、信頼できない語り手というメタ構造の問題を除けば現実と空想の入り乱れる物語のスタイルは、1982年製作のマーティン・スコセッシ監督のカルト的名作『キング・オブ・コメディ』から材を明白に採ってきている。
というのも、精神病院で看護者を殺して脱走を図る物語最後のシーンではまったく同じ画面構成が『キング・オブ・コメディ』からとられているだけでなく、憧れのトーク番組に脳内出演するという設定から元ネタでは主人公のワナビー役を務めたロバート・デ・ニーロを憧れのホスト役にあてるという配役に至るまで――さらに同監督の『タクシードライバー』も含めて――奇妙に思える量のオマージュと愛がスコセッシに捧げられているからだ。
名作と謳われる過去作へのふんだんな言及が最近のオスカーへの近道らしいが、残念ながらその正誤を判定する知識を僕は持ちあわせていない。
もともとスコセッシは本作のプロデューサーに名を連ねていたばかりか、最終的にはメガホンをとったフィリップスからスコセッシ自身が監督するよう個人的に勧められたりもしたようだ。
スコセッシ作品への過剰ともいえる言及が何を意味するか、あるいは何を意図されたのかはわからないが、その堅い忠誠の誓いにうすら寒さを覚えるのは僕だけだろうか?
いずれにせよ、『JOKER』は虚実錯綜した物語を信頼できない語り手に語らせて蓋をするといういかにもな文学的構造を持つがゆえに、物語に一定の解釈をだしたい通俗的な鑑賞者にSNSで語らせるとともに、批判的な批評を書きたいものにはジョーカーのクチから先手を打って黙らせるという実に巧妙なSNS戦略を備えている。
ネットで好意的に語りたいと思わせること以上に効果的なマーケティングはないのだ。

また、本作がその地味な作風とは裏腹にこうも高い話題性と興行収入を叩き出しているのにはもうひとつ理由がある。
不思議に思わなかっただろうか、この作品では女性や有色人種、セクシュアル・マイノリティが肯定的には描かれていないことに。
ここに、日本では絶賛ムードにも関わらずアメリカ本国では激しい賛否両論に分断されている根拠がある。
もう何年も前からアメリカでは多様性に配慮したコンテンツ制作をおこなってきた。
たとえば、先日批評記事を書いた『アウターワールド』では、プレイヤーの仲間となるパールヴァティーという女性エンジニアの恋の相手はジュンレイというアジア系女性で、そのインターレイシャルな同性愛に驚きや違和感の声は微塵もなくさも当然のように物語は進んでいく。
デジタルゲーム繋がりでいえば、通称BFVという第2次世界大戦を舞台にした対人戦シューティングゲームが発売前に女性兵士をフィーチャーしたプロモーションを仕掛け、ファンからは史実に反するとして炎上騒ぎになった。
これらを作り手の「現実」の反映と観るか、ポリティカル・コレクトネスに配慮した結果と観るかは悩ましいが、いずれにせよ下層階級の中年の白人男性が有色人種のキッズ5人から集団暴行にあったりする『JOKER』は、ポリコレへの配慮はおろかその社会常識に真っ向から抗した作品といえる。
実際、日本ではあまり知られていないが、フィリップス監督が映画のプロモーションで社会的正義を過度に重要視する昨今のウォーク文化のせいでコメディが成立しなくなったという主旨の発言をし、案の定というべきか現役のコメディアン側からも批判を浴びて皮肉にも炎上してしまった。
このごろのウォーク・カルチャーの中で、笑いを取ろうとしてみましょうよ。“もはやコメディが成立しないのはなぜか”という記事がいくつか出ていましたが、僕からすると、それは、めちゃくちゃ面白い人たちが“やってられない、誰かを怒らせたいわけじゃないし”という感じになっているから。Twitter で 3,000 万人を相手に議論することは難しいし、そんなことはできない。でしょう? だから“僕もやめよう”と。僕の作るコメディは――すべてのコメディにそういう面はあると思いますが――不謹慎なもの。そこで、どうやってコメディ以外の方法で不謹慎なことをやろうかと考えたんです。
個人的にはホモソーシャルの嫌な匂いがするたいして不謹慎でも挑戦的でもないハングオーバー・シリーズの監督が何を偉そうにと思わなくはないが、彼の発言に共感するひとは日本でも非常に多いだろうし、文芸作品の冒頭批評という僕のスタイルが「命を削って書いた作者を傷つける」という意味不明な理由でプチ炎上した身としてはそのいわんとすることもわからなくはない。
要するに『JOKER』とは、文学的意匠を凝らした男性目線の反ポリコレ映画なのだ。
そのため、本国アメリカでは銃規制が失敗しているのもあって激しい批判を浴びている一方、日本社会がいかに女性に差別的か考えればわかることだがポリコレの厳しさはまだ弱い分、日本の特に twitter 界隈では『JOKER』絶賛ムードが支配的だ。

もちろん、本作のなかにフィリップス監督がいうような「本物」が全くなかったとは思わない。
だれもがクチを揃えるようにフェニックスはヒップホップミュージシャンとしてだけでなくダンサーとしての隠れた才能を遺憾なく発揮し、アイスランドのチェリストであり作曲家のヒルドゥール・グドナドッティルのスコアはその音量の過度な大きさが耳に障るものの劇音楽としてはよかったが、本作の真の白眉は撮影監督のローレンス・シャーによる画面作りにある。
というのも、物語が進むにつれてその脚本の粗が目立つ本作を支えていたのは批評的に観ればシャーの映像表現で、撮影対象をただ漠然と撮るだけでは良しとしない彼の几帳面な画面作りはゆいいつ芸術表現として満足感を覚えるものだった。
実際、2017年にシャーは真の父親探しをする双子の中年男性を主人公に据えたコミカルなロードムービー『ファーザー・フィギュア』で監督デビューを果たし、批評家やレビュアーからは散々な酷評を浴びているものの、長年撮影監督を務めてきたフィリップスのハングオーバー・シリーズにありがち男たちの嫌な悪ノリ感を脱臭し、それでいて父と子の血縁関係の根源的な寄る辺なさをうまくヒューマンコメディのスタイルに昇華している。
『JOKER』のような話題性も反抗精神も見かけ上はない映画だが、コメディという枠内で数多くの禁忌と不安をユーモアに変換した素晴らしい作品だ。
結局、本作で名を挙げたのは疑いなくフェニックスの演技と撮影監督のシャーでありーー本国の批判的な評者でさえこの両者のクリエイションを称えるものは少なくない――短文と極論が好まれるSNSでより正確で公平な『JOKER』評を書きづらい理由がこの「本物」の仕事にある。
おもえば、今作のジョーカーは実に意志が弱い人物だった。
少年たちから集団暴行を受けても抵抗ひとつせず、地下鉄で近くの女性が酔っ払いに絡まれても緊張で笑いの発作を起こすだけ――アパートの同じ階に住む好意をもった女性には声もかけず尾け回し、殺人ですら明確な意図と計画をもって実行したものはおそらく肉親と最後の場面以外はないはずだ。
衝動的で野心がなく計画性もない。
何かを建てることなくただ怒りに身を任せて打ち壊すだけ。
本作がここまで多くの共感を呼び、鑑賞後にSNSで語りたい気持ちにさせたのはひとえに作品解釈を宙吊りにする語りの構造とジョーカーの極端な意志の弱さゆえだろう――弱さは人間を強く魅了する、だれもがより弱いもので自分を慰め、より強いものへの鬱憤を晴らしたいからだ。
特に男性というか哺乳類のオスにとって社会集団内の序列は遺伝子レベルから死活問題なため、ムダに見栄っ張りでプライドが高く、かといってだれかがポリコレ的な暴論を張ってでも守ってくれる庇護対象ではないが故にたえず自分の弱さと向き合わされ孤独に対処することを強いられる。
『JOKER』はいうなればその弱さという男性的な心の澱に悪の笑顔ですり寄り負の感情の解放を誘いかける。
僕の作品評価はすでに書いたとおりだが、娯楽作品としての社会的機能を考えた場合に『JOKER』という社会現象が突きつけるのは今の男性が追い詰められている弱さと孤独の袋小路だろう。
答えがだせないよう意図された解釈論争に淫するのも作品を絶賛するのも、あるいはポリコレ的観点から懸念を表明するのも大いに結構。
だが、本作を観たあとに本当の意味でオープンに語るべきは自分の弱さとその孤独な向き合い方かもしれない――ひとりでも多くの現実に生きるアーサーを救済するために。