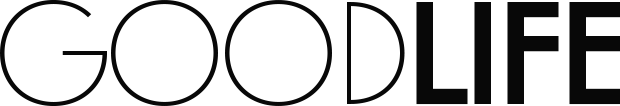Magic: The Gathering が世界中の現存するゲームのなかでもっとも複雑で、おそらくは唯一必勝法が計算不可能なものと科学的に認められたらしい。
ゲーム理論とコンピューター科学の専門知識を前提としたその紹介記事は僕の手に余る内容だったが、カードプールこそ膨大とはいえその数が限られているものの、盤面の広さや操作可能な駒数など、チェスや将棋、囲碁などと比べたらたしかにMTGは物理的制約が少ない。
後発の作品、たとえばデジタル・カードゲームのハースストーンと比べても、デッキ枚数やライフ、呪文のリソースとなるマナなど、マジックにルールとして設けられている上限の種類はやはり少なく、ターン毎の蓋然性も高いため、コンピューターが得意なブルートフォースアタックはその必勝法を探るにはあまり効かなそうだ。
ひょっとしたら、スパコンや人工知能の発展の度合いを示す指標として、あるいは人間がその頭脳を誇る最後の牙城としていずれマジックが研究者らから見出される日が来るかもしれない。
人工知能が考えた現環境最強のデッキを観てみたいプレイヤーは僕だけではないだろう。
とはいえ、マジックの魅力はそうしたマインド・スポーツの面だけに限らない――僕が紹介するのはもちろんその文学性だ。

マジックのフレーバーテキストとその世界観の面白さを各単色カードの紹介も兼ねて以前の記事では書いた。
白青黒赤緑の基本5色とそれらを組み合わせた10の多色がマジックの中心にあるが、今の環境がフィーチャーしているラヴニカという次元では――そう、マジックの世界観は多元空間論を採用し、物語の鍵となる者たちはさまざまな次元を自由に行き来する能力をもつ――固有の色の組み合わせをもった10のギルドが陰謀術策の渦巻くなか広大な都市を統治している。
今回の記事ではこのうちの3つのギルドと、ウェブで無料公開されているラヴニカの短篇小説を独断と偏見で紹介しよう。
Nicky Drayden というアフリカ系米国人のまだ若い作家による10篇の掌編は、娯楽作品という骨組みを守りながらも実に芸術性のある読み応えを成している――芸術性の厳密な定義はここではしないが、翻訳作品の批評の是非については過去の記事を参照してほしい。
というのも、不自然なまでに物事のディテールに触れるその筆致だけでなく、各物語の主人公はそれぞれのギルドの末端構成員がほとんどで、英雄的でありながらもどこか欠陥や宿痾を引きずる彼ら彼女らの目線で語られる物語は、読者を気持ちよくするというエンターテイメントの至上目的ではなく、ギルド内やギルド間で横行する構造的差別という普遍的な問題を映しているからだ。
とはいえ、百聞は一見に如かず――あとはあなたに判断してもらおう。

1.ゴルガリ
黒緑の組みあわせのゴルガリは、生と死は円環するという理念をもつギルドで、世界観的にはゴミ漁りから死体処理、社会の底辺に置かれた弱者への食糧供給をするなど、ラヴニカ社会の底の方のインフラを担っている。
ゲーム的には黒の除去・蘇生能力と緑のカードドロー・マナクリエイト能力という相性の良い組み合わせで、今も流行りの強デッキの一角を担っている。
余談だが、ゴルガリの現ギルドマスターであるゴルゴンのヴラスカは僕が「陰キャ界の聖人」と呼ぶほどの傑物で、頭から蛇がはえた奇怪な容姿から広く差別され(美しいのに)、その危険な石化能力からギルド内でも使い勝手の良い鉄砲玉程度にしか扱われていなかったが、悲惨な過去を背負った彼女がギルドマスターに登るための冒険を描いたイクサラン次元での恋と友情の物語は涙なしでは読めない代物だ。
今回紹介するゴルガリの物語の主人公はクロールと呼ばれる屍術に長けた昆虫種族の若者だ。
高位の屍術使いの新しい弟子になる登用試験に彼は挑戦するのだが、被差別種族であるクロールの彼はその命を賭した試験で無事栄光を掴みとれるのだろうか――そしてその先にあるギルドの現実とは?
冒頭を引用しよう。
私は多孔質の土に杖を押し込み、身構えながら鳥の巣茸の繊細な上向き傘を調べた――今季、ゴルガリのシャーマンが最も切望する茸。これを栽培できるに至ったのは三つの腐敗農場だけ、そして私達が最初だった。最も見栄えのしないものでも一本あたり一ジノの値がつく。この一本は印象的な黄金から青銅の色調を誇り、卵に似たその内に薄青緑色の球体を幾つも抱えている。だがこれは地底街で身に纏われる精巧なガウンを飾る運命にはない。この茸は私のものだ。
via. 死、その尊き瞬間

2.セレズニア議事会
白と緑の組みあわせのセレズニアは、厳格なまでに共同体内の平和と平等を信奉する集団で、ゲーム的には少ないコストで小粒クリーチャーを盤面に展開したり敵を拘束したりするのに長ける嫌らしい(?)連中だ。
マジックの世界観の良いところは単純な勧善懲悪に堕ちないことだろう。
善性を象徴する白色混じりの各ギルドは、青白のアゾリウス評議会は法の作成、赤白のボロス軍は法の執行、オルゾフ組は敬虔な信徒の集まりといわば社会的に正しい側に立っているようにみえるが、それぞれに腐敗と欠陥が蔓延っていることをマジックは隠そうとしない。
一見理想郷的な共同体にみえるセレズニアだが、彼らの場合には極端なまでに個の感情表現すらも抑圧することを義務付ける宗教的な全体主義だ。
冒険小説風のストーリーラインをなぞりながらもこの才能ある作家はセレズニアの不協和音を静かに響かせることを忘れていない。
余談だが、僕は自分が正しいと思い込んでいるひとの顔と佇まいが虫唾が走るほど嫌いなので、マジックでは白は可能な限り使わないように努めている――強いけどね。
冒頭を引用しよう。
「また例の子の所へ行くつもりなの?」 アンブレリンはそう言って、僕の部屋の入口を塞ぐように立った。実際には彼女の部屋だが、この数か月、あの事故以来使わせてくれている。彼女の声は穏やかだが、両目の端には皺が寄り、それは滑らかな皮膚が粗い樹皮へと変化する額に向けて深くなっていた。子供の頃から変わらない、彼女が内心に不満を持つ時の証だった。
via. 束縛と絆

3.グルール族
赤緑の組みあわせのグルールは、文明社会を本能への抑圧の檻とみなして破壊を叫ぶいわゆるヒャッハー集団だ――かつては都市の過度な拡大を憂いて野生動物のために自然の保護を謳うという高邁な思想もあったが、今では失われ、ラヴニカ社会から弾かれたならず者集団に成り下がっているらしい。
ゲーム的には非常に攻撃的で、クリーチャー強化や疑似除去、速攻持ちという脳筋感溢れるプレイングを楽しむことができる――実際には相応に難しいのだが。
今回紹介する小説の主人公は、ヴィーアシーノと呼ばれる人型爬虫類種族の若者で、戦闘能力はきわめて低いながらも腕の良い刺青師だ。
彼はある事件を起こして一族から放り出されるが、放浪の最中、己の内なる真の「怒り」を見出したことで部族のもとへ舞い戻り、あろうことか危険極まりない族長の双頭の巨人にその座を賭けた決闘を申し込む――強烈なる殴打に視界が白く濁ろうとも、肋骨の数本が折れようとも、繰り返し、何度も何度も。
作中冒頭で、監獄から釈放されたばかりの伝説の戦士は主人公にこう語る――憤怒は戦いと破壊の中だけにあるのではない、それは異なる者には異なる方法で語りかける、と。
典型的な成長譚の骨組みをなぞりながらも、社会的に正しい側の悪を、社会的に間違っている側の善をそのいびつな社会構造とともに描きだすことに成功している――そこに宮崎駿風の子どもじみたロマンティシズムはない。
冒頭を引用しよう。
私は枯れ草の中にうずくまり、獲物へと狙いを定めていた。二十フィートも離れていない所に、一体のマーカが空中に鼻を鳴らして威嚇しつつ猫の尾を激しく振り回していた。その獣から安全な風下にいても、動悸は激しかった。マーカに勘付かれたなら、その太く黒い鉤爪でばらばらに引き裂かれてしまうだろう。
via. うたわれぬ憤怒

いかがだっただろうか。
毎日遅くまで図書館に引き籠り、週に何度も古書店を物色していた頃はマジックのようにスリリングで文学的にも満足を与えてくれるものがあるなど思いもしなかった。
素晴らしいものはきっと身近なところにも星の数ほどあるのだろう、僕らがそれらを見つけて認めるだけの心の余裕がないだけで。
マジックだけではないが、そうしたものがこのブログを通して少しでも広まることを願ってやまない。