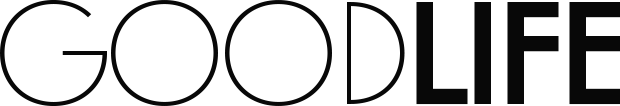狭間の地の遺産
コンテンツの腐敗に抗う
ひとの心を変える作品がある。
胸の熱くなるヒューマンドラマに明日も生き抜く心の糧をもらう、のではなく、コンテンツにもとめる水準を引き上げ、拡張し、ハッキリさせる素晴らしい作品だ。ときにはその出会いが人生を変えることもある。僕の場合はある有名な美術家からもらった塩トマトがそうだった。
『エルデンリング』がある種の共通体験としてゲーマーたちの脳に焼きつくことを想像する。
美味しいものがそうであるように、この作品がゲーマーの舌を飛躍的に肥えさせるかもしれない。従来どおりのものを飽きさせ、フォロワーを生み、その作品を越えることに価値が見出され、つまりは「エルデンリング以前と以後」で考えられるようになるひとつの未来が。
リリースから約1年が経ってもなお有名配信者たちにプレイされ、何百人、何千人もの視聴者を集められるオフラインゲームはそう多くない。控えめにいってもそれは多様な戦術と死に様とスタイルの幅を実現し、プレイの数だけことなる体験を生んでいるからだろう。
この記事では、『エルデンリング』の批評から後世に引き継がれるべき要素を抽出する。それは個人的な推測であり、願望であり、挑発でもある。あえていえば、のちの時代から振り返ったときにあらわれる本作の意義をなかば予見する試みだ。
今の娯楽環境はコンテンツの数にも種類にも困らない、人類史上もっとも遊びがいのある時代だ。ただ浴びているだけで底に溜まり、蕩けあい、忘れられるからこそ、作品の意義を分析的な言葉に変えることにも一定の価値があるだろう。
それは、飽食の時代を支配するコンテンツの腐敗に抗することであり、恵まれた時代のきたるべき破局への身構えかもしれない。本作をプレイしたなら血溜まりと伝言がいかに役立つか(あるいは笑わせてくれるか)は身に沁みているはずだ。
僕の批評もそうなるといい。

万人向けの「濃い」作品
去年のゲームシーンを振り返ると、想定客層の狙いにしっかりと刺さるインディー寄りの作品が大きな話題を呼んだ。『Sifu』や『Stray』、『Cult of the Lamb』、『Marvel Snap 』、『Dark and Darker』がその好例だろう。
一方、メインストリーム向けの AAA 級タイトルでは『God of War Ragnarök』や『Horizon Forbidden West』ぐらいだろうか。多額の費用がマーケティングに消えたにも関わらず、今では DLC の情報以外ではあまり話題にならないことをおもうと少し寂しい感じもする。
昨年 GOTY の栄誉に浴した『エルデンリング』はそのなかでも特殊な作品だ。
『ポケモン SV』の批評で書いたように、メインストリーム向けの作品ではだれがどのようなプレイをしてもクリアできるデザインになりがちだが『エルデンリング』は違う。マニア向けの高難易度アクションがベースにあり、そこに NPC の召喚や遺灰による招霊、戦技システムなどでカジュアル層も楽しめるようにできている。素の難易度を楽しみたければ自主的に縛ればいいわけだ。
つまり、『エルデンリング』はマニア向けながらも世界観にマッチした「救済措置」を組み込むことで AAA 級タイトルとして成功した。
こうした動きの背景には、ゲーマーの裾野が広がるとともに SNS や実況配信で繋がったエコシステムの成熟がある。「これが面白い!」という一部の層の声がたやすく拡がり、それを職業とするひとたちがあらわれた。僕の記憶がたしかなら『Escape From Talkov』もアーリーアクセス開始当初は一部のガンマニアが注目するだけだった。
マニア向けのとがった作品が広く評価されやすい昨今の傾向を僕は喜ばしく感じるし、万人向けでもハードコアなデザインをベースにするやり方はぜひ普及されてほしい。
というのも、消費者目線では、流行りの要素をツギハギしてわずかな差別化のスパイスをいれただけの薄い作品をフルプライスで買うのはあまりにリスクが高く、リターンも低いからだ。
ひょっとしたら、物語やキャラクターやデイリー報酬とおなじようにゲームとしてまず面白いことが大事な時代が来たのかもしれない。ゲームとして面白いとは、だれにでも挑戦しがいのある課題が用意され、達成感を覚える報酬があり、プレイヤーの自由な「遊び」の余地があることをいう。
これらを満たすゲーム作品は意外と少ない。

重力を感じるアクション
もし、ソウルシリーズにふれずに『エルデンリング』をプレイするなら攻撃モーションの遅さに戸惑うかもしれない。
操作性優先のカジュアルなアクションゲームではボタンを連打しても支障はないことが多いが本作は違う。攻撃モーションの遅さと敵のダメージの重さで適切なタイミングに適切なボタンを入力しないと命とりになるからだ。
プレイ体験の快適さを一見下げているだけのモーションだが、批評的にはいくつか重要な意味がある。
ひとつはもちろん、ハンドスキルと敵の行動パターンの捕捉に改善の余地を作ることで、初見では勝てそうにない相手でもやればやるだけ勝利にちかづける成功体験を実現していることだ。だいたいのアクションゲームでは難易度を上げることで敵の体を硬くして火力も高められるが、敵との読み合いで「どんな相手にも勝つチャンスはあるがどんな状況からでも負ける」公平な作品はそう多くない。
もうひとつは、映像表現としてリアリティを感じられることだ。
『ファイナルファンタジーVII リメイク』の批評で以前書いたように、高精細な美麗グラフィックを謳ったものでも人物や武器の重さを軽視した作品は少なくない。現実の物理法則をカンペキに再現する必要はないがそれらを考慮した『エルデンリング』のアクションは子供騙しにはみえず、映像表現にストレスを感じずに作品へ没入できる。
最後のひとつは、モーションに幅があることでビルドやロールプレイに意味が生まれることだ。
たとえば、爪や拳はこの攻撃モーションがとても軽い(短い)武器カテゴリーで、手数をふやしやすく状態異常の付与に長けるがそのぶんリーチも短く攻撃範囲がせまい。一方、特大武器や特大剣は一発のダメージが高く強靭削りにも秀でるが、攻撃モーションが重い(長い)ため被弾のリスクが高いという欠点がある。
重要なのはどれかが絶対的に強いわけではなく、プレイヤーの好みやスタイル、その都度の敵などにあわせて、ステータスの許すかぎり柔軟に変えられることだ。RPG でありがちな終盤の最強武器を握っておしまいというすべてを台無しにする味気なさとは無縁である。
このように、攻撃モーションひとつを切り取ってもプレイスキルやリアリティ、タクティクスなどの要素がよく練られていることが見てとれる。
『Mortal Shell』や『Steelrising』、『Thymesia』などソウルシリーズの影響が色濃い作品もふえているが、操作時の気持ちよさだけでなくさまざまな要素に配慮した密度の高いアクションゲームがこれから世に送られることを願う。

絶妙なバランスの装備
武器にふれたからには当然防具の話もしよう。
防具もまた、最強の装備を見つけらおしまいというわけではない。各種属性カット率や強靭度はそれぞれ違い、防具固有のバフ効果をもつ貴重なものもある。また、装備重量を軽くすることでローリングの飛距離が伸び、それをサポートするタリスマンもあるため重装備が正解というわけでもない。敵の攻撃スタイルも多彩で、相手にあった装備をステータスの範囲内でそのつど試すのがボス戦の醍醐味でもある。
つまり、防具の選択にもタクティクス(戦術)があり、装備重量をふやす持久力にどれくらい数字を振るかという意味ではストラテジー(戦略)の要素もある。
もっというと、各種カット率や強靭度、固有バフの違いを「誤差」としてオシャレやコスプレ(ロールプレイ)に全振りする考え方もあるだろう。極端な話、すべての攻撃を避けられるなら防具の違いはないにひとしいからだ。ちなみに僕はこのタイプで、どのゲームでもお洒落さは最優先事項だ。
すでに述べたようにゲームとしての面白さとは、だれにでも挑戦しがいのある課題が用意され、達成感を覚える報酬があり、プレイヤーの自由な「遊び」の余地があることだと僕は考えている。ロールプレイはこの「遊び」にはいり、『エルデンリング』がただ強敵を倒すだけの高難易度ゲームでないことを意味する。
もっとも、本作の防具は癖が強すぎるという否定的な声があるのもたしかだ。
実際のファッションでも癖のある服を着こなせるひとは少ないし、そもそも個性的な服を買うひとはかなりの少数派だろう。それを踏まえてゲーム(フィクション)内の装備をどの程度個性的にし、どの程度無難なものにするかはたしかに難しい。
僕の好みだが、正味な話、本作の防具が個性的すぎて使いづらいとはまったく感じなかった。たしかに癖は強いものの、そもそもの種類が多いため気にならなかったのが実感に近い。
そうじて、探索や戦闘の報酬として喜べるぐらいには防具の多様さがあり、そのタクティクスとロールプレイを絶妙なバランスで楽しめるようにできている。デザインはとても種類が多く、好き嫌いはわかれるものの、独特な世界観を活かしたユニークなものが豊富で高く評価できる。
このバランス感覚と種類の多さ、センスの良さはこれからの AAA 級タイトルにも引き継がれてほしいものだ。

プレイヤー主導の物語
ところで、ロールプレイングにはいくつか重要な要素がある。『ポケモンSV』の批評記事ではこう書いた。
ロールプレイングには、コンセプトの明確化、その遂行と洗練、そして、ゲーム内の課題の解決といくつかの要素があるからだ。
ロールプレイングの面白さとは現実の日常生活ではもとめられないこの想像力と試行錯誤にある。
ほとんどの RPG がそうであるように武器や防具の選択はこの遂行と洗練にかかわる。だが、密度の高いロールプレイングを実現するにはそれだけでは足りない。それが、プレイヤー主導の物語であり、作品世界の双方向性(インタラクティヴィティ)だ。
『エルデンリング』に僕が感じた不満のひとつはこれだ。すなわち、プレイヤーの取捨選択が物語としてはあまり要求されないことである。
クエストマーカーがないのでわかりづらいが、本作にはサブクエストともいうべき NPC イベントが数多くある。問題は、プレイヤーにゆるされた選択肢がおおむね、話しかける、アイテムを渡す、あるいは殺して装備品を奪うかのどれかで、実際には選択する必要がないことだ。あっても、最後の協力/敵対サインだけだろう。
すなわち、物語展開上、プレイヤーにもとめられる選択と分岐が少なく、好きな択を選ぶというよりはこまかく探索したかどうかが鍵となる。そのため、フィールド探索にインセンティブはあってもロールプレイとして選択に悩み、その後の展開を引き受け、自分自身の物語を歩んでいく面白さに欠けるのだ。
もっとも、これはほとんどの万人向けの RPG 作品にもいえることで、むしろ、本作ではメインストーリーだけでなくいくつかの NPC イベントにも分岐があるだけマシとすらいえる。
すでに述べたようにこれからのデジタルゲームは想定客層が広くてもマニア的な濃さや複雑さが強みになると推測される。
それを踏まえると、本作のようにクリア後の周回や新規プレイも楽しめる高難易度ゲームではその体験をより深める手段として物語の分岐と展開を複雑にすることが考えられる。少なくとも、ビルドと武器や防具の幅広さが活きるのはまちがいない。

考察を誘う物語の「穴」
物語に関連して、本作、というよりソウルシリーズに顕著なフレーバーテキストに依存した語り方を僕は評価していない。
というのも、物語に入り込むにはあまりに「穴」が多く、作品の世界観は楽しめても物語の展開を楽しむことはできないからだ。
たとえば、プレイヤーの多くが火の頂にてメリナを犠牲に黄金樹を燃やしたとおもうが、その物語の流れにどれほど躊躇や後悔を感じただろうか?
メリナが生存し、敵対もしない抜け道のようなルートが最難関イベントにあることを考えると、指巫女の代わりであるメリナはやはりプレイヤーキャラクターにとって大切な人物で、彼女を焼くことはこの物語でもっとも大きな選択にちがいない。そこに躊躇や後悔を感じなかったなら、感情移入させられなかったという意味で語り方としては失敗している。
もし、成功していたなら、火山館サイドの背律者ベルナールや狂い火サイドの指痕爛れのヴァイクなど、おなじ褪せ人でありながら二本指に反旗を翻した人物とその陣営もより真に迫ったものになり、エンディングでの律の選択がもっと悩ましいものになっただろう。
もちろん、この物語の「穴」の多さがファンコミュニティの「考察欲」を掻きたて、さまざまなコンテンツを生んでいるのはたしかだ。ソーシャルメディアや動画サイトが浸透した今ではひとを語りたがらせることほど大きな強みはない。
しかし、物語の考察と鑑賞は別物で、考察は作品そのものではなくその「穴」から作品世界を想像し仮構することだ。物語鑑賞は作品そのものの語りを楽しみ、評価することなため、考察しがいがあることは作品世界の魅力を前提にしても、作品そのものの語りの良さまでは保証しない。
おもうに、このスタイルの裏には、試行回数の多い「死にゲー」や寄り道が推奨のオープンワールドゲームでは開発の予期しないタイミングでプレイ時間が長くなり、間延びしがちで、場合によっては物語に矛盾が生じる相性の悪さがある。
その意味では、本作にかぎらず、オープンワールドやローグライト、高難易度アクションなどはひとしくおなじ問題を抱えている。そして、忘れてはならないのが、この相性の悪さに積極的なアプローチを試みた作品もわずかながらあることだ。
たとえば、Supergiant Games のローグライクアクション『HADES』は豊富な会話と人間関係の変化により、マンネリしがちなプレイの試行を物語そのものに変えた。また、Owlcat Games の「パスファインダー」シリーズは日数制限を含むさまざまなリソース管理であまえたプレイングと探索を咎め、物語の緊迫感を手放さなかった。
それをおもうと、『エルデンリング』のあえて物語らないことで「考察欲」を刺激するやり方はかなり消極的なアプローチといえそうだ。
ひょっとすると、メインストリーム向けの AAA 級作品(だいたいは「アクション RPG 」を謳ったもの)の影が薄くなってきたことはまた、ながらく支配的だったシネマティックな物語と今日のさまざまなゲームデザインの衝突を示しているのかもしれない。
ゲームデザインと物語をいかに調和させるかは今なお未解決の問題であり、あたらしい模索の時期を迎えている。

オープンワールドの金字塔
最後に、本作の目玉であるオープンワールドのデザインにふれよう。
結論からいうと、『エルデンリング』はどこを切り取っても「絵」になるフィールド作りとプレイヤーの「探索欲」をむりなく刺激する報酬デザイン、オープンフィールドでの超大型クリーチャーとの騎乗戦闘などでこのジャンルの水準を大きく引き上げ、荒削りながらもアクション RPG の金字塔を打ち立てた。本作に比肩するものはむこう数年は現れないだろう。
漂着墓地の重い石扉を押し上げ、黄金樹とストームヴィル城を一望しながら冒険のはじまりに胸を高鳴らせたことを覚えているだろうか。
あるいは、霧のたゆたうリエーニエの湖を霊馬で駆けながら水面に映る月明かりに驚いたときでも、ルーンベアに恐れ慄いて逃げた先の遺跡から神秘的な地下世界に迷い込んだときでもいい。本作には息を呑むロケーションが満ちている。
『エルデンリング』はオープンワールド RPG としてはかなりめずらしいスッキリした UI が特徴だ。クエストマーカーが画面の一部を埋めることはなく、アクティビティのある場所を指し示すオーバーレイもない。プレイヤーは文字通りの意味で「祝福の導き」をたよりに進むことになる。
この勇気ある決断を支えているのはランドマークを活かしたオープンフィールドのデザインだ。
たとえば、漂着墓地から出てすぐのスタート地点からは、レガシーダンジョンであるストームヴィル城をはじめ、黄金樹、神授塔、エレの教会、はじまりの祝福と、進行上必要なロケーションがすべて一望できるようになっている。また、ファルム・アズラやミケラの聖樹などをのぞき、ほぼすべてのエリアから黄金樹が見えることでどこが最終目的地か忘れないように出来ている。本作のフィールドデザインは動線の機能性とアートの美しさを高次元で融合させている。
また、多くのプレイヤーが自由な探索に誘われたと僕は信じるが、それが「無理のない」刺激だったことを評価したい。
というのも、Bethesda の「フォールアウト」シリーズや Larian Studios の「Dibinity: Original Sin」シリーズなどでは、ルーティングが重要なあまり「ゴミ拾い」のような煩瑣な作業がプレイングの大部分を占めかねないからだ。もちろん、それが好き、中毒性がある、というひともいるだろうが、擬似的な運要素にたよっていたずらに作業を強いるデザインを僕は評価しない。
要するに、本作のマップ探索は課題を解決するうえではあまり重要な要素ではないのだ。
ソウルシリーズのファンならよく知るように、本作の序盤にある平凡な武器が弱く、終盤入手のユニーク武器が強いとはかぎらない。防具についてもすでに述べたとおり。つまるところ、ロールプレイでも、タクティクスでも、課題難易度の面でも、探索すればするほどより楽しく、より強くはなるが、別にしないならしないでも十分戦える。
また、本作のクラフト可能な消費アイテムもあるに越したことはない便利さだが、別にないならないで特に困らないという調整だ。そのため、マップ探索にインセンティブはあっても、消費アイテムにこだわりがなければ素材集めは賑やかし程度の価値しかないため気楽な放浪を楽しめる。素材収集要素もないならないで味気ないだろう。
そして最後に、霊馬トレントに騎乗しながらのドラゴンとの戦闘だ。
最序盤の印象的なシーンなためその後の記憶に潰されがちだが、飛竜アギールや輝石竜スマラグのブレス攻撃から愛馬で必死に逃げるさまはまさしく本作でしか味わえない格別のファンタジーライフだ。
もっとも、結構な数のひとが感じるようにこの要素を活かしきれたかには疑問が残る。というのも、騎乗戦闘が強いのはプレイヤーキャラクターの火力が低い序盤だけであり、霊馬を活かしたギミック自体もほとんどないため物語が進むにつれて存在感が薄くなるからだ。
おなじことはほかにもいえる。
フォトモードがないのもそうだが、中盤以降のダンジョンにはすでに登場したボスが複数体で出現するなど「探索欲」に冷水を浴びせるものも少なくない。僕は遺灰を使わずとも「夜巫女の霧」や「輝剣の円陣」で複数体ボスもさほど苦労しなかったが、それでも(実際の意図はどうあれ)ソフトコンテンツの水増し感は否めず、フィールド探索の楽しみをやや奪われたように感じたのが正直なところだ。
そうじて、美しい景観と機能性をかなりの高水準で達成したオープンフィールドは素晴らしく、その「箱」を活かした UI も騎乗戦闘も種類豊富な収集要素のバランスもきわめてユニークだ。ソフト面ではやや疑問が残るものの、『エルデンリング』が実現したアイデアが未来のオープンワールドゲームでどのように発展し、洗練され、超克されるか楽しみでならない。

最後に
この批評は、2月10日の日中にその大部分を書き上げている。
つまり、今年最初の大ヒット作品であるオープンワールドゲーム『Hogwarts Legacy』のことを考慮していない。本記事でいくつか抽出した論点と評価はこの作品をより適切に分析するうえでとても役立つだろう。もちろん、僕自身もきちんとプレイしてから批評を書くつもりだ。
デジタルゲームを分析するのは難しく、「面白い、面白くない」の評価をだすのは至難をきわめる。
というのも、実際のプレイヤーの数だけ期待があり、スキルとスタイルの違いがあるからだ。『エルデンリング』を最初のマルギットで挫折したひともいれば無限に周回プレイしているひともいるし、すみずみまでマップ探索してからエリアボスに向かうひともいればオンラインでの協力プレイや対戦プレイを楽しむひともいる。それぞれで作品の見え方に偏りがあり、ことなる感想がある。
『ポケモン SV 』もそうだが、本作のオープンワールドやバランス調整が賛否両論なのはプレイヤー層が多様化し、作品もまた想定客層を広げている事情がある。今は懐かしき「霜踏み」弱体化の騒ぎを思い出してみてほしい。
この記事では、個人的な理由から「かるく、かんけつに」書くことが目標だったため、『エルデンリング』を包括的にとらえることよりも論点をしぼり、今後のオープンワールドアクション RPG と比較するのに役立つ批評を心がけた。そのため、こまかい補足や条件を省き、プレイスタイルによる印象の違いは書いていないが、記事中の「評価」はその多様さを意識してバランスをとっている。
僕の目下の課題は『ホグワーツ・レガシー』をどのように評価するかだ。そのためには「オープンワールド」という手垢のついた概念を考えなおす必要がある。次の批評記事を挙げるときには本作の「オープンワールド」もより適切に、より簡潔にとらえられ、他作品とのちがいもよりハッキリと理解できるようになっているだろう。
そのことに何の意味があるかはわからない。
ただ、この世の膨大なコンテンツから素晴らしいものを掬いあげ、その秘密を言葉にすることで忘却の波に少しでも抗うことが僕なりの今の時代にたいする戦い方なだけだ。そして、自分とおなじように作品を分析する言葉をツールとしてもとめるひとの存在をなによりも強く信じている。