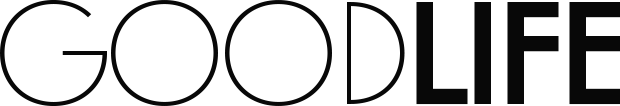大学生はコロナ禍の世界をどう観るか
SNS時代のおめでたい野次馬の暴走、種苗法-ドン・キホーテ-テラスハウス
せっかく気になっている相手と一緒に遊びに来たというのに、相手は隙を見つけてはスマホを取り出し、指紋の凹凸の具合が心配になるほど熱心に画面をこすっているのでモヤモヤした、という経験をお持ちの方はいますか。しかも、それとなく画面を覗いてみると(最も推奨されざる行為)、ツイッターのアプリが開かれていて、今まさに「沈黙が長すぎて息苦しい、なんか喋れよ。はやく帰りたい」という心の叫びが、裏アカウントから投稿されようとしている……。
羊谷:今、新型コロナ禍でさまざまな業種・業態が変化を迫られています。大学生もまた同様でしょうが、ソーシャルメディアの特性上、20代半ばを越えて学生さんとの繋がりがなくなるとその実情が全く見えません。マスメディアへの信頼が持ちにくい時代でもありますしね。まず、春先の新型コロナの影響でどのように学生生活が変わったか教えてください。
ピルスト:私の大学は、入構禁止期間が4月から約2ヶ月間続き、6月に解除されました。オンライン授業は5月中旬から開始され、教授の弛緩した講義を倍速で聞き流せるという効率化や、交通費がかからないというお得感がありますが、だったらはじめから参考書を読めばよく、そもそも授業料を払い続けていることを考えれば、オンライン授業にあまり利点は感じられません。特に、新入生はかわいそうだなと思います。せっかく受験から解放されたと思った矢先、質の低い(かもしれない)映像型予備校に幽閉されてしまったわけですから。しかも、まだ一度も同級生と会ったことがないと聞きます。バイトに関しては、飲食店なので宣言下では休業し、前後では営業時間の短縮、シフトの削減、さらにテイクアウト用メニューなるものが追加されたりと、直接的な影響を受けました。
あさだ:一番変わったのはあらゆる面での情報量でした。講義が原則オンラインになり、外出も生活に必要な分以外は省いたので、身体に飛び込んでくる視覚的、聴覚的、嗅覚的な情報が従来の半分以下に減った感じです。人の姿が見えず、人の声が聞こえず、街並みの変化も見えない。当初は、無駄な情報が減ったので、ゆっくり色々な文章を読んだり考えたりできるかと思いましたが、気付けばSNSを開く時間が増えていました。失われた情報量をSNSで埋め合わせようとしているのかな、と。また、6月頃はそれで時間が溶けることも増えたので、意識的に何もしない時間を作るようにしました。ひょっとしたら時間の感覚も間延びしているかもしれません。大学の同級生の声はたびたび通話で聞いていますが、姿が見えないので、生きた人と話している実感は薄いです。生身で会っている時には相手の仕草や表情が見えるので、そこで回答を判断したり、別の友人と遭遇して話を広げたりできましたが、それらが消えたコミュニケーションには正直まだ慣れません。
羊谷:興味深い論点ですね。あさださんにまずお聞きしますが、4回生のピルストさんよりも今期の授業数は多いと思います。ご自身の大学のオンライン授業及びコロナ禍の教育態勢をどのように観ていますか?
あさだ:私の場合、パソコンやスマートフォンを日常的に使っていたので、オンライン講義への変化にはそれほど難を感じませんでした。すんなり対応できたのは、秋学期テストの終了と、新型コロナが本格的に騒がれはじめた時期が被らなかったからでしょう。ただ、今の大学生でもPCに慣れている人ばかりではないですし、新入生は入学準備期と最初期の「自粛」期間が被ったわけで、大いに戸惑ったはずです。
オンライン講義は、科目によっては適宜聴き飛ばせるメリットもありますが、一人で画面へ向き合っていると、講義の質への不満が嫌でも自覚させられます。もともと、ここまで拘束時間を取らずとも、本一冊を読んで熟考すれば足りるのでは、この時間を圧縮すればどれだけの本が読めるかなどの不満がありましたから。実際に聴き飛ばしてみると、「こんなことで済む講義にあんな高い授業料を払っていたのか」という実感がショックとしてやってきました。これで済むならば学歴を買いに上京したと言われても仕方ない、という思いと、学生の能動的な姿勢に多くを依っている大学だな、という思いが交錯しました。なら図書館を活用しよう、という発想に至りましたが、当初は臨時休館でどうしようもなく、途方に暮れました。今は予約入館と郵送貸出で何とかなっていますが、気軽に行って「ついでにこの資料も借りよう」というやり方ができなくなったのは痛いです。
羊谷:大学の授業はたしかにピンキリですね。僕の経験上、ゼミも講義も平均より少し下の学生にあわせるので自発的に勉強できる学生には物足りないでしょう。だからこそ、大学の価値は図書館や興味関心の近いひとが自然に集れる場所の濃さにあったわけですが……。

羊谷:次にお聞きしたいのはあさださんが最初に話されたコミュニケーションと情報量の変化です。僕自身はコロナ以前から寄稿者さんとの打ち合わせはオンライン通話でやっていて、ピルストさんとはまだお互いの顔も知りません(笑) そこで僕がいちばん気を付けているのはポジティブな感情を直接表現し、生身の相手と接している実感をもってもらうこと。やっぱりこの感覚がないとひとは猜疑心を抱いてしまうので。大学生ってほとんどの場合、英語クラス、サークル、ゼミなどで普通に活動していれば自然と友だちができますが、社会人は見ず知らずの相手でも積極的に声を掛けたりイベントに参加したりしないと人間関係を拡げられません。今の学生がコロナ禍で突然コミュニケーション難度の高い環境に投げ出されたのはつくづく気の毒です。ピルストさんはあさださんの指摘を聞いてどう思いましたか?
ピルスト:身体的な情報量の減少に関して、あさださんと同じ感想です。身体的なコミュニケーションの大部分が、情報化によってそぎ落とされてしまっていると思います。ZOOMなどの動画のリアルタイム共有なら相手の表情の一瞬のゆらぎや、語調の変化などはなんとか読みとれますが、脚を組みなおしたり、爪をいじったりしている様子は見えません。それらのしぐさは明確な意味を伝えているわけではないので、言葉が聞こえればべつに見えなくてもいいのですが、見えた方が豊かであることは間違いないと思います。また、友人をつくる際に私は、特に目的のない時間をその人と一緒に過ごせるかどうか、という点で判断してきました。しかしこの有意義な「だらだら」というコミュニケーションは、コロナ禍では自宅で一人でやるしかないということで、とても残念であり不満です(でした)。
羊谷:おふたりのお話を聴いて心配になるのは学生のメンタルヘルスですね。僕の経験では、2011年の東日本大震災のときと近いものを感じます。あのときの方が突発的で、国内の被害規模は大きかったですが、今回は真綿で頸を締めるように経済と心理状態を毒しています。コロナ禍の学生のメンタルヘルスについてご自身の経験やご友人などの印象的なお話を教えてください。
あさだ:私の場合は、気の置けない友人たちに生身で会いたい、距離も音量も気にせず会話したい、という欲が日増しに強まっています。通話しているのでコミュニケーションが取れていないわけではありませんが、先に述べた身体的情報の希薄さに加え、アパートの壁が薄いという事情もあります。まめに通話を行い、溜まっている鬱憤や愚痴を吐き出すのが発散方法ですね。ただでさえ鬱々としているので、明るく振る舞った方がいいのかとも考えましたが、万事それでは蓋をし続けることになるので、かならず無理が来る。ネガティヴな感情を意識的に発話することで、バランスを取っています。もちろんこれは、話し相手の友人と互いに了解したうえでですが。また、学内の友人に加え、SNSで知り合った友人とも文章の遣り取りをしているので、どうにか世情に疎くならずに済んでいます。元々構築されていた交友関係に救われている部分が大きいですね。新入生とはまだ直接には会えていませんが、横の人間関係を作るスタートラインにすら立てていない人が非常に多いとも聞き、ピルストさんのように、つらかろうな、と思っています。
ピルスト:メンタルヘルスでいえば、私は一人でいることにそれほど苦痛を感じない人間なので、長い休暇の気分でのんきに暮らしていますが、それは口座残高から目をそらしていても何とか生活できる恵まれた経済基盤があるからにすぎません。今のところ、身近には退学を余儀なくされるほど困窮した友人はいませんが、コロナ禍による就職活動の遅延もあいまって、精神的に憔悴している友人はいました。どうやら、ビデオ会議では人柄の判定が難しいという理由で、通常より多くの面接を受けさせる企業もあり、選考期間が長引くことがあったようですね。また、教授から、オンライン授業に慣れることができずに単位を落としそうな大学1、2年生が例年より多い、という話を聴きました。これは、理解が追い付かないことが原因というよりはむしろ、自宅にこもってもくもくと講義を受け課題を提出するという決まった作業を続けるなかで「あれ、なにやってんだろ」と気づいてしまったことが原因ではないかと思います。注目したいのは、そのような学生は、直接連絡して話を聴いてみると意外とすんなりまたオンライン授業に復帰するらしいということ。複数人をまとめて対応するのはらくちんですが、面倒な個別対応にこそ人は安心を感じるのでしょう。

羊谷:ピルストさんからコロナ禍の経済的基盤のご指摘がありました。ご自身の経済状況の変化、アルバイト先のご様子、ご友人などの印象深いお話を聞かせてください。
あさだ:もともと、実家の仕送りがあったので経済的に困ってはいませんでしたが、年頭から半年の予定で入っていたパン工場でのアルバイトを、5月の下旬、少し早く切り上げました。本を買うお金が少し貯まり、周りで誰が切られるかという不安と殺伐の入り混じった空気が漂い始め、多少余裕のある私が居座り続けたらまずいと感じたからです。職場にはこの仕事を生活費の基盤にしている方も多く、新型コロナが騒がれはじめた時期には、そわそわし出したり、口数が増減したりする先輩たちが目立ちました。
大学の友人には、バイトのシフトがなくなる、リストラに遭うなどの憂き目に遭った人がかなり多いです。ただ、中退にまで追い込まれた学生は、今のところ交友関係の中にはいません。私が通っているのは都内の私立大学で、もともと経済的には盤石な家の学生が多いことが、要因としてあるかもしれません。例えばあの10万円給付の時などは、「現実には生活費に回すがそれはそれとしての妄想」というわけでもなく、「何買おう」と本気で話していた人もちらほらいましたから。もっとも、私の知らないところで辞めた学生も多いかもしれませんが。
私に関する限り、最大の問題は進路選択で、特にピルストさんも仰っていた就活については頭を抱えています。内定を取り消す企業、インターンを中止にする企業が続々出ています。私は2年次のうちに院進を希望していましたが、対岸の火事とは言えません。この分では3年後の社会経済がどうなるかも見通しが立ちませんから。極端かもしれませんが、多少倍率が高くとも、もう今の段階で進学から就活へ舵を切った方がよいのではないか、とも思い始めています。どこかで薄ぼんやり、当面はまあ問題ないんじゃないかと高を括っていたコロナ前の自分をビンタしたいですね。とにかく将来への不安は払拭できません。
ピルスト:私は悠々自適の実家暮らしなので、家賃、水道光熱費、食費等は家族に負担してもらい、それ以外の交通費や教材費等をバイト代から出していました。自宅にいれば交通費も教材費も掛からず、バイトをしなければならないというひっ迫した環境ではありません。バイト先に関しては、万年人手不足の職場にもかかわらず、コロナ禍では希望通りシフトに入れない人が大勢現れ、会社から「不安があれば、相談してください」といった連絡が回るほど、営業は厳しいものだったようです。飲食店に限りませんが、食品を扱う仕事は廃棄が増えても得はありません。一方で、なにかの拍子に大勢お客さんが来たときに料理の提供ができなないと、結果としてお店は評判を落とすことになるため、大胆に仕入れを絞ることもできません。緊急事態宣言下ではそもそも営業ができず、その前後はお客さんの予測が難しく予期せぬ対応が迫られるというコロナ禍の影響は、経営へのダメージと従業員の不安としてあらわれていました。
また、シフトに入れないのでバイトを変えたという友人はいましたが、経済的な理由で中退を余儀なくされたひとはいません。私もあさださん同様、私立大学に通っているので、周りに見かけないのはそれも理由の一つかと思います。ちなみに私のバイト先は、今ではほとんど通常営業に戻っているらしく、人手が不足し始めたとの連絡も入ってくるようになり、私の休暇もついに終わりを迎えそうです。
羊谷:東日本大震災のあと、学部時代から仲の良かった大学院の先輩が精神的な事情かなにかでご両親が急に働けなくなり仕送りが断たれていました。ご本人がそれから1年間なんとか懸命に働いて無事に修士課程は終えられたのですが、オレはもうお金に苦しめられすぎたよ、とつぶやかれ、今は小説執筆を止めていることを卒業後に聞いたのをよく覚えています。新型コロナの経済被害、昨秋の消費増税などによる日本及び世界経済の落ち込みとその影響はこれからでしょうから、学生の経済的苦難はひょっとしたらまだ先の話かもしれませんね。

羊谷:さて、あさださんから進路選択の悩みがありました。現代社会はもともと流動性が高く、さまざまな技術や能力が民主化され、物事の移り変わりも速いので「その先」を予測するのが困難です。そして、今度の新型コロナ禍。一部の識者にはパンデミックの発生は予測可能だったそうですが、世界の多くのひとにとっては晴天の霹靂で、収束と被害規模のみえなさから将来への不安感に苛まれていることでしょう。今、この不確実な時代におふたりが「働く」ことをどのように捉え、どういう道に踏みだそうとしているか、あるいは、今何に行き詰まっているか教えてください。
あさだ:2020年の日本に生きる身としては、生活費を得るための社会的行為一般……生き延びるためのさまざまな道がありますが、その中で最も無難な道と捉えています。もちろん、それだけでは勿体無いので、何らかの新たな意味、あるいは価値の創造をはじめ、自分以外の人間にも意味を持たせられれば良いな、とも。とはいえ、自分の専攻を直接的に活かせる仕事に就きたいかどうか、と言われれば、それは微妙です。これについてはコロナの流行前から変わりありません。重視したいのは適性、個人と職種の相性の良さです。それを無視して「憧れの会社」に入社したはよいが、メンタルを傷付け退社した、という人が身近にいるので。ですから就職するにせよ、職種についてはある程度割り切っていこうと思います。うまく合致すれば幸せかもしれませんが、まずは生きなければ話になりませんから。好みに関係ないところで働くことになったら、いかにしてそこで他のこと、例えばみずからの行動原理などに活かせるものを得るか、いかにして余暇を楽しいことに活かせるか、この二点がいざ就職したら課題になるでしょう。
ピルスト:コロナ禍以後、景気が悪化し雇用が減少することを除けば、仕事そのものの変化はあまりないと思います。都知事の「夜の街」発言のように、特定の業種の人たちは災害が起こるたびに被害を受け続けますが、かといって今回の件でポジティブな変化が起こるとは思えません。テレワークの導入もその場しのぎのために使われているだけで、コロナ禍が収束すればほとんど使われなくなるでしょう。また、専門家がパンデミックを予測できていたとしても、そもそも社会自体がパンデミックの可能性をほぼ無視した設計をされているため、だれもなにも出来なかった(しなかった)のではないかと。もちろん、医学上のブレイクスルーが起きれば話は別ですが。同じことは、日本において近い将来、首都直下地震が起きることが歴史から明らかにもかかわらず、どうにもできずにいつも通り社会を運営し続けていることからも言えます。なにより、パンデミックを完全に防ぎたいなら人間の交通を制限する必要があり、おそらく最も合理的な方法が鎖国ですが、グローバリゼーションの時代に徳川時代のアイデンティティが太刀打ちできるとは思えません。根本的なことを変えることは出来なくてもリスクを地道に減少させることは出来るはずですが、それらの対策の多くは個人や企業の経済活動の自由を制限することになるので、実現するのは難しいかもしれません。コロナ禍が収束したとき日本人が手に入れられるのは布マスクだけです。
ともあれ、具体的な話としては、想像力のない作家にとってコロナ禍は待ちに待った事態であり、よだれの出るような題材ではないかと。2011年の震災と違い、やっと自身も当事者になれて、周りの目を気にせず思ったことが書けるわけなので。ただ、そもそも専門性のない作家が偉そうに何かを言ったところで大した影響力などないし、私としては現状を慰めとりあえず政権を揶揄しておこうというエッセイは鼻紙にもしたくないと思ってしまうひねくれた人間なので、やはりもっと無責任なものを読みたいし、書きたいです。ちなみに、私にとっての賃金労働は、創作活動のための資金集めのような位置づけです。下世話かもしれませんが、どこから金を引っ張ってくるかについて考えることは、表現の自由について考えるということでもあると思います。俺は自由だ!と言って働かずにそのへんをうろついたところで、その行動にはなんの意味もありません。媒体の選択や、ものづくりのための基盤の構築は、それ自体がすでに表現の一部になっているというのが私の考えです。

羊谷:では、最後の質問です。おふたりが今の、あるいはこれからの新型コロナ禍の大学に望むことを教えてください。
あさだ:正直、2年半近くの時間を大学で過ごし、失望させられることが様々にあり、他大へ行った友人から話を聞いてみて「どこも同じものか」とさらなる失望へ至り、ひとにぎりの教授による鋭い授業と、図書館と、サークルのような場の3つさえあれば、望むことは特にないと思っていました。ですが、今回のパンデミックと入構制限で、物理的なもの・ことに思索や生活サイクルの多くを依っていたことを、嫌でも思い知らされました。これを機に、図書館には蔵書資料のデジタルデータ化と暗号通信化を進めて貰いたいです。場所と時間に関わりなく、資料を素早く参照できるシステムができれば、研究と学習の効率化が進むでしょう。また、私としては、今後もオンラインかつオンデマンドでも講義を受けられるよう、選択可能なシステムとして構築して頂きたい。多くの人が教育の機会を洩らさない社会を目指すには、これが不可欠です。
私は都市の電車で通勤通学地獄を味わっています。オンライン講義に入り、電車に乗る機会が減ってから気付いたのですが、家から目的地へ行くだけで疲弊する、勉学か仕事へ向かっているのにその途中で疲れている、これはちょっとおかしい。非合理的、非生産的です。物理的移動と混雑は肉体的に多くを消耗させるので、この点でもオンライン講義の継続による効率化が期待できます。また、都市部に拠点を構える会社や官公庁全てにも要望したい。これは、この豚小屋電車を野放しにして金を稼いでいる鉄道会社に恨みを覚えている、という私怨もありますが、なくもがなの要素を排する適切化と、リスク管理ゆえです。ピルストさんが、パンデミックの可能性をほぼ無視した設計の社会、と仰っていましたが、私の場合、もっと直接的な危機を覚えています。テロです。都市、少なくとも東京とそれを構築する周縁部のベッドタウン、その物理的移動を担う電車についてそう感じます。上京1年目に、今乗ってるこの電車でテロが起きたらどうするんだろう、爆弾でなくともガソリンでも撒かれたら、と思い、ゾッとしたのをよく覚えています。社会も共同体も思考停止の裡に成り立っている側面がありますが、それにしても、パンパンに膨らんだ釘入りの風船を思わせます。
ピルスト:大学に望むのは授業料の返還ですね。通信費と称した数万円の給付はありましたが、ひと月の授業料に満たない返還では焼け石に水です。オンライン授業は、私も普及してほしいと思います。ただ、私の大学に限った話かもしれませんが、オンライン授業は履修登録が必須で、単位をとるつもりのない講義に「もぐる」のは不可能になりました。完全登録制なので、もしかすると、オンライン授業は学問の閉鎖性をさらに高めることになるかもしれません。アーカイブとしてすべての授業を参照できるようなサービスがあれば便利ですが、私の通う大学には全く期待できません。
一応大学の利点を挙げておくなら、化学や工学の研究には高価な実験機器が必要になる場合が多く、これらの機器を個人でそろえることは不可能です。また、生物分野であれば、動植物を育てる土地や動植物それ自体が必要になり、これもまた個人でそろえるのは難しいでしょう。普通に生活していたら、絶対に経験できなことを経験するために必要なこれらの資源は、いわば「すばらしきキャンパスライフ」と「新卒採用」という宣伝文句によってまかなわれています。複雑な気持ちになりますが、かといってコロナ禍以後も大学は変わらないと思うので、それぞれの目的に応じて利用していくのが良いのかなと思います。