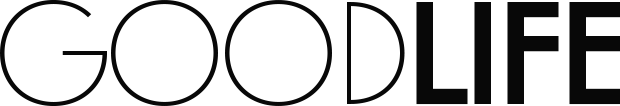アメコミ映画の多様性が見直されるようになって久しい。
2017年のガル・ガドット主演の『ワンダーウーマン』は、スーパーヒロインというだけでなくアメコミ映画初の女性監督パティ・ジェンキンスが制作したことで先駆的であったし、2018年公開の『ブラックパンサー』も黒人監督ライアン・クーグラーが彼らの文化を強くフィーチャーした制作で『タイタニック』『アバター』に次ぐ興行的大成功をおさめた。
ポルノ写真家の荒木経惟が長年の女性モデルから告発されたことで日本でも話題を呼んだ MeToo 運動も、アメリカの映画業界で火蓋を切られたことを忘れてはならない。
世界のエンターテイメント業界は奇妙なまでに保守的な風土であるらしい。
2018年のアカデミー賞長編アニメ部門を受賞した『スパイダーマン:イントゥ・ザ・スパイダーバース』も、アフリカンとヒスパニックの血が混じる少年マイルス・モラレスが主人公という意味ではそうした多様化の流れに属する印象を受ける。
が、マイルスが冒頭で仲の良い叔父の、最後には警察官の父親の肩を借りて描くグラフィティにはきまって自身のからだの縁取りを残しているように、肩肘はったマイノリティの声というよりは等身大の自分というメッセージが見え隠れする。
実際、今作の悪役キングピンの加速器を用いた実験によりマイルスの次元に迷いこんだ中年のスパイダーマン、ピーター・B・パーカーは、メタボ気味なうえに自堕落な性格が災いしてシリーズ伝統のヒロインMJと離婚していたりする。
下半身は灰色のスウェットという締まらない格好の彼をして「なんかオレと違って完璧」といわしめるマイルスの次元の(おそらくは本来の)ピーター・パーカーは開始早々に殺害され、彼の遺産を使ってマイルスやオッサン・パーカーをはじめ、スパイダーガールのグウェン、フィルム・ノワールの世界でナチと戦うノアール、アニメ世界でスパイダーロボを操る日系アメリカ人の少女ペニー・パーカー、そして、動物キャラのコミック世界からきた子豚のスパイダーハムが活躍するコミカルなカオスはなんとも小気味良く象徴的だ。
『ブラックパンサー』が見ようによっては幼馴染みの斥候だの親衛隊長だの科学者の妹だのといった強く自立した女性たちに囲まれた軟弱な優男という逆立ちしたハーレム構造をもち、いささか単純な古い世界観を擁していたのに比べれば、『スパイダーバース』の等身大という手垢のついたメッセージはその高度に複雑なコンピューティング・アニメーションを用いた映像表現と同様に革新的で味わい深い。
偶然だろうが、米国屈指の人気ラッパーのケンドリック・ラマーが監修した『ブラックパンサー』と今度の『スパイダーバース』には彼と同じ出身地のあるミュージシャンが参加している。
米国有数の犯罪都市コンプトン出身のヴィンス・ステイプルズだ。
彼を知ったのは、多分、2017年のセカンドアルバム『ビッグ・フィッシュ・セオリー』の頃だろうか。
ヒップホップはその音楽的ルーツに強烈なコミュニティ意識をもつせいかなにかと既存の型にハマりやすいジャンルだが、芸術志向の強い彼の音楽性はそのなかにあって不思議と異彩を放っている。
特に、同郷のケンドリック・ラマーを客演に迎え、アイドル系統のポップミュージックを上品ながらも奇形的に変奏することに長けたスコットランド出身のソフィーと、オーストラリアの新星フルームをプロデューサーに据えた「Yeah Right」は、ケンドリックの熱量あるラップも含めそれぞれのいびつな個性がカットアップ的に巧く混ざった名曲だ。
『スパイダーバース』の「Home」でヴィンスはこうラップしはじめる。
This morning I woke up in a fortress of distortion
(今朝、ディストーションの要塞のなかで眼が覚めたんだ)
I’m at war with my emotions, I’m at war with they enforcement
(オレは戦争中だ この感情の手先たちと戦っているんだ)
前掲の9分間の映画冒頭を観た方は気付いただろうが、ヴィンスのこのリリックは主人公マイルスなどにありがちな思春期の繊細な心のありようの巧みな詩的表現になっている。
歌詞全体を見渡したときに興味を惹かれるのは、「オレ」がマルチヴァースのように作品を作る自分と享ける自分に分裂し(マイルスはラップこそしないがグラフィティを描く)、ときに作り手の「オレ」が享け手の「オレ」に呼び掛ける形をとるため相互に矛盾したフレーズが意図的にぶつかりあっていることだ。
I wanna be home free, where’s one that was lonely?
(オレは自由の家でありたい かつて寂しがり屋だったアイツはどこへ?)
But I’m ready and waitin’
(だがだいじょうぶだ 待ち続けている)
For my day of salvation, and I’m patient
(救済の日まで オレは我慢強いんだ)
フックはこうだ。
I’m coming home now
(オレはいま家に向かっている)
I’m coming home
(家に向かっている)
Right where I belong now
(オレが今あるべき場所へ)
Right where I belong
(あるべき場所へ)
Home という言葉はたんに家や土地を指すだけでなく、家族や故郷のように自分の精神的な居場所やルーツも含意しているが、彼のこの歌詞のおもしろさはその Home にこそアーティストの戦場があるという矛盾した二重性が表現されていることだろう。
余談だが、ヴィンスに注目する日本人リスナーは僕以外にもわずかながらいるようで、彼の「リアル」を問われたインタビューの部分訳を日本語で読むことができる。
商業的なパーティ音楽だって本当にパーティして楽しみたいって人たちが作ってるんだし、それは「その人たちにとってリアル」だよね?
「リアル」って言葉を使うとき、それは「アーバンでアグレッシブ」って意味なのか?それが全員にとってのリアルなのか?
人の人生は人の人生だ。何があったとしても、音楽は自分の人生の鏡であるべきだ。
戦場は自分のなかにしかない、少なくともヴィンスはそう考えている。
今振り返ると、『スパイダーバース』の物語にはひとつだけ制作側のご都合主義を感じる部分があった。
マイルスがもっとも信頼し心を寄せていた人物――アーロン叔父さんがスパイダーの能力に目覚めたばかりのマイルスを庇ってキングピンの銃弾に倒れ、彼の亡骸のそばに跪いているのを警察官の父が目撃、新しいチビのスパイダーマンが自分の弟を殺したのだと勘違いする場面だ。
原作コミックでの扱いは知らないが、結局この誤解はうやむやのうちに解消され、特に明確な理由や根拠も示されないまま「殺したのは違うヤツだった」と丸くおさまる、なぜだろう?
スパイダーマンが最も信頼していた人物を失うのは様式美のようなもので、大事な人物を失ったマイルスを「その気持ちがわかるのは私たちだけ」「みんなを救えるとは限らないんだ」と各次元のスパイディーたちが慰める。
この喪失というテーマを得意としたのが、『(500)日のサマー』でカルト的な人気を収めて『アメイジング・スパイダーマン』の2部作を監督したマーク・ウェブだ。
特に『2』ではスパイダーマンの正体を知り「娘にはもう近付くな」と遺言を残した恋人グウェンの警察官の父が何度も亡霊のように現れ、人間の心の深い暗がりを丹念に描くと同時に、実際にグウェンを喪った5ヶ月後に迎える白昼のエンディングの澄み渡る清らかさは映画屈指の喪失と再生の表現としてもっと広く認知されて良い。
『スパイダーバース』でもその勘違いを深める迂路をとることで物語を文学的により深めることができたはずだし、誤解の解消の唐突さを考えれば実際にいくつかのシークエンスを用意しながらカットせざるをえなかったのではと勘繰ってしまう。
実際、作品の尺は2時間近くに達しており、この部分に限らずいくつかのシーンのカットを余儀なくされたのは想像に難くない。
ネットフリックス全盛の配信プラットフォーム時代において、脚本の妙や人物の掘り下げなどの文学的な部分はよりドラマ形式に流れ、映像表現の革新といった面はより劇場映画の形式に流れていくのは理の当然だろう。
そう、海外メディアがすでに解説動画を出しているように、『スパイダーヴァース』のアニメ表現はこれまでと次元を画す斬新なものであった。
4Ⅾ映像としての完成度やコミックの質感、エフェクト、色遣いなどをふんだんに盛り込んだコミカルな映像表現もさることながら、アニメやコミックの世界からやってきたスパイディーたちはより手描きの部分をふやして平面的に表現したり、フレームレート(1秒間あたりのコマ数)を単一のものから各シーン各キャラ毎に調整するなど、膨大な作業が手間がかかるためにだれも試みてこなかったことだ。
その意味で、この作品は新しい時代のまったく正当な芸術映画の最先端といえる。
ネットフリックスといえば、2013年の『ゼロ・グラヴィティ』で名を馳せたメキシコのアルフォンソ・キュアロン監督のオリジナル映画『ROMA』が、ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を獲っただけでなく、アカデミー賞の作品賞、撮影賞、外国語映画賞の3冠に輝き世間を驚かせたことが記憶に新しい。
冒頭の数分間を観るかぎり(そう、この映画の退屈さは僕の視聴に耐えられなかった、時間はあまりに有限だ)、長回し風のカットの繋ぎもろくに巧くなされていないこの作品がどうしてここまで高い評価を得ているのか不思議に思いたくはなる。
『ROMA』の流れる水の波紋を映しただけの約4分の1にも及ばない『スパイダーバース』の短いイントロ、そこにどれだけの創意工夫とダニエル・パンバートンによる情報量を巧みに操った劇音楽の盛り上げがあるかを思うと何ともやるせない気持ちになりたくはなる。
が、悲観することも驚く必要もないだろう、すでに僕が書いたとおり、エンターテイメント業界は奇妙なまでに保守的な風土なのだから。
この真に革新的なアニメ映画がひとりでも多くの良き鑑賞者に恵まれることを僕は願ってやまない。