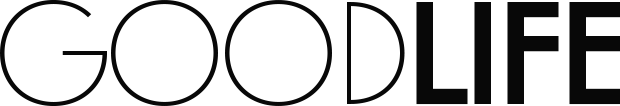ゲシャリーコーヒーの秘密兵器 FURUMAI
前回記事
Geshary Coffee の巧みな賭け、世界最初のゲイシャ種コーヒー専門店の分析
消費税 10%および軽減税率の導入により飲食店でのイートイン需要が冷え込むなか、国民総所得(GNI)は上昇しているにも関わらず、労働者の手取りにはほぼ反映されていないのが実態だろう。
率直に言おう。
私が GESHARY COFFEE に注目した理由に “ゲイシャ種コーヒー専門店” であることは関係がない。むしろ、この店の持つ最大のアドバンテージと勝算はコーヒーマシンにある。
FURUMAI と名付けられたそれは同社のグループ企業となる株式会社 TREEFIELD により企画・開発されたものであり、“世界初” の「全自動スペシャルティコーヒーマシン」とされる。
まず、注目すべきはその構造の複雑さである。GESHARY COFFEE の木原社⾧が元・大都技研の人物であるとは前回記事で触れたが、このコーヒーマシンにはかつてパチンコ・パチスロマシンの製造で培われたノウハウがグループ企業において応用されているのではないか……などと、下衆の勘繰りもしてしまうほどには高度な作りをしている。
本記事はそんな FURUMAI の機能について解説しつつ、その「バリスタ殺し」とも呼ばれる性能が果たして本当に職人芸を駆逐し得るのかについて、筆者なりの所感を述べるものである。

ゲシャリーコーヒーの使用する FURUMAI は内部構造を可視化した透明な本体をしている。これはコーヒーの抽出工程を一つのショーとして見せることを意図してのものらしい。(GESHARY COFFEE では、マシンと提供の待機スペースとの距離の問題で詳細には見辛かったが……)
コーヒー豆はマシン上部に備え付けのホッパーから投入するほか、一杯ぶんの少量豆用の投入口も設けてある。
内蔵されたミルは W グラインダー方式(分かりやすく言うと “コーヒー豆の二度挽き” )を採用している。二段階のグラインドで均一な粒度を実現するとのことだが、もう一つの特色は “チャフ(コーヒー豆中央部の溝にある渋皮)の除去機能” である。
1stグラインダーで粗く挽かれた粉が、粒度を整える2ndグラインダーへと移行する中間地点でファンが作動し、チャフを吹き飛ばす。除去されたチャフは専用のボックスに貯蔵される。なお、チャフは渋味などの雑味の要因とされる一方、適度に残すことで味わいの深みをもたらすともされることから、除去率はマシン側の調整でコントロール可能にしてあるようだ。
その後、粉はチャンバーと呼ばれる透明な筒状の容器に投入され、抽出工程が開始する。
つまり、豆を均一な細かさで粉砕しつつ、雑味の元となるチャフを取り除くことにより、コーヒーを雑味なく、安定したクオリティに仕上げることを可能としている。
そして、蒸らしの後に湯が投入され、容器内部に最大 4 気圧の圧力がかかり、粉に湯を浸透。その後、急減圧により粉の深部までエキスを引き出すという。仕上げにチャンバーをマシンの内部機構により回転させて攪拌、カップにサーブする設計になっている。
この史上類を見ない抽出システムは FURUMAI の持つ独自性の最たるものだ。特に、加圧と急減圧によるコーヒーの成分抽出という発想が新しい。
加圧状態を保ちながら粉を浸漬状態にし、そのまま急減圧により湯内にエキスを開放する方式は、エスプレッソマシンやスチームパンクなどの加圧方式で抽出するマシンと部分的に類似するが原理的にはまるで別物である。
これらのマシンの性能に単純な優劣を付けるのは難しいが、機構全体の性能を鑑みて、作り出せる味の多様性だけを見れば FURUMAI に軍配が上がると筆者は見ている。実際、前回記事の取材でテイスティングしたコーヒー二種を見てもマシンの性能の高さと味作りの多様さは見て取れた。
GESHARY COFFEE でコーヒーを注文すると、その銘柄の豆の情報や焙煎、抽出、簡単なテイスティング表の記載されたカードが付いてくるのだが、抽出の項目では FURUMAI によってどのような形式と目的で抽出されたかが丁寧に記されている。
たとえば「パナマ エスメラルダ農園 ウォッシュトマリオ3」の場合、弱い圧力を⾧時間かけながら浸漬状態におくことでゲイシャ種特有の香味を引き出したとある。事実、元々繊細で華やかな香味が持ち味かつ良い意味でコーヒーらしくないこの豆にとって、成分を強く引き出すようなアプローチは良さを殺すことになりかねないので理に適っている。
対して「コスタリカ ハシエンダコぺイ農園 ブラックハニー」においては、細挽きの豆を⾧時間浸漬し、チャンバーの攪拌を行うことでコーヒーらしい濃度とコクをもたらす意図が感じられる。カードに記載のあった “甘味” の表現に関しては、かえって攪拌が邪魔になっていた感はあるが。
いずれもプレス系マシンで抽出したコーヒー特有の液面の粉っぽい濁りがありつつ、ドリップコーヒーのように滑らかであったことは前回記事においても触れたが、それは上述した FURUMAI の各機能の “余計な雑味をもたらす要因を極力排除する” 神経質なまでの設計思想の賜物と言えるだろう。

FURUMAI は各抽出工程の詳細なパラメータ設定が可能だ。
項目は大別して――
- 豆投入
- グラインド
- 蒸らし・給湯
- 攪拌
- カップ送出
- メモ(恐らく、レシピ設定者による解説など)
となっているが、その下位項目はより多岐にわたる。こうして作成された抽出パターンはレシピとして登録可能であり、これは IoT(=主に電子機器などをインターネットに接続する機能)により世界中に存在する FURUMAI 間で共有可能となっている。
なお、一部のレシピは FURUMAI の監修に携わった世界各国の有名大会で優勝経験を持つバリスタが複数関わっている。こういった資本のかけ方にも開発サイドの “本気の博打” が見えて面白い。
この FURUMAI の登場をして「世界トップレベルのバリスタたちによるバリスタ殺しのマシン」と呼ぶネット記事もあり、なるほどそのように考えるのも無理はないと私は思う。
告白すれば、当初、本記事を書き始めた時点の私も同様の考えであった。大局的に見るならば、今後ドリップマンやバリスタなどの職人的な手仕事が、いわゆる音楽業界におけるピュアオーディオのように一部の物好きなマニアのものになってゆくだろうことは想像に難くない。
しかし、FURUMAI において、特定の豆に対する適切なレシピの作成を可能とするのは、それを設定する人間の力量である。事実、本マシンのパラメータ設定じたい、使いこなすには相応の専門技能が要求される。
また、よしんば膨大な対応レシピを登録してあっても、コーヒー豆というものは日々刻々とコンディションを変える繊細な素材だ。その時々にベストな対応を瞬時に行うには、ただパターンだけを数多く持っているだけでなく、自ら豆のコンディションを読む力が要求される。本当にコーヒーマシンが職人の手仕事を殺す日が来るとすれば、こうした思考・判断能力を持った AI が搭載された時だろう。
とはいえ、人間は往々にして職人という存在を神聖視するものであるし、殊、嗜好品という分野において、手仕事というのはそれだけで付加価値のあるものだ。おそらく、遠い未来においても、コーヒーマンの職人芸それ自体は何らかの形で残されて行くのではないだろうか。
今まで書いてきたとおり、“世界初” 全自動スペシャルティーコーヒーマシンの名を冠する FURUMAI はきわめて優れた性能と独自性を持っており、これを新興の日本企業が作り上げたというのは、国際的に凋落を続ける我が国にとって少し前向きな話だと筆者には思える。
かつてジャパン・アズ・ナンバーワンと賞賛された工業大国も今は昔、IMDによる世界競争力ランキング30位への下降や低コスト生産に優れた新興国の台頭、中国企業による日本の大手メーカーの買収など国際的に凋落を続ける現状において、過去の栄光を残り香のように漂わせるこのマシンはとてもロマンチックだと筆者は考えている。是非、この記事をお読みになったあなたにも、FURUMAIの作るコーヒーを味わってみて欲しい。