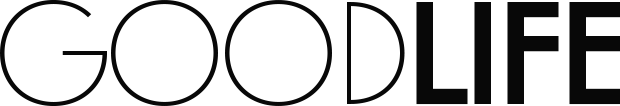NovelJam'[dash] 2019 にチームKOSMOSの編集者として参加されている加藤晃生さんから批評のご依頼を頂いたので書きます。
ご依頼は随時受け付けているのでご希望の方は遠慮なく申し付けてください。
ジャンル不問。
僕が対価としてもとめるのは僕の批評記事のRTのみ。
ノージャンル批評という特殊技能をもった人間の能力と時間、エネルギーをRTで買えるとおもえばかなり破格の条件ではないだろうか。
- 問答無用、斬捨御免。
- 原則、冒頭から読めた部分までしか読みません、時間は有限なので。
- 以下の批評は、羊谷知嘉個人の責任でおこなうものです。
- 反論歓迎。
- 批評をご希望の方はご依頼ください、批評記事のRTと引き換えに承ります。
- ジャンル不問。
オスマン帝国領エジプト、ポート・サイド。ここからヴェネチアまでは、三日と少しの船の旅となる。
八王子で織物商をしていた祖父が御一新の頃に始めた貿易商を、伯父とともに継いだ父は、わたしが子供の頃から買い付けで世界各地を飛び回ってきた。旅先の出来事を綴ったわたしの日記帳も十冊目。十六歳の誕生日にもらったばかりの万年筆も、新しい旅のはじまりの気分を高揚させた。
via. 森きいこ『天籟日記』
オスマン帝国? エジプト? 八王子?
いつの時代の話だよ、ハァ?!と思ったあなたは既にこの作品の術中にハマってしまったかもしれない。
日清戦争終結後の19世紀末、大清の隣にある架空の小国・天籟のお姫様が欧州にあるこれまた架空のクリークヴァルト公国に嫁ぎにいく船旅の道中、正確にはエジプトのポート・サイドからヴェネツィアへと向かう大型客船が物語の舞台だ。
藤原霞という日本の若い女性がなぜ語り手に設定されているかというと、日本で唯一天籟製の更紗を輸入している貿易商の父がその仕事の関係から姫君の輿入れの通訳として同行を求められたからだそうだ。
そして、乗船した船には姫と歳の近しいものがいなかったのだろう、語り手のカスミが彼女の話し相手として見初められたことが文化的背景も社会階級も異なる彼ら彼女らのエキゾチックな物語の交点となる。

まず、作者の森きいこの小説作品として観た場合、その出来はかならずしも褒められたものではない――控えめな言い方をすれば少なくとも僕の評価する作品ではない。
たとえば、書き手の会話表現に注目して観てみると、「はあ」「ええ」「まあ」などの会話を進行させるためだけの情報量の乏しい間投詞や長音符を複数連ねたマンガ・アニメ的表現がめだち、「〜よ」「〜わ」といったおそらくは意識していないマイルドな女性語が目立つことから書き手が登場人物を記号として扱っていることがわかる。
もちろん、語り手の英会話を女性語で表現することは時代背景を考えればおかしくはない。
しかし、意識的な表現としては作り込みが甘く、手癖の表現としてはやや安直に過ぎ、19世紀末の物語といえども現代の書き手から読み手に渡ると考えると質的にも政治的にもその感覚の古さには疑問を覚える。
また、大きなところを指摘すれば、エジプトの港湾都市からヴェネツィアに渡る船旅の途上、架空のアジアの小国の姫君とその幼い付き人、日本の貿易商の娘、文化的背景は不明だが若い男性甲船員(後日販売開始された彼のアクリルキーホルダーを観る限り、薄い褐色の肌に黄土色の髪色、碧眼といった身体的特徴からおそらくヨーロッパ寄りの地中海系人種と推測される)と、実に興味深い文化的混交さを湛えた舞台設定と人間関係を用意しながら、書き手の筆致があまりに薄く、この複雑で微妙な作品世界を読者に納得させられるほどの説得力をそのディテールにもたせられていない。
特に冒頭の2段落は、エジプト、ヴェネツィア、八王子とあまり結び付きにくい言葉が短い間でならんでいるにも関わらず、それを支えるディテールが致命的に欠けているため作品世界があたまに入ってきづらいのが正直なところ――おもうに作者の森はディテールの積み重ねで物語を動かすのではなく、自分の頭にあるプロットを言葉としてアウトプットするタイプの書き手なのだろう。
その意味でいえば『天籟日記』の作品コンセプトはノベルジャムという即興小説向きではなかったかもしれない――裏を返せばきわめて野心的な試みだ。
実際、『天籟日記』のこうした作品世界の微妙な舞台設定には編集者の加藤晃生がある種の考証役として大きく寄与しているだろうし、この作品の魅力の何割かは澤俊之の『We’re Men’s Dream』と同様にイラストレーターのこばじによる厳しい時間制限内の仕事としてはかなり出来の良い表紙の力に拠っている。
ノベルジャムの標準フォーマットには反するが、『天籟日記』ほど良い意味でも悪い意味でも複数枚の挿絵を読者に欲しがらせる掌編はそうそうあるものではないだろう。
それをどちらの意味で評価するかは読者により分かれるだろうが、いずれにせよこの作品があくまでチームKOSMOSのプロダクトであり、キャラクター文芸という見た目以上に即興作品としては非常なレベルの高さに挑戦したことは疑いえない。
『天籟日記』をある種の原作と観た場合、森きいこは少ない文字数のなかで4人の主要登場人物を記号的に形づくるという意味では堅実な良い仕事を果たしている。
それは、チームの営業成果でもあるだろうが、『天籟日記』の原作者以外の手による派生作品がすでに複数篇(編集者の加藤によるものも含む)電子書籍として公開されていることからも伺えるだろう。
森の書かなかった余白は良かれ悪しかれきわめて大きい。
しかし、作品コンセプトの大きな魅力とあいまり、『天籟日記』の読者や関係者にそのポテンシャルを引きだすべくさらなる創作に向かわせているなら結果オーライといえ、はじめからそのユニバースの拡大を狙ったものであれば恐るべき大胆さといわざるをえない。
森の残した余白から今後何がでてくるかはわからない。
チームKOSMOSの度量とクリエイティヴィティがそこで試されるのはまちがいなく、彼ら彼女らの闘いと結果によってはインディーズ文芸作家の新しいロールモデルになるだろう――その意味で『天籟日記』を読者がどう評価しようとも今後のプロダクト展開から眼を離せない。