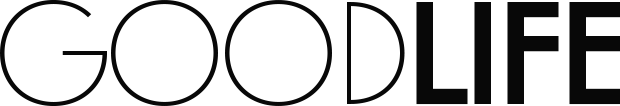NovelJam'[dash] 2019 にチームKOSMOSの編集者として参加されている加藤晃生さんから批評のご依頼を頂いたので書きます。
ご依頼は随時受け付けているのでご希望の方は遠慮なく申し付けてください。
ジャンル不問。
僕が対価としてもとめるのは僕の批評記事のRTのみ。
ノージャンル批評という特殊技能をもった人間の能力と時間、エネルギーをRTで買えるとおもえばかなり破格の条件ではないだろうか。
- 問答無用、斬捨御免。
- 原則、冒頭から読めた部分までしか読みません、時間は有限なので。
- 以下の批評は、羊谷知嘉個人の責任でおこなうものです。
- 反論歓迎。
- 批評をご希望の方はご依頼ください、批評記事のRTと引き換えに承ります。
- ジャンル不問。
「こっこ、こっこ」と、鶏たちがエサをついばむ音が静やかに響く。
わたしは乾燥したコーンを足しながら鶏たちの様子を見守る。
食欲旺盛でなによりだ。卵を藤かごに集める。実家の家業は養鶏。一人娘のわたしがこれを手伝うのは当然のことかもしれない。
高校を卒業してから八年が経過していた。
二十歳前後の頃、自転車の鍵を耳許で振り鳴らして心の落ち着きを取り戻すのが癖になっていた。
鬱が酷いときには世界が灰色になるとか色褪せてみえるとかいうけれど、鬱ではない別の心の病なり障害なりに独り苦しんでいたあの時の僕の世界はいつも砕け散る崩壊の予感とグルグルの轟音に支配され、動悸と息苦しさとともに視界が霞みだすまえに耳許で鍵を振りそのランダムな高音で現実に呼びもどさないと生きていけなかった。
少なくとも、当時の僕にはそうとしか思えない無明の苦しさに焼かれていた。
原因はわからない。
たぶん、原因と結果という単純な因果律を超えた仕組みでヒトの記憶が作動しているからで、心の不安定を克服したいまでも予期せぬ記憶の想起に始終苛まれていることからもいわゆる時間の流れを超えた場所に記憶があることは痛感できる。
澤俊之の掌編「We’re Men’s Dream」の語り手サツキもまた、ブラック労働に心身を病み、音楽を挫折した記憶の想起に苦しめられているらしい――少なくともを設定の上では。

……記憶力には自信がある。曲は一回聴いただけで覚えられるし、そして忘れない。でもそれは単なる特技で、自分の意志で身に着けたものではなかった。(中略)それに諸刃の剣でもあった。「忘れたい思い出も忘れられない」のだ。音楽への挫折は今までの人生でいちばんつらいものだったのだけれど、時折、そして突然その記憶がくっきりとリフレインされる苦しみは、これからも続くのだろう。
興味深いのは、語り手が実際に記憶のフラッシュバックを体験している場面や描写が全くないことだ。
小説版ハッカソンと銘打ったノベルジャムには執筆時間と文字数に厳しい制約があるため、参加作品として観る場合には完成度の高さや要素の豊富さなどにはある程度寛容に臨むのが作家作品にフェアな態度というべきだろうが、悲惨な過去という重要な人物設定を数行の説明だけで済ますのは影のない静物画を描くようなものだろう。
当然、陰影がなければオブジェクトの量感は表現されず、作品空間が歪なことを意味する。
残念ながら冒頭の性急な説明だけで語り手に感情移入するほど僕はナイーヴではないし、作品に書かれていないことまで自由に読み込むほどうぶな読者でもない。
また、ある種の即興小説には求め過ぎかもしれないが、語り手の語りがいまどきの20代後半の女性を表現するにはいささか硬質で、書き言葉めきすぎ、宮城の音楽フェスの出演に向かう途中で迷子になったガールズバンドの「〜っス」口調もさすがに陳腐で滑稽に映るといわざるをえない。
ロックにヒップホップで対抗する意図はないけれども、フリースタイルラップバトルでもIDや裂固のような優れた才能ある若いアーティストがその言葉の内容だけでなく音楽表現としてもきわめて高い水準の即興ラップをしていることを踏まえれば、澤の文章表現には文学作品としていささか不満が残ると評することは即興小説に対するフェアな批評態度の範疇におさまるだろうか。
その意味で、本作は物語の内容としては「できすぎ」た夢のようにふわふわと現実感のないものに感じられ、文章表現は言葉自体への透徹した意識を感じさせるほど良く練られたものではないだろう。
エンタメ作品として観た場合には澤の「We’re Men’s Dream」はどうだろうか?
楽しめるかもしれない。
文学的修辞もまま散見されるため羊頭狗肉感が否めないが、イラストレーター枠で参加のこばじによる世間ウケの良さそうな少女の表紙は彼の作品のキャチーさを力強く支えている。
文量の割には主要登場人物が語り手とガールズバンド3人組とやや多く、澤のおそらくは慣れていないであろうエンタメ作家としての筆致では彼女らの可愛らしさに属性を盛りきれているとはいえないが、今後の創作というか展開のタネとしてはよく機能するものを制限時間内で書きあげたという意味では十分評価できるはずだ。
というのも、ノベルジャムの面白さは作品が書きあがったあとのプロダクト展開がチームとしての審査対象になるからで、チームKOSMOSの公式ホームページから確認できる限りでも著者本人によるスピンオフ小説がすでに3本公開され、作中に登場する舞茸鍋のレシピがクックパッドにあげられ、各キャラクターの缶バッジやアクリルキーホルダーが販売開始されている。
完結した文学作品としてならまだしも、チームKOSMOSのプロダクトとして評価するのはその意味ではまだ時期尚早かもしれない――少なくともそう感じさせる作品のポテンシャルはあり、プロジェクトチームの熱量はいまだなお衰える兆しをみせていない。