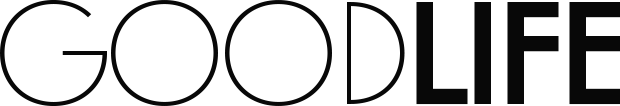仮面の裏のバセドウ病とパニック障害
オーストラリア出身の遅咲きの世界的覆面歌手 Sia を知らないひとはいないだろう。
2014年に発表された ”Chandelier” は当時の日本でもラジオや有線で散々流れたし、その奇抜なファッションや彼女のMVに出演するマディー・ジーグラーの不器用なダンスが好きなひとも多いはずだ。
個人的には、彼女が世界的に有名になる契機となったデヴィッド・ゲッタとの “Titanium” や “She Wolf”、あるいはバズ・ラーマン監督の傑作『グレイト・ギャツビー』での力強い歌唱が印象に強いミュージシャンだ。
今回の記事では、先日公開した秋津燈太郎さんとの雑談動画ではカットせざるをえなかったシーアの顔を隠し続ける意味について書こう。
ちなみに彼女は歌が上手い。
オートチューンやポストプロダクションの作業でその質をいくらでも変えられる現代ではメジャーシーンでこれだけの歌唱力を誇れる歌手はきわめて稀だろう。
――だれが何を言ったかは重要だ。
これは、フリースタイルダンジョンの評価の仕方をめぐる僕の動画内での秋津さんの鋭い発言だ。
詳細は動画をご覧になっていただくとして、表現と表現者をどの程度結び付けるかは評価者にとって難しい問題であり、どの程度の結びつきの強さを前提に振舞うかは表現者にとって苦しい壁だ――つまり、生身のからだをもった表現者と、表現あるいは作品、そして、ペルソナとしての作者像という三者関係の複雑な問題だ。
大前提としてまず、批評畑には耳タコのロラン・バルトを持ちだすまでもなく、評価者にとっては表現と表現者を強く結び付けることはご法度中のご法度だ。
控えめにいっても、鑑賞行為においては生身のからだをもった表現者のディテール――性別、年齢、地位、国籍、宗教、美醜など――はカッコに入れて保留し、忌憚なき気持ちで作品を観る必要がある。
そうでないならば、作品や表現の価値はそれ自体ではなく生身の表現者のありようで決まるため、表現活動、創作活動よりも、自身の好感度をあげるパフォーマンスやネットワーキングに心血を注いだ方が職業作家としてはるかに合理的だ。
そして、現実のエンターテイメント産業はその合理性を中心に動いている、残念ながら。
映画や音楽、デジタルゲームといった市場規模の大きい娯楽産業の超大作に付けられる莫大な広告費やキャスティング費用、人気ミュージシャンによる頻繁なコラボレーションの契約料などは等しく、メディアやインフルエンサーに話題を振りまき、作品の世評という名の付加価値を増すことに消えている。
大衆は個としての趣味を主体的に選択・判断できないというメッセージを暗に発しているといったら言い過ぎだろうか?
反対に、たとえば詩のようなより市場規模が小さく、少数者のための分野はどうかというと、前回の僕の雑談動画をご覧になったあなたはもうご存知のとおり、ネットワーキングが物をいう世界だ。
要するに、評価者にとって「だれが何を言ったかは重要」でないし、そうあるべきだが、現実には大半のひとにとって「だれが何を言ったかが重要」である以上、作家、あるいは表現者はそれを前提に、自分のより好ましいペルソナを創りあげるためにパフォーマンスしてネットワーキングしなければならないのだ。
特に日本では、美人すぎる〇〇が一時期メディアに大量発生し、就職活動では顔写真の添付が履歴書で必須なように、この「だれ」という部分が重要視され、建前としてすらこの「だれ」に潜む差別性が問題視されることはない。
秋津さんとの収録ではここからなぜミュージシャンの芸術的な寿命が短いかという話に進んだのだが、この記事ではシーアのより具体的な話にもどろう――ミュージシャンが創造的であり続けられる時間はそう長くはない、ヒップホップ界の帝王カニエ・ウエストですら免れえないように。
シーアの歌姫としての国際的なブレイクスルーが40歳を手前にしたときだったのはなんとも驚きだ。
1990年代半ばに地元アデレードのジャズバンドのヴォーカルとしてキャリアを歩みはじめたシーアは、商業的成功を求め、ロンドン、ニューヨークへと居を移していく。
2007年までに彼女が発表したスタジオアルバムは3つ、どれも鳴かず飛ばずといったところだったらしいが、4枚目の “Some People Have Real Problem” はキャリア初のUSビルボードにランクインするアルバムとなった。
2010年にはクリスティーナ・アギレラの主演映画に書いた曲がこの年のゴールデングローブ賞にノミネートされ、同年発表のスタジオアルバム “We Are Born” はオーストラリアに留まらず北米・欧州圏での知名度を高めることに成功した。
しかし、グローバルな音楽的成功を収めるにつれてシーアの心は名声の対価に深く蝕まれていったようだ。
この頃にはすでにライブツアーのプロモーションを拒否し、ステージ上では仮面を被り、薬物(ドラッグの類ではなく医療用薬物らしい)とアルコール中毒の沼にハマって自殺願望にとり憑かれ、バセドウ病とパニック障害に苦しんでいたという。
そして、アーティストのキャリアから引退し他人の曲を書くソングライターとして再出発しようとしたその年、アリシア・キーズのために書いた曲 “Titanium” がそのデモ版の歌唱に眼をとめたデヴィッド・ゲッタによりシーア自身とのコラボ曲としてリリースされ、欧米各国でトップ10にランクインするグローバルな大成功を果たした。
もちろんその名声はシーアにはかならずしも喜ばしいものではなかった――というのも、彼女はアーティストではなく裏方のソングライターになろうと努力しはじめたばかりだったのだから。

その後のシーアの活躍はあなたの知るとおり――2014年発表の6枚目のスタジオアルバム “1000 Forms Of Fear” は豪州だけでなくカナダや北米でも1位を獲り世界中でプラチナディスク認定、2016年発表の7枚目 “This Is Acting” も世界各国でトップ5にランクインを果たした。
シーアの覆面のウィッグは、彼女のきわめて個人的な精神的事情に由来することは疑いえないが、しかし、結果的にその一風変わったペルソナが彼女の有効なプロモーション戦略として奏功したのではと疑うことはできる。
実際、彼女の代表曲となった “Chandelier” は、若年期特有の承認欲求に飢えた少女とその性の利用を見事に描いたもので、若いときの性体験に失敗の覚えがある女性にはかなり痛切に響く歌詞だ。
(以下、翻訳はすべて羊谷知嘉)
I’m the one “for a good time call”
わたしは都合の良いオンナ
Phone’s blowin’ up, ringin’ my doorbell
携帯電話が鳴き、玄関のベルが鳴り響く
I feel the love, feel the love
わたしはそれに愛を感じるの、たしかな愛を、ね
文学的観点からコメントすれば、シャンデリアからぶら下がってブランコのようにスイングするというこの歌詞の象徴的なイメージが、直接的には鳥の羽ばたきに喩えられると同時に、客観的にみれば向こう見ずな行為で、シャンデリアから首を吊るという自殺の暗喩でもある複層性が少女の刹那的な生き方をより良く映していて面白い。
But I’m holding on for dear life
でも、わたしはこの手を離せないでいる
Won’t look down, won’t open my eyes
見下ろしたくない、眼をあけていたくないの
Keep my glass full until morning light
おねがい、朝陽が昇るまでお酒を注いでいて
‘Cause I’m just holding on for tonight
だってわたしには今夜だけなんだから
もちろん、こうした少女の心理を鋭く突いた歌詞が、前述のマディー・ジーグラーの不器用でかつ痛々しい踊りを前面に押しだしたプロモーションと相俟ってより広くより深い共感を呼んだことは想像に難くない――そして、リスナーの強烈な共感作用の前ではアーティストのディテールはすべて華やかなウィッグの裏に隠してしまった方が都合が良いことも。
この記事の執筆時点でのUSビルボードを試しに観てみよう。
TOP100位中、女性シンガーや彼女らを擁した音楽グループの楽曲はフィーチャリングも含め全体で29、そのなかで30代半ばを過ぎているのはビヨンセとピンクの2人――お情けで(?)レディー・ガガとケイティ―・ペリーを入れてもたった4人。
彼女たちがそれぞれのジャンルの大御所中の大御所で、20歳過ぎの若いときからスターダムの道を歩んできた女王と考えると、40歳を目前にして世界的なポップシンガーとしてブレイクスルーを果たしたシーアがいかに稀有な存在かわかるはずだ。
精神的な病を抱えていてもなお今も精力的に活動していることを考えると、シーアの覆面ウィッグは彼女自身にとっても功を奏しているようだ。
今の音楽シーンで唯一無二であり彼女のアイコンとなっているそのペルソナは、オーディエンスの欲望と、彼女の暗さを抱えた複雑な精神との適正距離におそらくは戦略的に作られた、前者の幻想と後者の人生を守る仮面として機能しているのだろう。