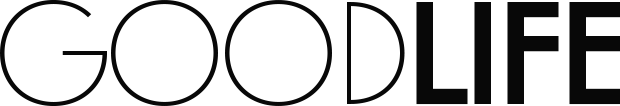キレイと汚いの感覚は、雑食動物の私たちには奇妙に根深い知性のデザインだ。
普通、京都の名で想起される花の市街地は、旧平安京の東限・鴨川の上下流域の南北でゆるやかに傾斜し、上流域は文化的な富裕層エリア、今の京都駅以南はもともと6つの村に分かれていた経緯もあり、下流域は田舎の郊外に住みわかれている。三方を低い山に囲まれた盆地と、鴨川、桂川、そして、琵琶湖の約8割の貯水量にも及ぶ豊富な地下水に恵まれた地形上、腐敗と疫病の地の低さから逃れ、より高く、風通しの良い土地を好んだのは想像に難くない。
実際、京都の西の山際の嵯峨野・嵐山は貴族たちの絶好の別荘地や行楽地であり、上賀茂・下賀茂の両神社や大徳寺に代表される洛北はもちろん、八坂神社にはじまり、銀閣寺、南禅寺、高台寺、東福寺、清水寺、豊臣廟を抱える洛東はいわば信仰と修行の高地であった。ひとことでいえば、都市生活の「外部」である。
外部といえば、娯楽作家・森見登美彦の『夜は短し歩けよ乙女』の舞台、鴨川の西岸沿いの花街・先斗町は、江戸時代初期の護岸工事までは鴨川の大きな中洲であり、乞食や遊女や芸者のいわゆる河原者が舞台や見世物小屋をひらいて暮らす低地であった。おなじ鴨川西岸のさらに南の通り、下流域の河川敷きは、中世の頃から牛馬の屠殺や死体処理、皮なめしの仕事に従事する者が長く暮らしを営んできた被差別部落の祟仁地区。部落解放運動の全国水平社が創設されたことで知られる。
もちろん、皮剥ぎや肉剝ぎを差別したのは日本に限らない。インドの最下級カーストに位置する不可触民は、屠殺や皮剥ぎ、糞尿の汲み取りなどに従事し、中世ドイツでも皮剥ぎは刑吏と同じ賤視の対象とされた。被差別であるから当然、彼らに触れたり話したり見掛けたり食事をともにしたりすれば賎民に堕ちる、普通にいえば、ケガレが感染ると見做された。
同様に、山岳信仰が今の京都にも色濃く残るだけでなく、世界各地の文明社会には太陽崇拝があまねく見受けられ、初期キリスト教では地の足ではなく天の頭が霊界に繋がるキレイな身体部位と考えられていた。なにより、ピラミッド然り、ストーンヘンジ然り、各地域の寺院・教会建築然り、文明社会による重力という自然体の克服は、人類の高さの信仰と低さの蔑視という基礎的な知性のデザインに裏打ちされている。
16世紀末、日本初の武家関白・豊臣秀吉が、黒漆塗りの大阪城の天守閣を市街地からよく観えるように位置や街路に工夫を凝らしたのもこの当然の仕組みを感覚的に知っていたからにほかならない。


人間は、雑食動物のジレンマを生き抜いてきた。
特定の草木や果実、動物に食糧を依存する偏食型の動物とは違い、雑食動物はその食料となる生き物の生息域に活動領域を縛られずに繁殖範囲を拡げられる、が、それは同時に、何が食べられて何が食べられないかの選択とその知識の蓄積に命が賭けられていることを意味する。私たちがいま食べているものとそうでないものの識別は、夥しい死と苦しみの集団的な経験の記憶に彫琢されたものだ。
むずかしいのは、私たちの鼻と舌からの信号処理を司る脳の古い部分・島皮質が、雑食動物の命を支える食物情報処理センターに留まらず、人間の嗜好全般を導く重要な器官になったことだろう。たとえば、道徳に反する行為やごくありふれた不正、あるいはとりわけ嫌悪を催す何かを目にしたときにも活性化するようになった、と、アメリカの社会心理学者ジョナサン・ハイトは語る。
つまり、私たちは食に限らず、物事全般に対しても雑食動物の延長として振舞うよう進化のデザインを被った。以下は、ハイトが紹介するおならスプレーの実験。
スタンフォード大学の大学院生アレックス・ジョーダンは、嫌悪をもよおす臭気を密かにまいておき、その間に被験者に道徳的な判断をさせるというアイデアを思いついた。……彼は、キャンパス内の歩行者通路の交差点に立って簡単な調査票への記入を通行人に依頼する。内容は、いとこ同士の結婚、あるいは監督が被験者を騙してインタビューに答えさせることで制作したドキュメンタリー映画の公開など、物議を醸しそうな4つの問題を判断させるものだ。
被験者の半分には普通に調査票に回答してもらうが、もう半分には次のような細工をする。インタビューを始める前に、まず近くのごみ缶をからにし、ビニール袋を入れておく。誰かが歩いてくるのが見えたら、おならスプレーをビニール袋のなかに2回ほど噴霧する。すると歩行者交差点の一帯は、数分間臭いが立ち込める。そしてその状態で被験者に回答してもらう。
その結果、悪臭をかぎながら質問票に回答した人は、より厳しい判断を下した。また、苦い飲み物か甘い飲み物のどちらかを飲んだ後で質問票に答えてもらうという実験を行った他の研究者も、同様の効果を見出している。……私たちは、何かについての考えを決める際、内面を観察して、どう感じているかを確かめる。そして、よい気分がすれば「それが好きに違いない」と考え、不快であれば「嫌いに違いない」と思う。
via. ジョナサン・ハイト『社会はなぜ左と右に分かれるのか』

ここで、京都の街なみの地形の高低差が自然のゾーニングを生んでいることを思い起こそう。相対的に低い場所は都の文化の外れに、公権力の及ばない川岸には社会のあぶれ者と被差別民が住み、富裕層はより高地に暮らし、東西の山際には貴族たちの遊興地や寺社がひらかれるーー。
私たちのキレイと汚いの感覚は高さと低さの文化的な関係と繋がっている。両者を結びつけるのは、食と毒、公衆衛生の死屍累々たる集団的経験の圧縮である。そして、私たちの自然のデザインは、万事につけ、同様のやり方で判断する。キレイか汚いか、快か不快か。両者の転倒、すなわち、倒錯嗜好はあっても中間はない。
このような効果を得るには、嫌悪感を引き起こす必要すらない。手を洗いさえすればよいのだ。トロント大学のチェンボ・ゾンは、質問票に記入する前にせっけんで手を洗わせると、被験者はポルノや麻薬などについての道徳的な潔癖さに関する問いに答える際、より厳しい判断を下すようになったと報告している。身を清潔に保っていると、汚れたものを遠ざけようとするのだ。
ゾンは、不道徳が人々に手を洗わせるという、逆方向の効果も報告している。自分のした不道徳な行為を思い出すよう言われたり、誰かがした不道徳な行為の報告を書き写すよう指示されたりした被験者には、清潔さについて考えを巡らし、体を洗いたいと強く思い始める傾向が見られた。実験が終わった後で、謝礼として用意した日用品から好きなものを選ばせると、お手ふきなどのクリーニング用品を選択することが多かった。ゾンはこれを「マクベス効果」と呼んでいる。この用語は、ダンカン王の殺害を夫に指嗾したあと、強迫的に手を洗うようになったマクベス夫人にちなむ。
言い換えると、私たちの身体と<正義心>のあいだには、両面通行の道路が走っている。
via. ジョナサン・ハイト『社会はなぜ左と右に分かれるのか』
だから、ハイトは人間のからだと道徳感情だけでなく、地形と、その上に繁茂する文化の地層にまで考察を進めるべきだった。というのも、人間の本能というべき私たちの自然のデザインの、数百万年、あるいはそれを優に越える進化論的な記憶の深さにまで想いを馳せない限り、なぜ、差別がなくならないのか、キレイと汚いのおよそ非科学的なイメージに延々振りまわされているかを感覚的に解せないからだ。
畢竟、私たちは、その精神は、進化史の無数の亡霊たちに憑かれている。