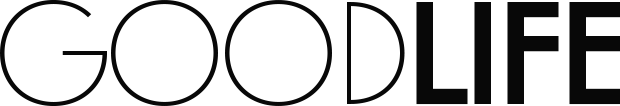fureai
午前八時のカノン、その、安いオルゴールの時報を僕らは聞き流す。余白の霧が立ち込める、開店間もない喫茶店が蠕動している。漆喰の壁が、ニスの剥げた木床が、呼吸に上下している。僕らは四人がけのルビンの壺に相向かいで腰を沈める。僕は通路側に頭を向けて、君は窓を背にあくびをして。
鼓膜が捉える音の数々。たとえばそれは電動ミルの駆動音。たとえばそれは湯を噴き上げるポット。その脇で鳴く蛙の声や、彼方に谺する怪鳥の囀り。それらを背後に感じるたびに、僕らの食卓に並ぶコーヒーとトーストが刻一刻と出来上がるのがありありと目に浮かぶのだ。
君はさっきから、眠そうな目を少し、楽しげに細めて、目の前の陰画の壺であると同時にテーブルでもある、それに植わったポトスの葉っぱを突っ付いている。すると、ふいに、僕の方へと視線を向けて。
「ねえ、ここ、ダルメシアンだよね」
と言って笑う。悪戯に歯を覗かせる、君の指先がなぞる緑葉にひろがる、白いまだら模様の一角を僕は君のようにみることが出来なかった。
「馬じゃないかな?」
そう、僕が言うと、周囲の霧がほのかに、虹色を滲ませる。スピーカーから流れる月並みな“Waltz for Debby”に混じって、鼻を鳴らす音や、舌を出して息を弾ませる声が聞こえる。
呆気に取られる僕の目の前にさり気無く差し出されたトーストとコーヒーのセットに、少し、驚かされる。ひとり勤務らしき、喫茶店の若い店員の顔を覗くが、像が曖昧で、輪郭を結ばない。
あらかじめバターを塗られた、二等分の山型トーストを僕らはかじる。君は山のほうから、僕は底のほうから手をつけた。そんな、偶然や気分にすぎない選択にすら胸がざわつく。
考えすぎだと頭を振り、量産品の白磁のカップに注がれたブレンドコーヒーを啜る。やや深めに煎られた豆を使ったのを感じさせる、この香りと風味は脳裡にあるイメージを喚起した。
「これ、中東の夕焼けっぽい感じする」
ふと、呟いた僕の意見に、君は首を傾げて、
「わたしはウェス・モンゴメリだなぁ」
と返した。その身体で、『考える人』を象る。トーストの皿の脇に添えられた小鉢のなかで痩せたサラダのうえにとうもろこしが咲いている。それにたっぷりとドレッシングをかけた。どっぷりと灰色だった。窓を染め上げる空模様は。空を、鮫が泳ぎ、歯形を残してゆくと、その穴という穴から水銀が垂れて、この都市に降り注いだ。
僕らの、食卓の壺にも降り注ぐものがある。落ち葉だ。空のしたでつちかわれた、その葉脈を僕らはとく。沸々と、足下に粟立つものがある。床の底で黒く、種が割れて芽吹く。床に、触れてみる。温かくて、マスカルポーネチーズのようにしっとりと、柔らかい。この感触には覚えがある。そっと、撫でてみる。手の平が捉える稜線は、女の脇腹のくびれから臀部にかけての起伏を想起させる。僕はそれをよく知っている。耳を、あててみる。心臓の鼓動と、血液の迸る轟音が低く、重く、響いている。この音にも、僕は親しんでいる。君だ。これは、君の身体なのだ。
そう、気付いた瞬間、僕の全身が床に沈み込んだ。藻掻いても、足掻いても、更に更に呑み込まれてゆく。君はフォークからレタスの葉を落として、豆鉄砲を食らった鳩の目をして硬直している。無理もない。僕にも訳がわからないのだから。
頭から爪先までずっぽりと埋まりきった暗闇のなか、窒息への恐怖に苛まれながら脱出を試みてじたばたしているうちに、ふいに、吐き出された。未知の空間の、未知の底部に、なんとか足をついて着地し、立ち上がると――ここは僕らの同棲するアパートの寝室だ。振り向くと扉があり、その左手には本棚が置かれている。天井の照明は常夜灯が点いていて、引っ越してきたときから変わらない、退屈な白い壁紙を橙色に染めている。床には黒猫のパターンが描かれたカーペットが敷かれている。扉の向かいの小窓にかけられたカーテンは最近新調したばかりで、綺麗なキャメル色をしている。
「ねえ、書いてよ」
小窓の下に設えられたタブルベッドのほうから、声がする。君の声だ。だが、君の姿は見えない。
ふと、扉と本棚のあいだに立てられた姿見を覗いてみる。そこには部屋の風景以外には何も映り込まない……僕の顔すらも。
なんてこった、僕らはすっかり透明になってしまったのだ。これはどうにかしないといけない、と思い付いて、目についたのが右手の机の上に置かれた、二本の筆ペンだった。
僕は透明な手で筆ペンをとる。数秒後、足音が響き、もう一本の筆ペンも宙を浮き、僕の鼻先で静止する。君がそこにいるのだと、即座に悟る。僕と君は同時に蓋を開けて、互いの顔の位置に筆先を伸ばした。
僕らは各々の記憶を読み返しながら、描く。君の/僕の、鼻梁を、瞼を。眉根を、唇を。顎を、頬を、うなじを、耳を、髪の一本、一本を。その途中、姿見を覗く。僕らはまるで、元の姿と似ても似つかない。外見容姿についてすら、こんなにも覚え違えをしていたのだと気付く。いや、きっと、元から正しくなんて見てもいなかったのだ。
悔しさの余り、書き直そうと、机の脇に置かれたティッシュを引き抜いて拭う。拭うと、ますます、墨が滲んで、似顔絵は拙さを増してゆく。だが、拙さが増せば増すほどに、僕らは互いの全身を舐めるように、愛撫するように、筆遣いを真摯に、精緻にしてゆく。
「ここ、ほくろあったよね」
「うん。……もうちょっと左」
胸を、腹部を、臀部を、陰部を、太股を。描いてゆく、その傍らで、ふと気付く。僕らは永遠に分かり合えないがゆえに、永遠に分かり合おうとするのだと。
瞬間、視界に光が差した。右側の壁に掛けられた、フランスパンを抱擁する洋梨の描かれた油絵が、柔らかな金色に包まれて発光するのを僕らは見た。そして、洋梨の背後から、あの喫茶店の店員が油絵のタッチで顔を出した。その顔が、牡蠣貝の変質したオパールのように輝いて、僕らを照らした。
しばらく見惚れてしまってから、はっとした僕らは、すっかり歪になってしまった瞳で見つめあい、ぐにゃぐにゃの身体と唇で、抱擁と接吻を交わした。すべて、これでいいのだという気持ちに満たされながら。